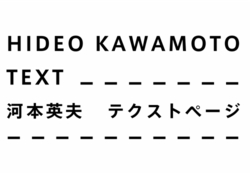クワスあるいは存在の裂け目
河本英夫
規則とオペレーション 2000年前後に問題にしたことだが、規則とオペレーションの間には、どのような意味でも対応関係はなかった。58+67=125という演算は、たとえ規則に従って回答した場合でも、それがどのような規則なのかは決まらなかった。そこからいくつもの可能性が出てくる。まったく別のオペレーションを行って回答に到達した場合、いくつかのエラーを含みながら結果はあっている場合、規則に従うというやり方とはまったく別のことを行っている場合のように、いくつもの可能性が出てしまう。クリプキが『ヴィットゲンシュタインのパラドックス』で行った懐疑は、予想外の仕方で、コンピュータ・ソフトの内実に関連している。そのことは行為と規則の間には、まったく別様のつながりがあったということであり、そうしたことの内実は当分明らかにならないだけではなく、解明の現実に限界がある、という問題であった。
科学哲学として重要な問題なので、再説する。ニ十世紀後半の思想上の哲学的大発見のひとつに「存在の裂け目」と呼ぶべきものがある。数多くの謎を提供し、数多くの議論と誤解を巻き起こしてもきた。クリプキの懐疑がある。私的言語批判を意図したと本人が表明している議論である。内容は次のようなものである。いま単純な算術を実行する。58+67=125を行ってみる。初等算術のトレーニングを少し積めば、誰であれ解答することができる。しかも正解を出すことができる。このとき58+67=5だと言い張る人が現れたとする。麻薬で思考障害が生じたのでもなく、キレたのでもない。懐疑を行っているのである。
いまかりに誰もまだやったことのない大きな数字の足し算を想定する。このときまだ誰もしたことのない演算であれば、足し算がどのような意味で、また規則がどのようなものであるかはわからない。足し算の意味は現行の行為の範囲で対応可能なものであるかどうかはわからないのである。だから足し算の記号によって意味されているものは現に行為してみなければわからないことになる。そこで足し算のような単純な演算行為でさえ、いつも「暗闇のなかの跳躍」であることになる。
ここで指摘されていることの範囲内では、かりに規則と呼ばれているものであっても、それが明日どうなるかはわからず、そしてさらに明後日どうなるかはわからないというものである。一般には未来の未決定であり、それを「暗闇の跳躍」という大袈裟な言葉で表現しているにすぎなくなる。未来はいつも現にそれが到来してみなければわからないということを、大袈裟な道具立てで語っていることになる。未来が未決定であることは、帰納の原理を制約するものであっても、規則と行為の関係に懐疑を向けているわけではない。実際のところ「未来の未決定」は、むしろ健全な常識に属するのである。
おそらくこんなところには問題はない。いま数列を考えてみる。2、 6、 10、[]と並んでいれば[]にはただちに10が思い浮かぶ。簡単な規則が見えるからである。だがこれは18でもよいし20でもよい。事実そのような数列を組み立てることはできる。この場合10を解答したときに規則だと思っていたものが、実は別の規則であることが判明する。当初規則だと思っていたものは、後になって本当は別の規則だとわかることはいくらでもある。語学の規則の修得時に格変化の規則だと思っていたものが、さらに進んで本当は規則は別のものだったとわかることはよくある。規則は後になってしばしば修正される。これは事実である。ここからさらに論理的な懐疑を行う。後になって規則が修正されるのであれば、修正された規則もさらに本当は別のものである可能性が残り続ける。とするとどこまで行っても本当は何の規則にしたがっていたかがわからない可能性が生じる。このとき現にしたがっていると思っている規則さえ、それがなんであるかがわからない。
こうして規則と行為との間には埋めようのない裂け目があることがわかる。この裂け目のことを「存在の裂け目」と呼んでおきたい。反省をつうじて対象として捉えられた裂け目だからである。つまりこの裂け目じたいは、意識にとっての対象となっている。そうすると裂け目といっても、経験の操作の派生態である可能性が強い。演算の行為においてこの演算を実行することができ、かつ正解をだすことができるにもかかわらず、そのとき何の規則にしたがっているかがわからない以上、行為することと規則との間にいわば層状になった質的な差があることを意味している。
この場面で演算規則という設定の仕方がまずく、むしろ操作的行為によって足しあわせるという事態を基礎づければ問題はなくなるという反論は予想される。だがひとつ、ふたつとオハジキを数え上げていくようにして、数え上げるという操作をつうじて足しあわせるという行為を正当化しようとしても無駄である。操作的行為によって概念を意味づける仕方を「操作主義」という。この場合数え上げるという行為そのものが、ある数以上になると別のものになってしまう可能性はいつも含まれてしまっている。そのため操作的行為によって事態を打開しようとしても、再度同じ問題に戻されてしまう。つまり数え上げる行為が本当はなにをしているかが、再度わからなくなるのである。
この問題を、次の様にして決着をつけることはできない。規則は、多くのひとのコミュニケーションがうまくいくための皆で取り決めた約束事なのだから、約束事は必要に応じて変えればよいというようにである。こうした考えを「規約主義」という。そこでの言い分は、1+1=2としたのは約束事であるので、規則は便宜上のものにすぎず、必要に応じてかえることができ、そのため規則がなんであるかは取り決め次第である。
このもっともに聞こえる言い分は、事態を取り違えている。規約主義は、演算の結果の正当性の理由づけをめぐっての立場表明である。1+1=2を何故2だと解答してよいのかという根拠について、それは約束事だと答えているのである。結論の正当性の理由を約束事に求めていることになる。一般に演算行為の基礎づけの観点から、基礎になるのは約束事だと言っていることになる。ところがクリプキの提起している問題は、演算結果の基礎づけを問うているのではない。かりに+の規則が約束事であっても、そして約束事にしたがって正解を出していても、なおそのとき何にしたがっているかがわからないという懐疑である。演算行為の基礎づけではなく、かりに基礎づけられたとしても何がなされているかがわからないという懐疑である。
この問題をクリプキ自身は、私的言語批判と結びつけようとしている。一人で規則にしたがう限り、規則にしたがっていることと、規則にしたがっているとただ思っていることとが区別がつかなくなってしまうからである。ここで持ち出されるのが規則にしたがっていると言えるための「言明可能性の条件」である。ところでクリプキ自身が指摘するように「皆と同じ答えを出していれば規則にしたがっていることになる」などと言うためには、人は哲学者になる必要はない。これでは規則にしたがうことのごくわずかな一面を、社会学的な別の言い方で語ったにすぎない。事実まぐれ当たりで答えだけあうこともあれば、何度かミスを重ねる間に答えだけあうということもある。 答えが一致するということは、規則にしたがうこととは独立であり、かりに答えが一致することを、規則にしたがっていることだと定義するなら、それは一つの定義をあたえただけになる。社会関係の複雑さを引き下げるためにそのように約束事で決めようという態度は、再度規約主義に戻っていく。規約主義は、規則と行為の関係には関連しない独立の問題である。
ここでクリプキが持ち出すのが「皆と同じ解答を出していれば、誰も規則からはずれているとは言わないだろう」という二重否定形である。直接共同体を持ち込まず、二重否定のかたちで関連づけられるというのである。規則からはずれているとは言わない、という点に二重否定が入っている。これはウットゲンシュタインの内的関係を応用したものである。たとえば人の座るための制作物を「イス」という言葉で呼ばなければならない必然性はない。イシ、イワ、イヌ、イエ、イコ、イネ、イコ等本来何でもよかったはずである。言語は本来、音のまとまりだからである。ところが他の言葉に置き換えなければならない必然性もない。イスという言葉は、それ自体には必然性はないが、他のものに置き換えなければならない必然性もない。これが内的関係である。他のものに置き換える必然性はないというところに二重否定が入っている。
これと同じようにして規則にしたがっていると言えるためには、共同体が内的関係になければならないというのが、クリプキの言い分であり、規則にしたがうことと、共同体は、必然的なつながりはないが、なくてもすむわけではないという関係になる。そしてそれによって私的言語批判が実行されていることになる。
はたしてそうか。規則にしたがっていると言えるための言明可能性条件をもとめたことの帰結が、この二重否定文であった。ところが言明可能性の条件とは、広く共有できるかたちで言え、記述できるための条件である。したがって言明可能性の条件という設定そのものに共同体が含まれてしまっている。規則にしたがっていると言いうるための条件は、言明可能性の条件の側ですでに共同体を含んでおり、規則にしたがう行為に共同体が内的に関与しているのではない。規則と行為の関係と、規則にしたがっていると言いうるための言明可能性条件は独立の問題であり、規則と行為の間の埋めようのないギャップは、共同体を導入しても何も変化を被らないのである。事実共同体に代えて、他者を導入してもよく、相互承認を導入してもよいし、場合によっては近所のイヌでもよい。規則にしたがう行為と近所のイヌが内的関係にあるという主張は、もちろん肯定されはしないが、おそらく否定もできないのである。実のところ二重否定には、確定記述の否定という確定記述の外の開集合が一度設定され、さらにそれの否定というかたちで重複的に開集合が設定される。つまり二重否定は二重の隙間を含むのだから、必要に応じて必要なものを導入することができる。そのひとつが共同体であった。
クリプキ自身は規則と行為の裂け目を、私的言語批判に結びつけようとしている。ところがこの二つは独立の問題であり、クリプキはみずから立てたテーマで別のことを実行してしまったのである。規則と行為の裂け目は、共同体や他者の導入とは独立の問題である。そしてこの裂け目がある限り、規則に従おうとする努力も、規則から逸脱しようとする努力も等価に無駄なものであることがわかる。
このとき規則と現実のオペレーションの間には隙間があり、類似したオペレーションを行っている場合でも、まったく別様な規則に対応している場合がある。そしておよそコンピュータで起きていることは、まったく別様な規則の生成と運用である、と考えたほうが良い。規則とオペレーションの間には、規則運用のネットワークがあり、たとえばあるソフトを動かすさいには、コンピュータに内蔵されたプログラムのうちで、どの範囲までのプログラムが作動しているのかはわからない。同じように規則と人間の行為を対比したとき、実際の行為を行いうるためには、範囲が決まらず、範囲の決めようのないネットワークが介在し作動しているに違いない。
つまり同じようなオペレーションを行っている場合でも、異なるプログラムにしたがってオペレーションを行っている可能性があり、プログラムそのものはまったく別様でありうるし、将来にわたって別様なものになりうるのである。このときどのようなプログラムでも、プログラムそのものの更新が起きるさいには、あるプロセスの仕組みが含まれている。要素単位のプロセスが次の進行を行ったとき、その次の要素単位を生み出すことができれば、手前の二つのプロセスが接続し、また次の要素単位を作り出すことができれば、その手前の二つの要素単位が接続するという創発的なプロセスである。
総じて、コンピュータは記憶容量がまったく異なり、記憶の保存というコストの心配はまったくない。つまり捨てる必要がない。人間の場合には、記憶の選択的排除をつうじて当面不要だと思われるものを過度に捨てすぎている。人間の場合には、わからなくても実行できる範囲が、どんどんと狭くなっているが、ところがコンピュータはわかることを重視していない。そもそもわかることから認知が成立していない。わかることは選択肢をより多く設定するための隙間を開くための機能である。反射反応を避け、反射の起きそうな場面で、それを停止させ認知を遅らせるのである。その遅れが自己固着や自己陶酔にもつながる。コンピュータは飽くことなく、しかも莫大な速度で試行錯誤を行うことができる。理解とは別の選択肢の広げ方をしているのである。
再度整理しておく。コンピュータの情報は、なにかについての情報である限り、つねに二次的にこの情報系に写し取られたデータである。そのためコンピュータの情報系とそれ以外の現実の間にはつねにギャップが残り続ける。このことは人間の言語と、言語系が写し取る現実の間でも同じことが起きる。どのように高度な情報系でも、そのシステム以外の系に開かれている。情報系の穴のようにそれ以外の現実に開かれていくのである。だが情報系に写し取る際に、モニターによる視覚情報は、人間の視覚をはるかに凌ぐほどの詳細さを持ち、しかも莫大な量の記憶ができる。そして情報系はそれ単独で作動を続け、人間の知能の現状にはなかった新たな現実を形成し始める。それがソフトの機能に出現する。人工知能の学習の仕方が、どの程度の可変性の幅があるのか、次々と新たな学習の仕方を編み出していくのか、そのことを推論するにはまだまだデータが足りていないのが実情である。