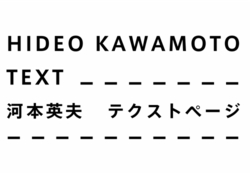自然知能とソフト・ロボット――科学哲学的考察
河本英夫
知能が人間だけに限られたものではないことは、生物界ではよく知られている。たとえば働きバチのかなりの部分は、働かない。怠け者のように見えるが、ハチの組織を維持するうえで、一定量の働かないものを作っておくことは大切な仕組みのようである。何か極端な激変が起きたとき、たとえば毒物をせっせと食べてしまうような場合、絶滅を防ぐためにも生活の仕方が異なっていたほうが良いことは、むしろ自然の知恵である。人間とは異なるシステムを形成し、それはそれで維持されている場合には、人間的に言えば、それ固有に十分な理由があり、その意味で有効な活用法があるに違いない。すでに成立している仕組みを人間のシステムに導入する場合には、サブシステムとして導入して置くことが選択肢となる。介護現場のように厳しい労働環境では、同じ一つのシステムとしてやっていくことは容易ではない。ときとして代替可能なシステムをサブシステムとして導入しておくのである。
晩年のダーウィンが、ミミズについて考察している。ミミズを畑に飼っておくと、ミミズはただ餌を求めて、ひたすら動き回る。土を食べ、微生物を濾し取って、大量の糞をする。それだけをやっているのである。だがこのことの結果は、土壌に細かな穴を開け、結果として土地を耕し、土壌に空気を含ませてくれる。このことの帰結は、結果として土壌を豊かな状態に改良してくれることである。ここでは意図と帰結はずれている。ミミズは土地を改善しようとしてはいない。またミミズを手なずけて、人間の都合のように調教しているのではない。そもそも人間の知能とミミズの知能は、まったく別のものである。ただミミズの働きは、植物の生育に有効な効果をもたらし、その延長上で人間の農作業にも、有効に機能している。これは人間の営みの延長上に、ミミズのシステムを接続しておくと、サブシステムとして有効に機能してくれるということである。ミミズが一定数密度以上になると、エサの濃度の高い方へと分散していき、土壌は満遍なく自動的に耕されるようになる。
かつて河川が汚濁し、ボウフラや蚊が大量発生するようになったという報告が、続いたことがある。洗剤が高濃度の栄養を含むようになり、河川に流された洗剤水で河川が富栄養化したというのである。このとき多くの河川では、コイの放流という対策が取られた。コイは大量発生する微生物を食べてくれる。しかも平均寿命も40年と長い。微生物の量が減れば、ボウフラや蚊の発生を抑えることができる。コイは、動物の本性にしたがって、「食べたいだけ食べるのではなく、あるだけ食べる」。いつも恒常的に餌があるわけではないので、あるだけ食べてしまう。金魚も餌をやりすぎると、食べ過ぎて死ぬことがあるらしい。コイはただ食べたいだけ食べているだけであるが、人間の環境衛生には有効に機能している。あるだけ食べるものは、食料に適合的な大きさの餌をただひたすら食べてしまい、周囲にいるコイはより小さな餌まで食べるようになる。こうして河川は透明度を増す。
こうしたシステムの働きを、「自然知能」と呼んでおきたい。自然知能は、知能を人間にだけに留めないこと、知能のモードにはさまざまなことがありうること、知能の働きは、連動するシステムにとって、組み立て方によって有効に活用しうること、等々の位置から考察することになる。人間をモデルにした知能をAIで創り出したり、人間を典型例としたロボットを創り出すこととは、異なる仕組みで議論は進む。
人間をモデルにして制作が行われれば、制作されたものは人間の能力を超え出ていく。これはむしろ必然である。特定の機能に特化すれば、その機能は人間の備えた機能を超えていき、また特定の機能を実行するためには人間に備わる生得的な機材(身体の一部)は、それほど優れてはいないことを意味する。こうした機能的能力は、人間の機能的な経験や生活に、莫大な利便と便利さをもたらす。それは驚異的なほどである。だがこうした利便性に比較したとき、人間の経験は豊かになっているのだろうか。
自然知能はたんに科学的な解明を目指すものではないことが、基本的な視点である。ミミズの生態について科学的な解明を目指すということが行われているのではない。ただ周囲の環境のサブシステムに少し変更を加えると、サブシステムの自動的な動きの継続によって、局面がかわってくれる、ということである。発想は、どちらかと言えば工学的である。人間が自然界のなかではローカルシステムでしかない以上、人間の側から制御しなくても自動的に有効に機能する多くのシステムとの連動で成立している。その連動するものにわずかの人為的変化を加えるのである。
こうした工夫は、実質的には長い伝統をもつに違いない。植物のなかで特定のものを選び出し、育て上げて薬草として活用する「本草学」では、鉱物資源の活用も行っていた。化学資源を創り出すような実験もおこなっている。それだけではなく「農業」とはほとんどの部分で、自然知能の活用の営みだったのである。
サブシステムは、それとして作動している。そのため道具のように、人間の延長上に人間が制御することによって有効に機能するマシンではない。このタイプの道具は、道具である限り、基本的には可能な限り自動制御するオートマシンまで進む。自動車も、自動運転の車までは、進んでいく。しかしこれはどのように高度化しようと、道具である。出発点と終点を別建てで決めなければ、自動車はそれじたいで動くことはない。それに対して、サブシステムはみずから作動する。こうしたサブシステムを、人為的に導入してみる。実際に行われることは、サブシステムの回路を人為的に増やすことである。そこに有効に作動する人工的な仕組みを導入できれば、サブシステムの選択肢が増える。おそらくこうした方向へと自然知能の考察は進んでいくように思われる。
自然界に持続的に維持できる仕組みがある場合には、どのようにしてそうした仕組みが成立しているのかはわからない。長年の年月を経て形成されてきたものか、あるいは偶然そうした仕組みが成立して、有効だから維持されてきたのか、由来については、いくつもの回路がありそうである。由来は後になっての理由付けだからいろいろとあってよい。そうだとすれば人工的なサブシステムのアイディアを考案し、機会に応じて導入すれば、サブシステムは有効に機能するように思われる。
最大の視点の転換は、人間的な視点から現実に対して説明をあたえることではなく、むしろサブシステムをそれとして出現させていくことである。一般的な言い方をすれば、トップダウンではなく、ボトムアップさせることであるが、そのことの内実は、事象のコードを変えていくことである。たとえば働きバチの3割は働かない場合には、人間的なコードでは、働きバチの総体を3つの組に分け、ローテーションでそれぞれの班が仕事に従事するということになる。ハチがそんなことをやっているとは考えにくい。むしろまったく別のコードを使っている可能性が高い。イメージとしては、以下のような事例に示されていることである。
家を建てる場合を想定する。13人ずつの職人からなる二組の集団をつくる。一方の集団には、見取り図、設計図、レイアウトその他の必要なものはすべて揃え、棟梁を指定して、棟梁の指示通りに作業を進める。・・・もう一方の13人の集団には見取り図も設計図もレイアウトもなく、ただ職人相互が相互の配置だけでどう行動するかが決まっている。職人たちは当初偶然特定の配置につく。配置についた途端、動きが開始される。こうしたやり方でも家はできる。
デザインの仕方は、目的合理的である必要はなく、また目標設定に対応するものでもない。この文章は、マトゥラーナの作ったものであるが、1番目の13人の集団は、人間的、あまりに人間的なコードであり、2番目の13人の集団は、まったく異なるコードで作動している。大きな違いは、1番目のコードは、プロセスの到達点からそこに到達するように組み立てられていることであり、2番目のコードは、プロセスの継続だけで組み立てられ、そこから出現したものはプロセスの副産物になることである。こうしたコードの違いを見分けるようにして、事象を出現させていくのである。
このとき対比項目はいくつかに分かれる。人間の観察するコードではなく、むしろシステムそれじたいのもつコードを対照的に取り出すこと、さらにシステムそれ自体のモードをアルゴリズムか数学で近似的に表現するのだが、現実の物性からなら物理系と、サイバー空間内の疑似システムをうまく架橋するような仕組みをそのつど考案することである。
1 自然知能のモード
人間から見て、「知能」に見えるものは、必ずしもそうなる必然性はないが、おのずとそうなっている場面が含まれている。事態に選択的な場面があり、力学的、エネルギー的にみて必然性がなく、そうならなくてもよいのにそうなっている事象が「知能」と感じられる場面である。DNAの骨格のとなっている5員環からなる核酸は、エネルギー的には最も安定な作りではないようである。それでも現在まで活用され維持されている。この核酸は、複製の場合に有効性があるらしく、自動的に複製されることによって、たとえエネルギー最小でなくても維持されていると考えておくのがよい。
シュタイナー木問題というのがある。たとえば発電所があり、周辺に複数個(4か所以上)の配電場所(たとえば家や工場等)がある場合に、電柱を建て配線する。このとき送電線の総量を最短にするためには、どこに電柱を建てればよいか、というのが典型的な問題のかたちである。電柱の数は、任意に選ぶことができる。電柱の数が多くなれば、電柱間を結ぶために電線が必要となり、できるだけ電柱は少なくしたほうが良い。電柱を1本にすれば、逆に配線の総量は多くなると予想される。この問題を数学的に解くことは容易ではない。設定条件が複雑なために、計算によっては爆発的に時間がかかる。人の一生では間に合わないほどの時間がかかる場合もある。
この問題に対して、類似系を人工的に作ってみる。界面活性剤を含んだ水に4個以上のビーズを浮かべて、ビーズを任意に配置しておく。水分が蒸発していくと、界面活性剤が筋のように残り、ビーズとビーズの間に筋状のつながりが残る。水がどんどんと乾くと、筋状の線も変化していくが、水分が乾燥した時点で線が残り、ビーズを結ぶ最短の線が出来上がると予想される。これが実際に最短になるのかどうか、線が一通りに決まるかどうかはわからないが、エネルギー最小に近い事態が出来上がる、と予想される。幾何学的な最短とエネルギー的な最小作用は、空間の性質がいくぶんか異なっている。幾何学的な最短の場合にも、電線の重さによっては、最短の配線が実際には実行できないこともある。
(斎木敏治「コロイド粒子系への自然知能の物理的実験」『人工知能』Vol.33,No.5,pp.600-607)
だが数学的問題の類似系を、ごく単純な物理系で実現させることによって問題解決の選択肢を増やすことにはなっており、またその過程をアルゴリズム記述の一つの雛形としても活用できる見込みが生じる。最適解に自動的に近づくようなシステムを作り上げて、これをサブシステムとする可能性を増やすのである。最小作用にしたがう程度では、いまだ「知能」と呼べるほどではないが、少なくても人間の採用するモデルを増やすことにはなっている。
さらには環境の変化に応じて自動的に調整を行う場合にも、「自然知能」のモードだと考えることができる。ここにはおそらくフィードバックが含まれているが、内実はよくわからない。理論的に解くことに代えて、疑似自然系を作り、それをサブシステムのモデルケースとするのである。複数の腕を選択することの有効性を確保するための仕組みがあるに違いない。複数のターゲットのなかで、より有効な選択をする仕組みを作り上げるための自動的なマシンは多くの場面で必要とされる。
まず選択的ターゲットの設定を行う。最小事例として二つのターゲットを置く。どちらが実際に有効であるかは、時系列的に変化するものとする。するとシステムが作動中に、より有効なものが変化する。そのときそれに対応して、システムの作動の調整ができるのであれば、自然知能の一つのモードとなる。フィードバックを含んだ自動調整は、知能の基本形でもある。このことのテクニカルな問題系は、「多本腕バンディット問題」と呼ばれる。
イルカの餌付けの場合には、特定の刺激に対して餌がもらえるようにしておくと、この特定の刺激に対して、自動的な反応が行われる。このとき刺激のモードや種類が変われば、一時的に大混乱が起きる。だがまた新しい刺激に対応していく。そうした場面での変化をごく単純な系で作り上げてみるのである。そのとき最初の刺激反応系のモードの形成を、安定的な自動安定系とせず、確率的に頻度の多いというように設定してみる。その状態で、より有効な選択が自動的に変化していく仕組みを考案するのである。見た目には「反省」能力に見えるが、それほど高度なものではなく、「選択的に自動調整できる仕組み」という自然知能の出現である。
要点となるのは、あらかじめ「選択的に自動調整できる仕組み」をAIで作り込んでおくのではなく、ごく単純な系でこうした仕組みそのものを出現させることである。特定機能を作っておき、機械的に実行させるのではなく、機能性そのものをごく単純の系で出現させることである。AIに特定の機能を埋め込んでそのように作動させることは、今日ではむしろたんなる「機械性」でしかない。むしろ「機能」そのものを出現させることが、知能の解明となる。
単一光子と偏光板を組み合わせて、こうした仕組みが立案されている。偏光スプリッターを設置して、そこに単一光子を当てて、偏光板が45度の傾きの場合には50%ずつ、二つの検出器で検出されるようにしておく。偏光板の傾き次第では、検出の確率は0から1まで変動する。偏光板を45度程度の傾きにしておけば、二つの検出器のどちらが選ばれるかは、確率に依存する。この状態で、どちらの検出器が選ばれるかに、報酬確率をつけて、誘導を行う。そしてこの報酬確率を時間的な進行に合わせて、重さ(0.2 か0.8)の入れ替えを行うと、0,8の選択を行う方向に自動的に進むようである。
ここには、確率的な揺らぎとプロセスの進行中の履歴、さらには履歴の寄与が含まれており、これを人間が観察すれば、自動的に良質な選択がなされているように見える。こうした場面にも、「自然知能」の出現が見いだされる。いまつるっとした大き目の球形ボールの上に、真上から水を断続的に流してみる。水滴がボールを右側に落ちる確率も左側に落ちる確率も、半々のように設計する。実際に水を落とすと、最初に左側に落ちれば、水流の左側には9割以上の水が落ち、右側には1割程度の水しか落ちないことが知られている。これは水流に履歴が残る事例である。いま重みづけを変えて、右側に落ちるようにすると、今度は右側が増えて、やがて右側が9割程度まで増えていく。これらは自己組織化に典型的な事例で、これをごく単純な装置で実行させるのである。
機能性の出現が起きると、それは一定期間維持されなければならない。機能維持には多くの「自然知能」が含まれていると予想される。たとえば生命機能として、代表的なものは、自己維持、自己修復、自己複製であるが、それぞれの機能の出現には機能の安定化が含まれている。そのとき必要とされるのが、系が環境に接続しているとき、環境に対して選択的に対応することである。その場合の現象は、環境からの刺激に対して、反応しなくなるという事態である。
少し高度な系では、免疫システムは、必要に応じて反応し、反応しなくてもよいものを自分で決めている。過度に反応しすぎれば、アレルギー反応が起きる。たとえば自分の汗に反応すれば、過剰反応であり、反応しないほうが良いものに反応しているのである。他方反応しないほうが良いものに反応ができなければ、過度の炎症が起きる。免疫システムが対応できない場合には、ワクチンを打って個別に対応する。毎年のインフルエンザ菌は、DNAの作りが異なる場合が多い。すでに作られた体内の免疫グロブリンでは、対応できないのである。そこでワクチンを打つ。免疫システムは高度に作られた反応系であり、こうした事象がずっと簡単な系で出現してきていると考えたほうが良い。
こうした事態を「選択的無視」と呼んでおく。選択的反応とは、余分なものに反応しないことから形成されると考えてみるのである。システムは履歴をもっているので、環境からの刺激に対して、対応する履歴があれば、それに対しての反応は、システムの作動にとって余分なものである。あるいは環境刺激に対してもたらされる変化は、システムにとって測定誤差にしかならない場合もある。この場合には、環境刺激に対応した作動が、すでにシステム内の仕組みに備わった作動に対応しているので、見かけ上はもはや対応しないのである。
このとき「個体」ということの実質的な意味が出現する。人間から見れば、環境と個体との間には1対1の対応関係がなくなる。単体には選択的な対応が出現するようになる。人間から見れば、まるで単体に「主体性」が出現してきたかのように見える。
アメーバ状の単体の相互作用のネットワークが、ときとして問題となる。単体アメーバが増殖しながら、相互にネットワークを形成していく。密度勾配をもちながら単体ネットワークが広がっていく。このとき相互作用の形成のなかに、「選択的連結」と「無視」のバランスがおのずと形成されているはずである。
たとえばアサクサノリは、びっしりとノリの細胞がつながっているが、栄養上、形態上、機能上の相互作用はほとんどない。ただノリの細胞が横に並んでいるだけである。横に並ぶ理由は、大水が出たとき、海が荒れたときの防衛力だけに依存しているようである。「相互作用」というときのモードは多くのものがあり、どのようなモードの相互作用が出現してくるのかを、事例ごとに分析していく必要が生じる。
粘菌性アメーバには、そもそも中枢性の情報処理系は存在しない。そのためセンサー、情報処理、運動系は完全に機能分化してはおらず、アメーバの構造は、一種の膜である細胞外質と内部の原形質から成る。その原形質が流動しており、収縮と弛緩という周期的な運動をおこなっている。アメーバの周辺に複数個の餌を置くと、エサを結ぶ最短距離を見出し、それに対応して身体を変形させる。ごく単純だが、ある意味での最適化の「自然知能」が備わっている。このアメーバの動作に光照射を行い、光方向への膨らみを阻止する場面を考えてみる。すると光照射されるリスクを回避しながら、エサを最短で求めていく最適化の能力を実行させることができる。
そうなると細胞間でのやり取りも、ごく単純な指標を活用して行っているに違いない。タマホコリカビの集合過程で行われる細胞間コミュニケーションについては、個々の細胞が、誘引シグナル分子濃度の絶対値ではなく、濃度の「変化の比」に対して応答していることが確認されている。濃度勾配を活用して、細胞間のつながりを作る作業を行っていることが判明している。
実際にアメーバの増殖により、細胞の密度が次々と変わるなかで、細胞密度がかりに小さくても、濃度勾配を捉えることができれば、ネットワークは形成されるようである。細胞はシグナル分子を細胞外に分泌し、これを受け取った他の細胞が、さらにシグナル分子を放出、あるいは分解するなどして、細胞集団の協調的な運動や、分業などを行う。コミュニケーションが円滑に行われるさいには、細胞外の液体中を自由に漂うシグナル分子が用いられるため、環境(細胞の密度等)の変化によってその濃度が大きく変わってしまう。それに対応するために独自のコミュニケーション戦略を創り出しているようである。コミュニケーションの形成は、個体密度と個体にとっての環境の変化の度合いに連動している。
そうなると集合体の密度もしくは数量によって、コミュニケーションのモードそのものが変わる場面もあるはずであり、さらにはコミュニケーションを行いながらの機能分化の仕方が変わっていく可能性が生じると予想される。細胞密度に応じて、あるいは細胞の絶対数に応じて、やがて細胞間に見られる規則が変わる可能性が生じる。
一般的に考えてみると、単細胞で独立栄養の細胞が集合体になること自体は、生存確率を高めるために、有効である場合が多い。敵に襲われたとき、集合体での一部だけが餌になり、それ以外は生存するからである。ところが集合体の各細胞が機能分化し、異なった細胞機能をもつ細胞の複合体になるというのは、生存戦略として有利だとは必ずしも言えず、どのようにしても証明はできそうにない。
単細胞生物二つが集合体を形成し、この二つが一方は増殖を担い、他方は運動を担うというような機能分化が起きるとは考えにくい。ひとたび機能分化が生じ、機能分化していく細胞を生み出す細胞が指定されれば、それが各種幹細胞となる。脳神経系のなかには4種の神経幹細胞が指摘されている。とすると最初の機能分化がどのようにして生じうるのかは、容易に解けそうにない。「集合量が大きくなれば、集合体全体の規則が変わる」、という大原則はおそらく正しいのだが、現実にどのようなかたちになるのかは実例を示しにくい課題でもある。
また機能分化の回路は、一つに決まるとも思えない。簡便にするために二細胞集合体を想定してみる。二細胞集合体は、それぞれ単細胞として生存できるとする。そのとき特定の働き(たとえば増殖)を一方の側の細胞に委譲し、他方は餌をもとめて運動するための運動性の細胞として機能特化すると考えてみる。これはリン・マーグリスの言うような「共生説」を変形した複数細胞版である。マーグリスの場合、個々の機能体(複製デバイス、モータデバイス、体形維持デバイス等々)が共生的に合体して真核細胞が出来上がるという説である。単一の細胞そのものが複合機能体だとすると、それぞれの機能性がやがて個々の細胞で機能特化していく回路は、すでに細胞そのものに備わっていた、という考えに近くなる。個々のデバイスの性質が機能特化していき、個々の細胞レベルにこの機能特化が現れるというのである。この場合には、単一の細胞だと見えていたものが、機能分割を起こし、どれかの機能を拡大させ、どれかの機能を縮退させるというような仕組みになるのかもしれない。
こうした事態をサイバー細胞で想定すると少しやっかいな事態となる。サイバー空間内の疑似システムでは、動いているプログラムの一部の機能を拡大し、他の機能を縮退させるような機能分割が起きることを意味する。つまりプログラムの自己分割を意味する。こういう仕組みがあるらしいことは理解できるのだが、どのようにしたら起きるのかは、よくわからない。プログラムは、作動すれば自動的に動き続けるのだから、プログラムの自動的な作動、プログラムの複製、プログラムの伸長は、比較的容易である。しかしプログラムそのものが自分自身を分割するような動きは起きるのだろうか。
2 ソフト・ロボット
人間の身体が、機能的に特段にすぐれたものではないことはただちにわかる。走力では、馬にもチータにもはるかに及ばない。物をもち上げる力も、ゾウにははるかに及ばない。また機能的に見て、指が5本であることに、特段の利点があるとも思えない。電車で吊革に捕まりながら本を読むときには、ページをめくるために指がもう1本あればとも思う。身体は合理的な目的性に向かって形成されてきたというわけではなく、またより多様で高度な機能性に向けて進化してきたわけでもない。身体は、進化史的な履歴を負って、たまたま現在のようなかたちになってきただけである。このことは一方では、身体は素材的にそれほど優れているわけではないことを意味する。また他方では、人間の生殖法から見て、大幅な変更が無理であることもやむおえない。個体は、ありあわせた条件下で発達を繰り返すしかない。
身体的な働きで考える場合、どうしても人間の身体に類比させて作りがちになる。たとえば手の働きであれば、手に似せて人工的な手を作ろうとする。しかしいま素材を少し変えてみる。手の機能のほとんどは、物を握る働きである。人間の手に似せて手首、指を作り、物を掴むようにプログラムを組み立ててみる。ところがこの人造手首は、相当に硬いのである。指の動きを細かくプログラム制御しようとすると関節が多すぎて、簡単には制御できない。物を掴む「働き」そのものを、別の仕組みと素材で実行させようとすると、さまざまなアイディアと仕組みが考えられる。
風船を膨らませ、なかにコーヒ豆を入れて、掃除機用の取っ手を接続すると、空気の動きによって、物を吸着する。掴むというよりも、吸い取って掴むのである。人工的な手と物の接触があり、吸着できれば、それで物を掴む働きは実行できていることになる。こうした「働き」の代行が、ソフト・ロボットの基本的な組み立てになる。
ロボットは、人間に似ている必要もなく、人間的な挙動を行う必要もない。働きは、環境内での人間的な振る舞いの代行になっていればよいのである。そのときまず素材の問題が考えられる。たとえば女性の豊胸手術では、シリコンの埋め込みが行われる。とするとシリコンを基本素材として、別の動きのモデルを活用してみるのである。タコの足には骨はなく、硬い筋肉はない。だが極めて多様で自在な動きをしている。こうしたタコ足のような組み立てで手足のイメージを作り、人間的な環境に適合するようにプログラムを組み立てて見ることはできる。
そうなると自然界は、風景が一変する。チータと馬では、走り方が異なる。どこが違うのだろう。背骨の活用法が異なる。チータでは背骨が収縮湾曲し、それが次の瞬間では伸びて、一挙に歩幅と跳躍距離が生まれる。馬の走りは、足の付け根の筋力だけを使っているように見える。すると全身の移動では、どの要素を活用するかに力点があることがわかる。ソフト・ロボットは、素材と形態に自由度をもたせ、「働き」を人間に有用なように、そして環境適応の点でより多くの選択肢を創り出すように進める手続きのことである。
現在の人間が、進化史的な偶然で出来上がっている以上、人間をモデルにして、人間を代行するかどうか、あるいは人間の知能を超えてさらに進むかどうか、場合によってはマシンが人間に取って代わるかどうかは、とても狭い発想である。人間を課題の中心に据えたとき、すでに人間中心主義がこっそりと持ち込まれており、そのときすでにして「人間」は超えられてしまっている。むしろ現在の人間にとって、人間とは単独では、過小な選択肢と過少な可能性の回路に拘泥している存在だとみておいた方がよいとも思える。
3 数学の問題
どのような事例を利用するにしろ、プログラムを組み立てるさいには、サイバー空間内の数学を活用しなければならない。個々の数学的な定式化とは別に、数学的な発見法というのはあるに違いない。一つ一つのシステムは、異なった数学的定式化をもっている。異なるシステム間には、移行や射影があるに違いないが、それらを近似的に包摂する数学的な手法があるに違いない。その一つが「圏論」と呼ばれる、カテゴリー間の射影を行う構想であり、射影集合論である。ただし集合の要素間の射影ではない。もう少し雑なやり方だが、集合間に繋がりを見出すさいの手続き的な仕組みである。
事例でこの構想のだいたいのイメージを作ってみる。可能な限り数式を使わず、かつ具体的な事例を材料とするために、数学・論理学からは少し外れるが、圏論のイメージをつくるためには、そうした歪みはやむないことである。ヒトデとイカとヒトを並べてみる。ヒトデは星状に5本の腕を広げている。放射性の動物で、回転運動を行うように体をひねりながら移動していく。イカは頭部に足が付いており、足を使って前後に移動することができる。ヒトは左右対称的に身体を交互に移動させることでさまざまな動作を行う。身体の作りに大きなギャップがあるために、これらの間には移行がないと思われる。アリストテレスもキュヴィエも同じように考えていた。イカの足は10本であるため、ヒトデの5本脚を二つずつ避け目を入れ、10本にすれば変換は可能である。先端が二つに分かれればよいからである。またヒトの場合には、左右対称のために左右部材が基本部分を占めて、左右それぞれの末端で5つに分かれる。こうしてみるとそれらの間には変換の見通しができるので、ヒトデの微分幾何形をX、イカの微分幾何形をY、ヒトの微分幾何形をZとしておく。
ヒトデは平らだが、背中と海底側にある口をつまんで、背中と口を引き延ばす。すると口が先端となり、背中の真ん中が最後尾となるような棒状の柱に垂直となるように、5本の足が出てくる。その5本の足を口の方へ折り曲げる。すると足が頭の近くに生えて、棒状になる。この場面では、ヒトデはイカとほぼ同型になっている。ヒトデの5本脚に切れ目を入れて2つずつにわけると、10本の足が揃う。ヒトの場合には、内部に骨格が通っているので(内骨格)、明確な左右対称が出現する。左右対称の部材を長くし、末端だけに5本の分岐が出現すれば、同型になる。イカの左右の耳の部分に、先端が5つに分かれる仕組みを再度導入すれば、10本の手ができる。
こうした同型性は直観と直観的イメージによるもので、それらがなければ「世界の輪郭」さえ失われてしまい、そもそも「現実性」そのものが出現してこなくなる。そして現実性と言えるものにはどこかに内的連動性があり、複数の対象の間には写像の関係があるに違いない。その写像を対象の要素間で対応づけを行うのではなく、対象の間の形の写し(射)で実行する。圏論の大枠での手続きは、そうやって組み立てられている。
(1) Oを対象の集まりだとする。
(2) 対象Xと対象Yに対して、A(X,Y)はXからYへの射(もしくは矢印)を意味し、すべてのA(X,Y)をAとする。射そのものがAの要素である場合があり、その場合にはなんらかの変換がある。
(3)対象X,Y,Zに対して、A(X,Y)とA(Y,Z)から、A(X,Z) を導くことができる。これは射の合成である。
(4)自分自身への射があり、恒等射と呼ばれる。
この4つを満たすものが、圏(カテゴリー)である。
伝統的にカテゴリーと呼ばれてきたものは、対象を配置したり、対象を比較するさいの共通の座標軸のようなもので、概念をベースにしていると思われる。カテゴリーとは不思議な事象である。カテゴリーは単独で成立することはなく、他のカテゴリーとの関係のなかでしか成立しない。たとえば真というカテゴリーは偽というカテゴリーとの対関係のなかでしか成立しない。カテゴリーのなかで他のカテゴリーとどのように繋がっているのかがわからないものや、他の複数のカテゴリーの関連してしまうものがある。たとえば「可能性」というカテゴリーは、他のどのようなカテゴリーと対関係を結ぶのだろうか。「可能性」は、「必然性」と対になることがある。この場合には、必然的なものではないが、ありうることだという意味合いである。つまり一時的で、仮構的なものだという意味である。この配置の仕方は、分類学的な配置の仕方であり、必然的なものをことさらに際立てるために設定されているカテゴリーでもある。
圏論のカテゴリーは対象をもつものに限定される。可能性や必然性は概念ではあっても、カテゴリーではない。そうしておかないと、あまりにも多くの任意性が含まれてしまう。言葉のなかで、明示的な視聴覚イメージ(ソシュールではシニフィエ)をもつものだけに限定しておくのである。明示的な視聴覚イメージをもたない語は、さしあたりモード(様相)に分類しておく。
また認識のさいの対象相互の共通の基盤(カント)という根拠へのバイアスでカテゴリーを設定するのではなく、むしろ移り行き(射もしくは矢印)というオペレーションでカテゴリーを捉える試みである。根拠への問いに代えて、むしろ発見法的な拡張が課題となる。ヒトデとイカを対比するさい、共通の前提となる「時間」や「空間」を取り出すのであれば、カントのカテゴリーとなる。しかしこのカテゴリーは、二つの個物(対象)の外から設定されている。それに対して、移り行き(写像)を手続き的方法として活用することで、カテゴリーを射影関係から規定するのである。そのことの利点は、個物(対象)の間の内的なつながりを見出すことでもある。
そこでいまヒトデとイカの共通の母体を(A) としておく。(A) からヒトデに矢印を引き、(A)からイカに矢印を引く。ヒトデ(放射性動物)とイカ(頭足類)の間にあるようななんらかの動物を想定し(B)とする。(B)の候補はいろいろあり、場合によっては架空のものであったり、絶命してしまったものもあるのかもしれない。(B)からヒトデに仮説的に矢印を引き、またイカにも仮説的に矢印を引く。そして(A)と(B)の間に、破線の矢印を引いてみる。すると(A)と(B)との間には、発見的な手続きが存在する可能性があることになる。(B)からヒトデに矢印が引け、(B)からイカにも矢印が引けるのであれば、(A)と(B)の間の破線矢印は、「存在し一意である」可能性が出てくる。
こんなふうなやり方を設定しておくと、個物(対象)をアルゴリズム化し、数的なプログラムを仮構したときにも、プログラム間の関連を調べることができ、さらに第三、第四の選択肢、すなわち可能的な(B)を見出すことにもつながりうる。これが「発見的」ということの意味である。圏論は、おそらく相当に多くのことに活用できる。
参考文献
池上高志、石黒浩『人間と機械のあいだ』(講談社、2016年)
神野圭太、澤井哲「場の変化を読みとる粘菌アメーバの巧みなコミ力」『東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 Web紀要』
圏論の歩き方委員会『圏論の歩き方』(日本評論社、2015年)
人工知能学会『人工知能』(Vol.33 ,No,5,2018年9月)
竹内外史『層・圏・トポス』(日本評論社、2015年)
マックレーン『圏論の基礎』(三好博之・岡本理訳、丸善出版、2012年)