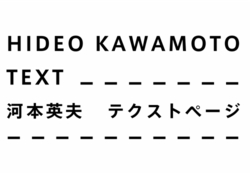哲学の困惑
――科学哲学的試論
河本英夫
目次
はじめに 3
1自然という現実性 8
2世界という現実性 32
3情報という現実性 54
はじめに
新たな現実性の出現
現実性の範囲があらかじめ確定していた時代がある。フーコが現代と区別して「古典期」と呼んだ時期で、世界地図で世界の輪郭はほぼ決まり、次々と未知の世界に出会う局面が終わった時期である。自然神学は、あらかじめ確定された「力学世界」を基調としていたので、世界はひとたび作られてしまえば、必然性が支配する。神学的な創造と創られたのちの必然的世界というかたちで、神学と力学(科学)は、役割分担しながら無理なく両立する。この仕組みのもとでは、宗教と科学は相互補完として両立している。そして古典力学には、新たな現実性を生み出す仕組みがないのだから、現実性の範囲は確定している。この段階では、現実と虚構、現実と想像性は、明確に区別できる。虚構はあくまで、現実性の向こう、あるいは現実とは区別されるエクストラである。それらは娯楽ともなり余興ともなるが、むしろそれに留まっている。 18世紀末から19世紀初頭に起きた知の再編によって、「現実性」の範囲が変わってしまう。これ以降、新たな現実は際限なく生み出される。フーコの『言葉と物』では、生物学と経済学と言語学に生じた同型の変換によって新たな知の前線が形成された。そこで起きたことの内実を網羅的に取り出すことは容易ではない。たとえば生物学という語そのものは、この時期に生まれる。しかもほぼ同時期に、複数の科学者がこの語を使い始める。それ以前には、自然界は、鉱物界、植物界、動物界に区分されており、これはアリストテレスが提起して後、2300年引き継がれてきたものだ。そのとき生物体は、器官の関係であれ、機能性の維持であれ、個体がそれとして成立する仕組みが、個体に固有化される。機能性を代表象する関係性そのものが普遍化されれば、それが種を決定するものとなる。各個体は、外から割り当てられた基準に照らして規定されるのではなく、みずからを自己規定するのである。こうなれば自己規定するシステムは、由来の上からも、向かうべき目標という点でも、あらかじめ外から決められるようなものはなにもない。 ちなみに経済学では、物(財)についての記述から、価値への探求が前面に出る。物についての網羅的で特徴をひとつずつ書き表していく段階から、価値がどのようにして成立し、しかも価値がどのようにして生み出されるのかの考察に進む。また言語学では、名詞が主要な考察の対象であったものが、むしろ動詞と活用形に力点が置かれるようになる。ここには18世紀的な博物学から19世紀以降の知の仕組みへの変化がはっきりと描かれ、知は外的な支えを失い、それじたいで生成していくものとなる。自己規定するシステムは、こうして分散的になり、新たな個体が出現する可能性はつねに開かれており、しかも自己規定するシステムはみずから変わり続けることもできるのだから、現実性の範囲は更新され続けるものとなる。こうした変貌し続ける現実性のなかで、「人間」という語が別の意味をもち始め、あらゆる場面で、この「人間」という語が、現実性の限界にも、現実性の可能性の幅にもかかわってくるようになる。「人間」とは、神がたんなる外在なり、出発点も到達点もない時代に作り出され、ある種の虚構としてセットアップされた最後の「現実性の拠点」だったのである。こうした時代の推移のなかに、大幅で多面性をもつ「仮想現実」が作り出されるようになった。その最大のものが「進化論」である。キュビエは、骨を一本見ることができれば、その動物の全体的輪郭を描くことができると豪語し、どうみても存在しそうもない生物の絵を描いてもいる。進化論の理論的な枠組みは、進化の機構と総体的な図式である「系統樹」からなる。進化の機構は、「用不用説」「自然淘汰」「遺伝子の突然変異」のような進化をもたらしうる機構にかかわっている。もう一つの系統樹は、生物の系列的な配置を行うもので、ラマルクやヘッケルが詳細に描いているが、いずれも頂点に「ホモ・サピエンス」が置かれている。「人間」は進化史の延長上で、一切の生物系統の頂点に配置されることになった。それによって「人間」は系統樹の頂点で、ひとしきり安定を得ることができた。この安定は、構造的に確保されている。たとえば生態学では、ユクスキュルに見られるように、各生物は固有の環境世界をもつことが明らかになっている。ダニにはダニの固有世界があり、ハエにはハエの固有世界がある。だからと言って、ダニやハエの固有世界がそれとして多平衡分散的な多数世界となるわけではない。そうした固有世界は、実は人間の捉えている世界から引き算をするように捉えられている。ダニやハエの固有世界も、人間の世界から引き算され、多くの現実性が欠落したかたちで配置された世界なのである。これが「人間」がどこまでも「現実性の拠点」である理由であり、そしてそれは同時に構造的な保証でもある。「人間」は「現実性の拠点」である、というおのずと成立してしまう議論の枠には、実はこっそりと「利益相反」が含まれてしまっている。その主張を採用することが、おのずと人間の利益にもなっているという利益相反である。人間が現実性の認定を行う以上、その現実性には人間性の利害が含まれるのはやむをえないという主張がただちに聞こえそうである。これが「認識論的利益相反」である。各種カント主義の末裔には、この主張がある。また人間から見た世界以外に何が捉えられるのかという主張も聞こえそうである。これは「人間的ローカリズム」という人間辺境主義の裏側で張り付いた「論理的居直り」である。人間は、現実性の一つの辺境である。この辺境は、構造的に保証されていて、それ以外の可能性が閉ざされているという論理が理由となっている。だがいずれもごくわずかのきっかけで崩れそうな危うさをかかえている。AIがまったく別様な計算を行い、人間には見えていなかった現実性を描き出す可能性は高く、そのとき現実は、人間が捉えているものとは大幅に異なっている可能性は高い。AIをはじめとする技術的な進化を通じて、この頂点に置かれた「人間」そのもののが、ひょっとして一つの「仮想現実」ではなかったのかという思いが広範に広がり始めている。それは生身で生活する人間が、AIに仕事を奪われ、AIに頂点の位置を奪われるという何度もSFで語られた内容に留まるものではない。仕事の役割分担の上で、人間がみずからの作り出したAIに仕事を委譲していくことは、技術の進化に照らしてみたとき、不自然なところはまったくない。たとえば稲の作付けで、代掻きも田植えも稲刈りも、現在ではすでに機械が行っている。やがて街中のタクシーも無人タクシーに置き換わっていくと予想される。外科的な手術のかなりの部分はロボットが行っている。こうした場面では、仕事の役割分担の配分が変わるだけのことである。多くの仕事は、AIやロボットが担うようになる。だがこの場合には、現実性の範囲は同じままで、仕事の分担がかわっているだけである。さらにAIの記憶力と映像分析力とデータ処理力を活用して、業務の細かさが変わっていくことにも、不自然さはない。仕事をより詳細な技能で実行できるのであれば、それを止める理由もない。ただしこのことの延長上で、人間には直接見えない現実が明るみに出て、人間とは異なる計算式で物事が捉えられるようになれば、人間の経験にはそれまでなかった要素が入ってくる。現実性のなかの仕事の配分の変化によって、「人間」そのものに変化が及ぶことはほとんどないと思われる。仕事を失くすかもしれないという日常生活にともなう人間側の心配は、当然ながら残る。ただしその心配の大半は、たとえば2,3年に一度すべての既得の知識を捨てて学ぶ直すことになるかもしれないという敷居の高さと、それにともなう不安に由来している。人間は生物的存在として、毎日食べ、眠り、糞をして、ともかく生きていく。だがそれに留まるのではない。むしろ人間は、自分自身のイメージをもちながら、自分を律して生きていく。人間自身がもつ自分のイメージが、「人間」である。この「人間」に対応する現実性の範囲がある。むしろ問わなければならないのは、現実性そのものの輪郭が変わり、現実性そのものの範囲が変容してしまう可能性である。そのとき「現実性の拠点」であった「人間」は、少なくとも位置価を変え、場合によってはなくても済む存在になるのかもしれないのである。一般に仮想現実と呼ばれるもののなかに、なにか現実性の範囲を変えてしまうような動向が見られる。
認識の限界
このとき哲学は、認識と相関的に捉えられる「世界」というものの安定性を失うだけではない。アリストテレスからカントまで暗黙の大前提でもあった世界の現実性が崩れてしまえば、そもそも認識とは何をすることなのかということが問われてしまう。そして最初にやり玉にあがるのが、世界と認識はそもそも相関的に成立しているのかという問いである。カントが認識論を試みたとき、明らかに認識と世界は相関的である。またその前提を置かなければ、認識の在り方を詳細に論じていくことには意味がなくなる。認識の枠組みを詳細に論じてみても、それが最初から世界とすれ違っているのであれば、いったい何を問題にしているのかが再度問われることになる。メイヤスーやガブリエルの議論の基調となるのは、「偶然性」の扱いである。そしてそれが知の形成にとってどのような場面で有効に機能していくのか、またどのようにして知そのものの形成が開始されるのかをめぐって、多くの選択肢があり、可能性がある。たとえば何かが偶然に出現するとき、その出現するものに主観性そのものが巻き込まれていくのであれば、その何かを主観性が認識する、ということに留まることはできない。このとき主観に対置されるかたちで「実在」を捉えることはできない。あるいは対象が変化し続けていて、それの行き先も予期される結果も見通せないときにも、認識は対象を捉えることはできない。ここに「新実在論」と呼ばれる広範な構想の可能性が出てくる。無限の問題を扱うさいにも、主観性は主観性に留まることはできない。無限なものは、どのような存在なのかという問いに、哲学の既存の道具立てで答えることは容易ではない。というのも無限性は、認識とは別のオペレーションで成立しているからである。認識の下で行われるオペレーションでは、「加算無限」まではイメージできる。数え上げたり、演算を継続的に行うという操作を際限なく繰り返すことで、予期された繰り返しの総体をイメージできるからである。しかし非加算無限では認識に対応させることのできる操作は、残ってはいない。あるいは環境は、そもそも認識の主体を取り巻いているのだから、それじたいは認識の対象ではない。認識がそこで起きている場所は、認識の対象になりえないのである。こうして再度認識の限界という問題が生じてきた。19世紀の終わり近くになって、デュボア=レイモンが「認識の限界」という議論を行ったことがある。議論の骨子は、認識の延長上では、「物そのもの」と「力そのもの」には到達できないというもので、そのあたりから再度新カント主義と呼ばれる一群の議論が台頭してくる。物そのものも、運動そのものも認識の限界概念なのだから、認識とは別様に扱うしかない。たとえばエネルギーから物を作り、物からエネルギーを創り出してみる。太陽表面では、重さがエネルギーに転換している。核融合が起きているのである。ところが制作をつうじて物の究極、力の究極に到達しようとしても、制作は認識から導かれたものではないので、認識には回収できない。 相関主義の最大の問題は、認識主観そのものの形成が、事実としても課題としても組み込めていないことであり、またその課題に踏み込むだけの道具立てもないということである。認識する主体そのものは、環境のなかで形成される。この形成過程は、発達心理学とは別の問題を提起している。能力の形成が、理性的大人になるという局面で終わりになり、それで完結するという見込みはほとんどない。世界の現実が変わるだけではなく、認識の主観性そのものも変化する。その場面を組み込んで議論を立てるのでなければ、古典的な認識論そのものも、すでに終わった材料の組み合わせを変えているだけになる。 こうしてかつての「実在」にかえて、変容し続ける「現実」が問われ、認識の可能性の条件であったパック化されたカテゴリー群に代えて、形成され続ける主観性が問われることになった。こうした場面で哲学は、いったい何を課題とするのかが、再度問われるのである。哲学は、課題が見つかるたびに、それを可能な限り普遍性をもったかたちで定式化する営みである。あるいはそれまで見えていなかった現実を見えるようにしていく営みの総体のことである。さらに現実を解釈することに留まらず、現実そのものを変えていくことが必要だという議論も持ち出されるのかもしれない。マルクスがフォイエルバッハのテーゼで述べたように、現実をどのように解釈するかではなく、まさに現実そのものを変えていくことが緊要だという主張も出てきそうである。だが残念ながら哲学には、現実を変えるほどの力量はなく、現実を変えること自体はやはり哲学の課題ではない。逆にそれほどの力があるのであれば、哲学は危険極まりない。事実、哲学そのものに、それほど問題解決能力があるわけではない。問題解決は、多くの場合、科学技術、医学、法律、経済に委ねられ、それらの方が圧倒的に優れた能力を示している。また能力を形成するさいにも、哲学そのものよりも、芸術の方が優れた効果をもつことが多い。哲学は、課題を明確に定式化して、指針を立て、複数の選択肢を提示する。それによって有効に手続きを進めるためのコーディネーターなのである。そしてその程度のことしかできないのが実情である。 こうして「変容し続ける現実」に対する新たな「哲学」の課題設定が必要となった。ここではそのことに踏み込んでみる。「自然という現実性」「世界という現実性」そして「情報という現実性」という三つのテーマを取り上げようと思う。ただし変容し続ける現実に対して、もはや伝統的な問いの形では、対応することはできない。たとえば「時間」というテーマや「存在」というテーマについて、「時間」とは何か、「存在」とは何か、という問いのかたちを取ることはできない。何であるかを確定するような問いの立て方が、すでにして事柄とすれ違ってしまうからである。それらを主語のようなかたちで設定することにも大きな問題がある。主語として内実が問われるようなものではないからである。時間や存在は、どのような経験であるのか、あるいはどのような経験を前景化すれば、事柄の際立った相貌が明るみに出るのか、というような問いにかかわっていかなければならないと思われる。こうして哲学は問いの立て方を変えていかなければならず、また言語的に定式化すれば、事柄が捉えられるということでもない。
1 自然という現実性
自然と人間の関係(非関係)を捉えるさいに、大まかには四種類の基本的な枠がある。しかもどのような構想であれ、「展開可能性」の大きさで考えを進めることが必要であり、根拠連関においてたとえ根拠づけられないことが明らかになったとしても、それを展開可能性へのチャンスを含むものだ、というように考察することが必要となる。すなわち哲学的欠陥は同時に新たな選択肢を含む、というように構想することである。これは哲学を手続き的プロセスへと置き換えていくことであり、哲学を基礎づけ構想ではなく、新たな構想の選択肢を提示するものだと考えていくことである。現在の現実は、情報のただなかですでに情報ネットワークのなかで経験は進行している。情報ネットワークがすでに一つの自然性となってしまっている。情報もしくは情報化という現代的な問題に取り組むさいには、この課題に対して最も展開可能性の高い枠を採用しながら考察することになる。ここで提示する四つの枠のなかで、情報の意味内実も、情報のもっている可能性も、別様なモードと機能性をもつ。そのなかで情報を扱うさいに最も適切な枠の採用と、そこでの展開可能性を考察することが、ここでの課題である。そのさいには個体をどのように捉えるのかが、各構想のなかで、決定的な重要性をもつという見通しがある。それを受けて、情報ネットワークの特質を論じる。情報はインタイーネットの出現によって新たなシステムとして登場した、システムの分化の一つの事例である。だが急速に現実感を変貌させ続けてもいる。そのことを主題的に取り上げてみようと思う。
1 自然をめぐる4つの基本形態
反省はつねに主観から発する。そして主観性はつねに世界へと向かうように世界に開かれている。この場合、主観は世界にどの程度届くのかという思いを、つねに残してしまう。それは多くの場合、世界からもたらされた働きかけ(刺激、質料性、作用等々)に対して、主観はどの程度それに対応できているのかという思いのなかで問いが立てられる。そして捉えられた対象は、どの程度世界の事実なのかという思いも付き纏う。前者が主観性の働きへの反省につながり、後者が真理基準につながる。この真理基準はどこにあるのか。主観性のなかに含まれているのか、それとも客観の側にあるのか、あるいは主観と客観の関連(関係性)のなかにあるのか。これによって議論の立て方は大幅に変わってくる。可能な限り、多くの現実的な事象を捨て去ることで、「疑いようのない事象」に到達しようと、デカルトは試みている。カントは主観性のなかの真理基準が、同時に対象の可能性でもあるという、ある種の逃げ道を使って、折れ合いをつけようとしている。つまり認識の可能性が同時に真理基準を充足するという仕組みを考案したのである。いずれの場合にも、世界は主観-客観の相関のもとで成立する。そしてこれが第一の基本類型となる。その場合、一般的には自然とは対象の総体である。 第一類型 ここではいくつもの変種や変異体がある。しかしそこでの小さな違いを取り除いて、一般的なかたちにしてみる。主体は、自然の境界、限界に位置しており、(1)主体との関係から分離された対象「それ自体」を把握することはできず、(2)主体はすでに対象との関係に置かれているのであって、そうでない主体を把握することもできない(メイヤスー『有限性の後で』)。この定式化にしたがって、とりあえずこの類型を検討してみる。つまり主体と客体の相関の関係のもとで「自然」が成立している場面で考察していくのである。これらはカント哲学に典型的な認識論の枠組みの基本的な特徴と要素的条件を取り出したものである。 ここにはいくつもの問題がある。第一にタイムラグの問題であり、人間が生息していなかった時代の記述や、典型的には5万光年先の星からやってきた光の観測の問題である。光が到達するためには、5万年を要するのだから、その間にその星はすでに消滅しているのかもしれない。この場合、主体-客体の相関関係のなかで、客体はすでにないことになるが、にもかかわらず観測は、間違いなく事実として成立している。この場合、相関関係そのものが維持されていなくとも、なお観測は行われていることになる。 この問題については、カンタン・メイヤスー自身が詳細に論じている。しかも哲学の組み替えを意図して、メイヤスーは帰結に釣り合わないほどの大論陣を張ったのである。メイヤスーの思い出というべきものを少し述べておきたい。
メイヤスーの思い出
メイヤスーによれば、最終的には数学や情報の世界を、徹底的に前景に出して、それを手掛かりに新たな現実性を出現させ、前景に出していくことになる。たとえば数学は、主体-客体の相関から生まれたものではない。にもかかわらず重要な現実性を形成する。そのことの主張のために、哲学を組み直さなければならないという論陣を張った。というのも哲学は、言葉の新たな活用法を開発し、新たに現実性を打ち立てる営みだというのが、メイヤスーの理解だからである。こんな議論には、これまで活用されてこなかった、いくつかのキータームの新たな活用法が含まれているものである。哲学とは、言葉の活用法を変えることで、新たな現実性を出現させる営みだからである。それらのタームのいくつかは否定性を含む。「偶然」「非理由」「無矛盾」というような語の新たな記述の仕方や活用法を開発することが、ここでの哲学の課題なのである。偶然は、必然の否定形だが、必然的でないものはおしなべて偶然であり、偶然のなかにもほぼ確実、蓋然的、可能的(ありうることである)、不可能ではない等々の度合いがある。そして偶然という語に決定的な重要性をもたせるのである。認識の最終的な限界においては、一切の事物の現実、出現、その変化は、偶然であり、偶然以外にはなにものもないのだから、この場合偶然は一つの必然である。こんな議論の仕方をするのである。雰囲気はどこかヘーゲルに似てくるが、ヘーゲルの場合には、現に事物がこのようであることには「理由」が残っており、そのため「形而上学」となる。メイヤスーは、一切の理由づけをもとめずなお「絶対的なもの」について語りうる議論は成立し、それがみずからの「思弁的事実学」だとしている。実質的に当面狙っているのは「数理神学」だと思われる。そのことで魂の現実性、あるいは天使の現実性を再度新たに立ち上げようとしているのかもしれない。新たな哲学を語りうるのだという自負は、全編を通して漲っている。その心意気や思いが、議論の内実と釣り合っているのかどうかは、また別問題である。そして絶対的なものは、それ以外にはありえないという意味での形容詞として活用される。それは認識の不備によってたまたま知られていないことを理由とする偶然ではなく、また未確定な事態が含まれるような偶然ではない。およそ認識の不足から生じるような偶然とは異なり、それ以外にはないという意味での偶然であり、それは絶対的な偶然であり、すなわち必然である。こうした最後の審級において持ち出されるものが、絶対的なものについての語りである。イメージ的に言えば、カオティックなカオスである。この思弁的事実学を構成するのは、どのような場面でも「偶然」が基本であり、それは反省的な審級においてもそうなのである。この偶然は、世界がこのようにあることの事実的偶然性のみを主張するのではなく、ともかくも世界があるということそのものの偶然性も主張する。 そして相関主義を批判するさいには、一切理由なく成立する現実を広範に認め、ライプニッツの理由律を放棄して、「非理由律」を設定する。これも否定形の言葉だから、必然的な理由があるわけではない、多くの可能性のなかでたまたまこのようである、あまりないが不可能というわけではない、等々の多くの度合いがある。ライプニッツが「理由律」を掲げたときには、神学的な理由がともなっていたが、科学的な探求では、現に在る現実がこのようであることの諸条件を探し出すための方法論的な探求原理となる。それがあることによって諸科学は詳細な探求へと進んでいくことができた。ところがメイヤスーの「思弁的事実学」では、一律に「非理由律」が提示される。それはどのような科学法則の解明であっても、決定的な必然性をもたず、また明らかにされた科学法則でも将来別様なものであることが明らかになる可能性があり、また事物の側でも新たな現実が出現しうるという可能性の幅を残すためのものである。しかしそれは実証科学ではほぼ自明なことに属する。非理由律という大上段な大義をかざして、メイヤスーはいったい何を手にしたのだろう。それは最終的な審級であっても、理由は必要がなく、最終的な偶然にはそれじたいの正当化も必要ではない、という論証上の言い訳に近い自己正当化のようにも思える。こんなものをもちださなくても、相関主義は多くの課題設定ができ、また新たな課題を対置することもできる。相関主義にとって、「思弁的事実学」はほとんど接点がないほど、自分たちとは無関係なことが述べられていると感じられると思われる。だがメイヤスーは、根本を一挙に変えない限り、現状は変わらない、と感じているようでもある。そうだとするとメイヤスーに議論によって、現状は有効に変わって行くのだろうか。ここに有効性の問題が生じる。だがメイヤスーの議論には、「有効性」について論じ、配置できるような場所はないと思える。 メイヤスーの議論の「非理由律」にならぶもう一つの柱は、「無矛盾律」であり、これじたいはヘーゲルの議論との違いを明確にしておくためのものであるように思われる。矛盾を考えることができるにしても、現実に矛盾が成立するとは考えられないことを基調にしている。矛盾を運動の論理として活用したり、矛盾によって何かが語られてしまう場合には、あまりにも多くのことが語られすぎてしまう。このことへの不満があるようにも見える。 全体として、メイヤスーはこの著作によって、展開可能性のある有効な踏み出しができたのだろうか。主要なターゲットにしたのは、論証である。論証は、目標を掲げながら、実は的を外しているということはよくある。そしてその可能性が高いと私は見ている。というのも新たに活用できそうなモデルは、無限集合論の部分と全体の組み換えであり、それを非全体化として提示している。自然数と整数は、普通に見れば整数の方が数が多いように思える。ところが自然数と整数は同じ濃度である。無限集合については、部分-全体関係が変容する。 哲学的に議論を行うときに、否定形を持ち込むことは好ましいことではない。否定形は基本的に補集合なのだから、そこには多くの度合いが含まれてしまう。この度合いを細かく使い分けながら、ときとしては恣意的に度合いをすり替えながら活用するというヘーゲルにも見られる傾向は、メイヤスーにもはっきりと出ている。言葉で語るのではなく、経験が前に進まなければならないようである。
メイヤスーから離れて、再度相関主義の問題に戻る。タイムラグ以外にもいくつもの問題があるからである。まず第一に、相関関係ではすまない事態がある。認識することが客体そのものに変化をもたらしてしまう場合、相関関係で主体が客体を捉えると同時に、認識のさまざまなレベルで主体の関与が客体を変化させてしまうことになる。客体が変化してしまうのであれば、認識とは別のことが起きてしまう。量子の不確定性の場合がもっとも有名で、電子を当てて認識しようとすれば、対象そのものが変化するのだから、認識から働きかけを分離することができない。マクロでみても、各種障碍者に対する心理的統計分析は、統計を取るための手続きが、そのまま対象への介入を含むのだから、純粋な認識関係は成立していない。主体-客体の相関関係の手前で働きかけるという体験的な層がある。あるいは認識が一つの行為であれば、認識がそのまま行為としての働きかけになってしまう。そしてこの行為のレベルを無視することのできないような事象が実のところ数多く存在しているのである。 第二に問題になるのは、客体がそれとして維持されている場面ではなく、客体が客体として成立してくる場面である。個物を考えてみる。物は認識によってはじめて個物に成ったのではない。物は、みずから物である。それを主体は認識しているのである。個物が個物となるという場面は、個物となった物をどのように認識するのかとは別の局面である。これは物自体を知ることはできないという問題とは異なっている。カントの場合、認識の対象は、主観性によって構成された表象である。しかしたんに表象であるなら、現実に物の認識であるのか、それともただ主観性によって思い浮かべられただけなのかの区別ができなくなってしまう。極端に言えば、認識なのか幻覚なのかの区別ができなくなってしまう。そこで感覚は物から触発を受けていなければならない。この触発をもたらす部分をどのような形であれ、残しておかなければならない。しかしたとえ物から触発を受けるにしろ、認識できるのは物についての表象である。そのため物自体には到達できないことになってしまう。ここには別の問題も含まれている。触発は、物と認識主観の因果的な関係である。カントの仕組みではこれを残さなければならない。ところが因果的な関係は、悟性のカテゴリーに含まれているのだから、悟性的な構成の場面でしか成立していないはずである。そうなると物による触発には、カテゴリーの取り違えがこっそりと含まれてしまっている。 物自体の認識が不可能であることが問題なのではなく、物がそれとして物である場面と、物についての認識が別の事柄である、ということが、実際のところ大問題であった。そして物がそれとして物であることは、どのような意味でも主体-客体の相関関係ではなかった。 物はみずから物であるという仕組みは、認識とは別のさらに大掛かりな仕組みを導入しなければなかった。その仕組みの一つが、フィヒテが『全知識学の基礎』の原則論で提起しているものである。そこでの出発点は、「自我はみずから自我である」という仕組みである。この仕組みを編み出したために、この原則論は、物自体について別様に語る典型的なモデルとなった。当初の自我の設定は、「みずから自身をセットアップする働き」である。この働きからセットアップされたものも自我である。自我とは、働きであり、みずから自身をセットアップする働きであって、セットアップされたものも自我である。そこで働きとその産物が一つの事柄であるような関係を考えなければならない。これが「事行」である。こうした場面をフィヒテが捉えだしたために、フィヒテは物自体を因果関係とは別の仕組みに移行させ、産出関係で捉えることになった。フィヒテの場合、理論哲学と実践哲学をつなぐ拠点の確保のために「自我」の導入が不可欠であり、この拠点はさらに別のものによって基礎づけられることはできない。そこから編み出されたものが、「自己基礎づけ」であるが、これによって物がそれとして物である「働き」が導入されることになった。この働きは、基礎づけの連鎖を断ち切るだけではなく、「自己組織化的な生成論」に移行する道を開くことになったのである。 物がそれとして物であるという事態には、物の自己維持も含まれており、自己維持であれば、均衡状態の維持が機構として考案できることになる。カントの『自然科学の形而上学的基礎』で示されているのは、引力と斥力が均衡し、物のかたちが維持されているという仕組みである。引力過多になれば、物は引っ張られて収縮するはずであり、斥力過多になれば物は膨張するはずである。物がかたちを維持している場合、なにかが均衡状態にあるが、その均衡は物に内在する引力と斥力の均衡である。こうした議論を「動力学」と呼ぶが、動力学はカントの場合、物が自己維持することの必要条件を取り出したものである。動力学は、衝突や運動とは異なり、物が物でありつづけるための条件を取り出しており、ある意味で「物の内面」でもある。カントによって、物の内面である動力学の設定が行われ、フィヒテは物がそれとして成立することを働きとして語る回路を見つけ出したことになる。 この延長上でシェリングは、不均衡動力学とでも呼ぶべき仕組みを考案することになった。それが自然哲学である。自然哲学は、自然を絶対的産出性だとする。産出性そのものは働きだが、このままでは特定のかたちをもたない。働きは、たとえ働いているとしても、現実的なかたちにはならない。ここで必要なのは、働きが現実化する仕組みであり、現実化によって個物が出現する仕組みである。このときシェリングは、働きが阻止を受けると考えたのである。ここが反対の働きが関与する場面で、動力学をモデルにしている局面である。ところが産出性と阻止が均衡状態に至れば、それで物の生成は止まってしまう。そこで産出性と阻止は、不均衡状態でなければならない。ここに不均衡動力学という自己組織化と類似した仕組みが登場することになった。 このときさらに課題となるのは、物の夥しいほどの多様性である。シェリングは、この物の多様性を、関与する阻止の度合いによって説明しようとする。ということは阻止が多様性の出現をになうことになるが、それがどのような仕組みなのかを解明できるほどのところまで構想が進むことはなかった。 こうしてカント的認識論は、物がそれとしてあることの内実へと展開し、自己組織化の基本的な構想の一つを作り出すところまで進んだのである。 主体-客体相関のもう一つの問題は、この相関をどこで誰が捉えているかにかかっている。相関関係が指摘できるためには、相関関係の外にいるものが指摘するよりない。それは反省を介した主観性が行っているように見える。だがそのことはこの反省が、現実に遂行されていることとは別のことを語ってしまう可能性を残すのである。主体-客体の相関というとき、主体の範囲はどのように及んでいるのか。主体の占める位置はどのようなものか。主体は客体と対置され、並置されるようななにかの個物なのか。つまり主体-客体相関の外に立つ反省的な視点は、主体をまるで客体と並置される個物のように扱っているのではないか。そしてそれは妥当なことなのか。こうした問いが次々と浮かんでしまう。反省的に捉えた相関関係のもとで、こっそりとまるで主体がそれとして主体の位置からみずから考察しているかのように、いわば位置移動をおこなっているのではないのか。およそ主体-客体の相関のもとで、自然を語ることはすでにして多くの制約と誤解を伴っている可能性が高いのである。
第二類型
次に自然の第二類型に進む。ここでの自然は、環境であり、環境世界である。ダーウィンの「自然選択」には、自然を介した選択という意味と、「おのずとなされる選択」という二つの意味が含まれている。哲学者と異なり、自然科学者が「世界」や「自然一般」などのようなすでに概念化されたタームを持ち出すことは、もはやほとんどない時代のことである。ダーウィンにとっての生命は、生きられる以上に子供は生まれるという条件と、生まれた子供は少しずつ異なっているという条件を備えたもののことである。この二条件を備えた個体群を考えると、環境内の食糧が一定限度でしかなく、生き残るものはおのずと決まってくるという仕組みになっている。自然選択とは、個体の自己組織化的な生き残りの機構のことである。このとき生き残ったものは、環境に適応していると言われる。それが適者生存だと呼ばれる。しかしこの仕組みで、個体集団の平均的形質に変化が生じるとしても、どのようにしても新たな種の誕生までは進むことができないはずである。少しずつしか変化しないものは、隔たりはあっても転換はない。生き残り続ける微小な変化から、転換を導くことは容易ではない。逆に転換が起きるほどの大変化が起きたとき、どうしてそれでも残ることができたのか。ここにははるかに大きな偶然が含まれている。遺伝子の突然変異が起きたとして、一部の遺伝子の突然変異であれば、身体体制の局所的変化であり、ほとんどの場合「奇形」の出現である。となると遺伝子の突然変化は、身体体制のいくつかの主要部分の整合的な変化を伴わなければならないが、それはもはや単なる突然変異ではない。 自然選択は、もはや生き残ることのできないものを排除する仕組みであり、生き残ることのできたものはすべて一応「適応」である。そのため自然選択から、なにか新たな仕組みが生じることはない。この場合自然とは、選択性の網目のようなものである。それでは進化における「新たなもの」はどこから生じるのか。それは同じ親から生まれた子供でも、少しずつ違いがある点に求めるよりない。だがそれは大半は、小さな変異に留まるのである。 生き残るという場面が前景に出てくると、各生物からどのように世界が見えているのかという問題が生じる。ダニにはダニの世界があり、ウニにはウニの世界があり、ハエにはハエの世界がある。それはどのようなものなのか。ダニは木の上に登り、動物から発している酪酸の臭いに反応して下を通る動物に落下し、体温で血液の在り処を見分け、自分の体がはち切れるほど血液を吸い込んで、動物から草むらに転げ落ちて、大量に卵を産んでそのまま死んでしまう。つまりごくわずかの世界を捉えていれば、ダニのライフサイクルは完結する。ユキュスキュルはそうした環境世界を描こうとした。ハエの世界は、輪郭もはっきりせず灰色と黒の世界である。しかし人間の描く世界は、どうしても視覚に制約されてしまう。臭いや音を視覚像のなかにうまく描くことができない。視覚以外に多くの認知能力を活用しているはずだが、それがどのようなものであるのか、人間の位置からはほとんど判別できない。猫は静止した視覚像は、ほとんど認知には活用していないようである。音と事物の動きには敏感である。現在のグラフィクスの技術では、音と運動で作られている世界を描くことは難しい。魚は眼の仕組みが哺乳類とは異なり、4原色である。4原色で海のなかを見ると、どのように見えるのか。人間から推測して描くことはできるが、誰もそうした世界を経験したことがない。各生物種から見えている世界とそれを捉えようとする人間の描く世界との間には、やはりどこまでも隙間がある。クジャクのメスは羽の眼の数が140以上あるオスに求愛する。それは科学的事実である。しかし140以上もの眼の数をメスが数えているはずもなく、別の指標を活用しているはずである。そこでその指標が何であるのかの研究が進む。科学的研究は、ほとんどそうした作業であり、各種生物で起きていることを、人間の世界に翻訳して描くことのできる範囲のことしか捉えることができない。ユキュスキュルの描いたハエの世界も、人間の世界から色を取り除き、さらに物事の輪郭を漠然とさせ、人間の世界の解像度を落としたようにしか描くことができない。 自然としての環境世界は、生物各種がすでにそこに適応している世界である。この適応には「認知的適応」も含まれている。余分なことを認知せず、しかも必要なことは精確に認知できるような仕組みを備えていなければならない。つまり環境とは、すでに生存適応的に限定された周囲世界のことであり、種ごとに圧倒的な多様性をもつ。そして人間から見えている環境は、ごくわずかなものであり、すでに適応的になったものしか見えていない可能性が高い。適応とは認知を標準化する装置であり、つねに無駄なものを避けて最短で行為を起動するための方向付けの装置である。そのため環境世界とは、つねに人間化された環境である。人間の行為と環境情報との接点を、行為に連動する認知から明るみに出そうとしたのが生態認知である。たとえば走り幅跳びの踏切板までの距離を測り、歩幅を調整しているさいには、何を行為の調整要因として活用しているのかが問われる。競技を外から見ている人にとっては、身体の位置と踏切板の間の距離が短縮していく。しかし行為主体である当人は、踏切板までの距離を外から眺めるように知ることはできない。当事者にとっては、みずから移動しているのであるから、その距離の変動はつねに行為の指標ともなっている。その指標は何かを問うのである。おそらく踏切板まで到達することに要する時間であり、この時間の短縮にかかわる指標を活用しているはずである。しかも歩幅を合わせる動作に変換できているところみると、この短縮する時間を空間的な距離として変換する仕組みも前提されている。この時、時間を捉える認知を、生態心理学者たちは「知覚」だと呼んだ。知覚によって捉えられるものが、「環境情報」である。そこでこの情報知覚を定式化したのである。しかし一連の動作で最も重要なことは、時間情報を動作の調整につなぐ回路であり、ここが学習であり、訓練である。障碍者がかりに情報を知覚できても、身体行為にそれを連動させることができなければ、有効な行為を行うことができない。しかし心理学の本性上知覚情報の分析を広範に行ってくれたものの、知覚と行為との連動を解明する回路までは進むことはなかった。この部分が広範な誤解を招いた部分である。ただしそこで解明されたものは、有用な定式化が多く含まれている。このタイプの議論のなかで、哲学では脇道に迷い込むような筋違いの議論も行われた。いわゆる実存的な世界内存在の議論である。世界内存在でも、世界は現存在を取り巻くものだが、存在者の認識を介して存在に触れるような仕組みで、存在について語ろうとした。この場合、存在へのさまざまな語りは可能だが、存在そのものは明るみに出ることはなく、事象としての展開可能性がない。さまざまな作品を取り上げることはあり、繰り返し存在について語るのだが、その語りが前に進んでいるのか後退しているのかは、どのようにしても判定できない。いったい存在そのものは、自己組織化を通じてみずから変化していくことがあるのだろうか。少なくても存在とは、身体行為としてかかわるものではなく、言語的な架空態である。言葉でさまざまに語りかえることができ、かつそれにたいしての解明が一切すすまないものが壁である。また一般には反復的な信仰という行為に対応するものでもない。こういう場合には、いくつかの典型的な問いがある。たとえば「存在」とは、どのような手続きに対応するのかと問うてみればよい。一切の手続きと対応せず、どのような手続きも、その手続きとは接点のない所に設定されるものは、言語的な意味と意味の理解しか経験のなかで対応するものがない。存在についての解明は、存在そのものを前提するがゆえに、存在の全貌は明るみに出ることはない。Being is A,B,C・・・.という言明で、存在について語る文は、述語に存在の一部を含むというのである。言語や文の形式で比喩として示唆されるような「存在」なるものは、やはり言語的架空態であり、言語が内包上の内容をすべて確定して成立するということはないことを逆手にとって新たな意味内実を読み込もうとするのである。経験的な意味の確定しない言葉にはこうしたことが付きまとう。「空(くう)」「魂」「善」「光」「無」のような言葉は、意味の広がりが際限なくあり、それらは言葉とそれが表している当のものとが隔たりすぎていることによる。いわばそれを悪用するかたちで経験を筋違いに拡張したところに、特異経験、神秘的経験、無底の経験その他が出現する。そして「みずからしかある」という「自然」(じねん)も、同じタイプの語なのである。 しかも存在という語は、あまりにも多義的に活用されすぎる。あるいは大雑把に活用されすぎる。個物(石、岩・・・)があるというのは、それじたいで持続的であるということが必要条件である。持続的にある場所を占めるということが、「在る」ことの必要条件となっている。そのため通り抜けできないこと、身体で接触すれば跳ね返されること等が、付帯的な特徴である。動物個体は移動を含む。しかし個体はみずから個体である場合には、みずからであることを持続的に維持している。この持続性が在ることの必要条件である。そうしてみると在ることの条件は、かなり大幅に変動し、「在ること一般」というのはどこか思い込みである。そしてそれに対しては経験の前進がない以上一つの壁となる。壁の前で繰り返し同じ経験を行う場合には、その壁は「嘆きの壁」となる。嘆きの壁の前で、嘆き続けるものは哲学的鬱である。 この「存在」の経験にとっての拡張と、存在そのものの自存化は、実は多くの文化で見られたことである。しかもさまざまなヴァリエーションがあった。たとえばイスラム文化においては、およそ以下のようなことであった。「存在」いう概念は『コーラン』の術語ではない。「存在」、「本質」、「偶性」などのような術語は、古代ギリシア哲学のテクストのアラビア語訳によってイスラム文化圏に流入してきたものである。イスラムの哲学者はそれらの概念を『コーラン』の概念と対応させた。例えば、彼らは「存在」を、知性的分析の下に、必然的なものの存在、可能的なものの存在へと分割し、必然的なものの存在はまさに「アッラー」であり、「アッラー」以外のものは可能的なものの存在である。必然的なものの存在と、可能的なものの存在の分割のもとに、「存在」という概念は「存在そのもの」と「存在者」に分割された。「存在」と「存在者」の分割に基づいて、神(アッラー)は宗教の観点から創造主であり、哲学の観点からは「絶対者」、「絶対存在」、「純粋存在」、「絶対無分節」である。「絶対存在」、「純粋存在」、「絶対無分節」の存在は自立自存のものであり、「存在者」の存在は依存的なものである。ここで「存在」は当初より自存するものである。本質は存在者のアイデンティティーである。例えば、「花」や「リンゴ」という場合、「花」や「リンゴ」のアイデンティティーとしての本質を指している。これらは種的本質である。イスラム哲学で、存在者が「存在」と「本質」へと分割されることで、いくつか問題が生じている。「花が赤い」という文を具体例として取り上げてみる。この文において「赤」は偶性として花に述語されている。この文では、既に「花」の存在は認められており、それに「赤」を述語づけたのである。しかし、「花が存在する」という存在命題においては、「存在」は「赤」のような偶性ではなく、いわば特殊な偶性である。この場合には、「花が赤い」という文のように「花」の「存在」をもとから認めているのではなく、「花が存在する」という文において「存在」が述語として「花」に存在を付与している。この特殊な偶性を初めて提示したのが、イブン・スィーナーであると言われている。この特殊な偶性は「赤」のような偶性と差異があるので、それは「述語外の偶性」と呼ばれた。これは、述語が本来は主語であるべき状態を示している。イスラム哲学者にとって、「花が赤い」と「花が存在する」のいずれの命題も、言語学の観点からは、共通の構造をもつ。「花」は主語、「赤い」や「存在」は述語である。だが哲学と存在論の観点からは、この二つの文はまったく異なる。「花が存在する」という文においては、実在体験としては、命題の主語は本来「花」ではなく、「存在」である。すなわち、「存在」に「本質」(=花)が付加されることで、本質が「存在者」として外的に確認される。このことは、哲学の観点から、「花が存在する」という文は「存在が花する」という文で表現されなければならないことになる。こうしてイスラム哲学では、「存在の優先性」と「本質の仮構性」が導かれる。こうして「存在そのもの」は自存化され、言語的にも哲学的にも一切に先立つ位置に置かれる。こうして存在という語が一般化されると、絶対者、根源的一者、絶対無分節というように、もはや「存在」という語である必要はなくなり、個々の存在者とともに存在が語られ、存在のさまざまなモードが明らかになると、「存在」という語そのものが経験を前に進めていくための妨害になっていることがわかる。一般化されれば、そうした語は固有の意義をもたず、固有化されれば語そのものがもはや理解のための誘導を行うことができなくなる。どうしてこんなことが起きるのか。たとえば活動から個体が作られると考えてみる。生きるという活動が特定の花となる。「生きることが花する」は内容上も成立する。述語が活動であり、動詞が主語を作り出すと考えるのである。このタイプの議論は、フィヒテやシェリングの議論に少し変容を掛ければ成立する。活動から主体が生まれるのである。こう考えることの利点は、自己形成のさいに自己そのものが形成される局面を描くさいに、適合的なことである。しかし「存在する」という動詞は、活動を表すような動詞ではなく、「存在」自体が、なにかの活動の結果なのである。あるいは主語と述語をつなぐ繋辞にすぎない。場合によって省略することもでき、別の語でも置き換えの利く「つなぎ目」の働きでしかない。これを動詞のように考えることから、多くの誤解が生じているように見える。
第三類型
第三類型として、個体にとっての環境という問題がある。これが自然の第三類型である。ただし個体をどう考えるかによって自然の内実が異なってくる。個体といえば、ただちに思い起こされるのが、ライプニッツのモナドである。モナドには窓がない。モナドの働きは、基本的には二つである。一つは世界の認識にかかわる「表象する能力」であり、もう一つは表象の移動を支える「欲求能力」である。モナドは閉じているのだから、実効的に世界へとつながっていく回路は存在しない。にもかかわらず世界とも他のモナドともすでに調和状態にある。ここが世界の最善性に由来する理神論的な大前提である。そしてこれは近代当初の力学的世界に整合的である。ひとたび世界が作られてしまえば、それ以降の世界の動きは、力学法則に従う。とりわけ慣性の法則に従う。世界が創造されるさいには、力学からみたとき、本当は何が起きたのか決めることができないし、何が起きたのかがわからない。そこに多くの選択肢が入り、大前提となる「調和」もその際に実現されるものである。哲学のことだから、こんな前提から進んだ場合にも、どの程度「展開可能性」があるかどうかが問われる。あるいはどこに壁が出現するのかが問われる。モナドはそれじたいで完備しているのだから、発達も成長もない。とするとこの仕組みで経験が変わっていくのはどのようにしてか、ということが大問題となる。この場合には、モナドそのものが誕生時にみずからのうちに、潜在性を内含していると考えるよりない。だがこの内含された潜在性も、必然性をもって決まっていなければならない。たとえ潜在的に能力の開発を含むものであっても、あらかじめモナドの潜在性にも見合うように整合的に設定されたものが世界である。 次にカントの場合での個体性を考えてみる。個体はみずから個体でなければならない。それを意識の制御によって実現されると考えるなら、意識はすでに個体性がなんであり、個体性の実現が何であるかを知っていなければならない。ということは意識によって個体がもたらされるのであれば、すでに意識が個体性の本質を併せ持っていることになる。これは解明すべきことを、実はあらかじめ前提してしまう論点先取に到る。 カントにとって物質の世界はニュートン力学に従うのだから、物質の世界で自動的に個体が出現する仕組みを考えることは容易ではない。物質と意識の間で独特の存在次元を占めるような存在体を考えるよりない。そしてその候補となるのが、「有機体」である。『判断力批判』の後半で、カントが有機体を定式化しようとした苦心の跡がみられる。有機体は、みずから自身を目的とする「自己目的」の仕組みとして考えられる。しかし自然内の存在体であるから、ニュートン力学との整合性は維持されていなければならない。そこで自己目的の条件を考えることになる。(1)有機体の各部分は、原因にもなり結果にもなってひとつながりの連鎖を作る。(2)有機体の各部分は、全体との関連をそれぞれもつ。ここまでは因果関係で扱うことができる。しかしこれでは腕時計にも当てはまってしまい、有機体のような仕組みにはならない。そこで(3)部分が破損した場合には、有機体はその部分を自分で治すことができる。カントがこうした規定をあたえたのは、時計が壊れたときには、それを職人が設計図をもち治すことになるが、有機体の場合には、そうした手直ししてくれる職人は必要ではなく、また職人が活用するような設計図も必要でないことを強調するためである。こうして集合体としての個体の定式化があたえられたように思える。しかし(3)を強く取ると、部分は破損しなくてもさらに自己形成できるはずであるから、有機体は自分で変わっていく仕組みも内在させていることにはならないのか。一定頻度で平均値からはずれた「奇形」が出現することは、当時からよく知られており、奇形の出現は当初に想定されていた秩序性そのものを破壊するのではないか。しかし別様に考えれば、無作為に奇形が生じるわけではなく、ほとんどの場合秩序は維持されている。こうした秩序の維持にかかわっている総体が「自然」という名前で呼ばれていてもおかしくない。しかしこの秩序性を強く取ると、種の圧倒的な多様さに到る回路を考案することが、とても難しくなる。個体は自己維持の仕組みを備えているが、その自己維持の仕組みが強くなれば、圧倒的な種の多様性もたらす回路の可能性が細り、自己維持の仕組みが弱くなければ、種のそのものの成立が危うくなる。これはある種のジレンマである。このジレンマを解消する飛び切りの概念が、「有機構成」であった。この語は18世紀末から19世紀にかけて、圧倒的な流行語となったのである。 ヘーゲルの場合、新たな個体概念、つまり論理のもっとも基本的で要のところに「個体」という語が入ることになった。しかも論理展開のあらゆる場面で導入されている。
生命は、主体・過程となったときに、本質的に自分を自分自身に媒介する活動である。主体的な生命から見れば、特殊化の最初の契機は、(1)自分を自分自身の前提とすること(同一性)であり、(2)こうして自分に直接性というあり方[個体]をあたえ、(3)直接性のなかで、自分の条件と外面的な存立に自分を対抗させること[非有機的自然に対する個体の存立]である。内にひそんだ自然の理念を、主体的な生命力へ内面化し、そしてさらに精神的な生命力へと内面化[想起]することは、[一方に]自己と[他方に]その過程のない直接性という二つのものへの根源的分割[判断]にほかならない[霊肉・身心分離の成立]。主体的な統合から前提された、直接的な統合は、有機体のたんなる形態にすぎない――これが、個体的な物体の普遍的な体系として地球という物体である。
一般的な図式では、形式的普遍が否定され、特殊であることが否定されて、それらが内面化されることで「個体的なもの」となる。そのため個体的なものは、普遍性の契機と個別性の契機をともに含んでいる。また繰り込まれ折りたたまれる度合いに応じて、さまざまな複雑性をもった「個体」が成立する。 こうした一般化された普遍性は、科学法則のような事象の外に張り出された論理性であり、規則性である。これが否定されて内面化されるのだが、内面化された事態は、科学的な量から特定の値が割り振られるようなものではない。たとえば関数の値が決まり、相対的な値が決まるというようなものではない。相対的な違いではない。相対的な違いこそ配置をあたえられた特殊である。それも組み込んで個体的なものが成立しなければならない。この関数一般とその個別的値とは異なる仕組みで語られる「個体」を、現在の科学は持ち合わせてはいない。なによりも相対的違いとは異なる「個体性」を語らなければならない。この課題に応えることのできる探求の仕方は、現在のところいまだ開発されていない。あるいは開発できるのかどうかも良くわからない。しかも、そのもののそれとしての固有性である「個体性」を語るという仕組みが、あまりにも多くの条件からなっている。一つは自己媒介性であり、どこかに自己回帰性や自己再記性が含まれていなければならない。そうでなければまとまりが出現しないことになる。しかも第二にまさにそのことによって出現したものが直接性をもたなければならない。直接性も多くの内容を含むが、なにかによって媒介的に支えられているのではないという仕組みが成立していなければならない。だがいまだ意識や魂のような原理を持ち出すことはできない。直接態の外面性が形態であり、内面性はさまざまなかたちで分岐していく事象になっていく。ヘーゲルの語りは、語によって過度に語られすぎてしまっていて、別様の語りの可能性や別様の仕組みの導入に対して、はなはだしい困難を生じさせる。これほど明確な概念的語りでありながら、どこをどう進めば経験科学的な展開可能性のある問いに転換し、どのように進めばよいのかの示唆をあたえることに不向きである。みずからの言語的記述が過度に完結しすぎるのである。過度に語りすぎるということは、言語的語りの整合性を優先していることである。こうした哲学的な語りを自分で終わらせるというヘーゲル自身の追い込みの気迫は感じられるが、そのことによって何を獲得しようとしているのかは、未決着の課題となっているように思える。言葉と世界の間には、実際には多くの隔たりがある。この隔たりを概念の側から克服することはできない。そのため言葉から進んでいった場合、多くの発見的な手掛かりを埋め込んでいかなければならない。こうした埋め込みの隙間がないように、ヘーゲルは言葉でことごとく隙間を埋めてしまったようにも見える。
第四類型 個体の次の局面が、オートポイエーシスである。オートポイエーシスを一言で言うと、個体の出現の仕組みであり、個体の創発の仕組みである。ライプニッツで言えば作りつけになったモナドに代えて、「モナド化」の仕組みを導入しているのであり、断続的にモナド化し続ける仕組みを導入していることになる。またカントで言えば、各部分は原因にもなり結果にもなるというぐあいに連動して一つの全体を作るのであるが、そのとき部分の集合がどのようにして決まるのかの仕組みがなかった。カントの場合、やはり全体がすでに作りつけになっていて、部分の集合がどこかで決まってくるはずであるが、それが不明なままになっている。ヘーゲルで言えば、個体化に含まれる概念のさまざまな出現や機能分化のモードに代えて、力学的な物の運動の側から構想すること、それによって科学的に展開可能なシステム(体系)を形成すること、さらには新たなカテゴリーとして、内外の区分がもっとも主要なカテゴリーとなることである。論理で言えば、存在の各段階が生成するとき、ヘーゲルでは手前のものが後のものに組み込まれて内化され、システムはどんどんと高度になっていく。そして内面化されたものは統合されて新たな直接性が出現してくる。オートポイエーシスではこの仕組みをもっとゆるやかにするのである。組み込みの仕組みは、否定、止揚、内化、直接性というような語群で示されるプロセスであるが、存在階層の高度化はそれほど簡単な仕組みにはならない。 各機能系は、連動している場合、一つの系に統合されていく必要もなく、ゆるやかな連動系を維持できればよく、各機能系は別の機能系に置き換えてもよく、また新たな機能系が入り込んでもよい。連動すれば、一つの複合系ができるのだから、むしろ作動の維持だけで機能系の連動を考えていくのである。そんなふうに考えていけば、部分が全体に緊密に組み込まれていくという表象を避けることができる。そこでまず部分-全体の表象を捨てることから開始する。新たに設定されるのが、マンフレード・アイゲンたちが開発したハイパーサイクルである。
ハイパーサイクル模式図
こうした図柄で考えたときには、それぞれのサイクルが維持されたまま連動して全体的なシステムを形成している。どれか一つのサイクルが外れても、全体が維持されていればサイクルそのものは維持されており、また新たな個別のサイクルが入り込んでもよい。これは連動する多並行分散系であり、一切の統合は必要がない。こうした分散系として、ヘーゲルの議論を転換することはできると思う。 もう一つの大きな柱は、オートポイエーシスでは一切の目的論と機械論を別様に組みなおしてしまうことになる点である。たとえば化学反応式では、いくつかの物質から結晶が生じる場合に、出発点に置かれた物質から到達点である結晶に向かうように描かれる。それが化学反応式である。しかし目的論で考えれば、結果に向かうように描かれているのだから、反応産物が目的として到達されることになる。逆に機械論ではその目的に到達するように出発点の要素物質が揃っていることになる。出発点から結果までを結んでいるという点で、目的論も機械論も同じ仕組みを使っている。最も分かりやすく言えば、機械論は目的に必然的に到達するように出発点の条件を決めておく議論の仕方である。 そして自己組織化やオートポイエーシスは、こうした仕組みを疑ったのである。生成プロセスをもっと詳細に分析してみる。結晶化が始まると、引き続きそのプロセスは進行する。すると結晶化プロセスとは、「あるプロセスが次のプロセスの開始条件になるように接続したプロセスの連鎖」のことである。しかしさらに重要なのは、個々のプロセスが、一方では結晶を析出させてプロセスの外に出し、それと同時に次のプロセスの開始条件となるという具合に、進行していることである。このとき個々のプロセスでは、二重に進行する事態が捉えられている。一つはプロセスの外に結晶を排出するプロセスであり、そのことが同時に次のプロセスを起動させているという事態である。これを私は、「二重作動」と呼んできた。二重作動の利点は、プロセスの外に出てしまう結晶は、プロセスの副産物ではあっても、到達点や結果や目的だとは考えないことである。 そしてこの二重作動は、結晶のような産物が同時に「現実化」という役割を果たしていることを意味する。働きもプロセスも、人間の眼には見えない。人間の眼はそうした事象を捉えることができるようにはできていないのである。物のように静止状態にならなければ、それとして現実化しないのである。二重作動の一方は、現実化という働きを兼ねており、他方ではプロセスという見えないまま進行する事態を表している。 このことはシェリングの自然哲学で、絶対的産出性に対する阻止が、現実化という役割を同時に担っていることと類比的である。阻止は、一方では働きを現実化させて、現実のものを作り出し、働きそのものは継続して作動している仕組みにも、こうした二重作動が非明示的に組み込まれている。 シェリングの自然哲学の産出性を、プロセスならびにプロセスの継続に置き換えてみると、シェリングの構想がアナログ的で、プロセスに置き換えた場合がデジタル的であることがわかる。つまり自然の産出性、創発性を組み込んだ構想は、プロセスと産物という仕組みを用いてオーダーを更新する詳細さで新たに展開可能であることがわかる。しかも産物側の構成を、システムの構造として展開可能であることもわかる。 オートポイエーシスでのシステム構想の要の位置にくるのが、内外の区分である。これこそこのシステム論が、最も緊要なところで導入した仕組みなのである。内外を区分する境界そのものは、内でもなければ外でもない。このことはヘーゲル『論理学』でもはっきりとでてくる。しかし何が境界を引くのか。境界を引くものが内であれば、最初から内となるべきものが決まっている。とすると逆に内と外の出現が境界によってもたらされなければならない。だがそれは何によって決まるのか。それこそシステムの作動であり、作動の継続である。作動が継続することによって、まさにおのずと内外の境界が決まる。この作動は意識以前のものであることは当然であり、ある種のシステムの行為である。このことは断続的に個体が出現することを意味する。 哲学の伝統的なカテゴリーのなかで、真/偽、善/悪、美/醜のような二項対のバイナリーコードは、一般に相対的なものである。相対的配置を相当に変動させることもできれば、場合によって逆転させることもできる。醜さのなかの美というのは言葉だけではなく現実感覚としても成立する。善悪の入れ替わりは状況次第で起こりうる。一人の人間を救うことが他の一人の人間を見捨てることだというは良く起きることである。ところが内外の実質的な逆転は、何が起きるのかよく分からないのである。人間の内外を入れ替えることがどういうことなのかが実際に何を意味するのかよく分からないのである。口から手を入れて、小腸の末端辺りを掴み、内臓を無理やり外に引っ張り出すことなのだろうか。内外の区分は、また新たな課題として設定されたように思える。システムが内外の区分を行ったとき、これによってシステムの固有の空間(位相空間)が、内外をつらぬくかたちで設定される。つまり個体に応じて、個体に応じてそれぞれ固有空間が決まる。たとえばオタマジャクシの生きる固有空間と、カエルの生きる固有空間とは異なってくる。異なる固有空間を形成しながら生き延びることが、「メタモルフォーゼ」である。その場合、個体は変貌しながら、異なる環境と連動していくことになる。
これがオートポイエーシスの模式図である。システムの本体は、プロセスのネットワークであり、そこからまるで結晶のように「構成素」が出現してくる。この構成素の集合によって作り出される空間が位相空間であり、ルーマンは固有のシステムの実現の仕組みを考案し、それぞれが交叉しながら分岐するシステムを考えたのである。支払いを構成素として継続的に作動するシステムが経済システムであり、コミュニケーションを構成素として継続的に作動するシステムが、社会システムである。そしてルーマンは、基本的には図の下側を問題にして論じることになった。つまりルーマンの場合、オタマジャクシがカエルに変わっていくようなメタモルフォーゼの事例は、ほとんど視野の外にあった。こうした図式の元で、情報システムが出現してくるが、通常のコミュニケーションの範囲を遥かに超えて、作動を開始した新たなシステムなのである。またプロセスのネットワークには、作動状態に応じて多くのモードがあり、そのモードのなかで比較的持続性が高いものが、「種」である。このモードは一般に「有機構成」(オーガニゼーション)と呼ばれる。 個体が連動している個体の外が、一般に環境と言われるものである。この連動は、一般にシステム用語で、「カップリング」と呼ばれている。ただし個体にとってのカップリングの相手は、必ずしも個体である必要はない。個体の動きと連動する範囲はとても広範で、光や空気のようなものから、情報ネットワークのようなものまだ含まれる。つまり個体の連動の仕方には、多くのモードがあることになる。こうして世界内存在という定式化の仕方が、すでに荒っぽい要約にもなっていないことがわかり、またシステムの環境の設定では、システムそのものの変貌、変質(たとえば脳損傷、生まれながらの障害その他)に{応じて、固有の環境条件の整備が必要となることがわかる。 個体は発達し、変容し、それでも生きて行く。すなわち作動を継続する。そこでの個体形成のプロセスを見込んで連動する環境の設定を考えなければならない。こうして連動可能な潜在性の全範囲が、「自然」だとする新たな定式化が生まれることになる。この自然は、個体の連動可能性から規定されている。ここにシステムの発達という固有の課題領域が生じていることがわかる。 オートポイエーシスでの個体の定式化によって、実はさらに大きな問題が生じている。システムの本体はプロセスである。するとプロセスの継起的反復によって、経験はプロセスのさなかに巻き込まれていくという事態が起きる。しかしそのことを図示すれば、模式図のようなかたちで書き表す以外にはない。ここで起きることがシステムそのものと観察者の乖離である。物事を理解しそれを解釈して表現しようとすれば、観察者として語るよりない。だがそれはシステムそのもので起きることとおよそ接点がなくなるほど隔たってしまう。生成プロセスのさなかにあることは、意識から見てどのようにも当人にとって分からない部分を含む。何が起きているのかわからないのである。ところがそれを分かる形にしようとすれば、「分かったかたちの理解」を行うしかない。ゲーテの言うように「学んでも何も分からない、行為することが必要なのである」。そのときシステムの本性上、理解をしなければならないが、理解そのものを括弧入れしなければならないのである。そのことを「システム的還元」と呼んでおこう。 プロセスのさなかにあれば、知覚は刻々と変わり続ける。最も単純な事例では、部屋のドアに近づいていく時、ドアの知覚は、接近するたびに変化していく。そのときドアの知覚は、それじたい後の行為を制御するための「予期」となっているか、少なくとも「予期内在的」である。また行為のさなかでは、行為そのものを制御するために内感的な「気づき」が働いているはずである。この気づきに応じて、知覚はおのずと無視するものと顕在化するものの区別が、おのずと働いてしまっている。自動車に乗って運転しているとき、路上の小さな小石は、おのずと無視しているはずである。この無視の境界は、行為の速度によって変わっていく。こうしてプロセスのさなかにある事態と外からの観察では異なる事態が生じてしまうことがわかる。
ところですべての生成が個体化まで進むとも限らず、個体を組み替えることに到るとも限らない。それでもなんらかの生成が起きる場合には、やはり自己組織化で扱うよりない。これが第四類型となる。自己組織化は、個体化に到ることもなくどこかで停止するプロセスや、個体化したシステムのなかでも個体そのものを組み替えることなく進行するプロセスを扱うさいには、必須のものである。たとえばゲーテが「眼は光によって、光へと形成される」というとき、当初の見ることそのものの獲得にも光は関与しており、その場面では機能そのものの獲得がある。そのとき構造部材としての眼の形成に関与している場面では、眼のそのものが形成されるので、オートポイエーティックである。しかしゲーテがイタリアに旅行し、光に溢れた光景を見ることで、見ることの感度が変化したという程度のことであれば、むしろ自己組織化で扱ったほうが適合的である。 眼の形成を含んだ時、光(もしくは闇)から色彩法則が出現してくることになる。この場合光とは、可視的な明るさのことであり、可視的な明るさに可視的な闇が関与して、色彩が形成されてくる。そんなふうに双極対をなす原理(光と闇)を設定して、色彩論を形成するのである。出現した色彩は、ひとつながりとなり、色彩環となる。しかし黄色と緑の間には夥しいほどの「黄緑」があり、それらは色覚の形成にかかわっている。おそらく光を粒子だとしたのでは、光の内実の3割程度しか届いておらず、光の科学的な規定は、光のごく一部しか捉えることができない。また光を波動だとしても同じである。フィヒテは後期知識学で光の記述に取り組み、6割程度に到達している。ゲーテが色彩論で、8割程度に光の本体に触れることができている。そのとき光の総体的な本体は何かという問題が生じるが、光をつうじて生きている以上、認識からは当然ながら到達できることに限界が生じる。認識がそこで限界に当たり、にもかかわらず生きていることに不可分に必要条件となっているものこそ、ここでの「自然」である。 進化論的な形態変化で、「過形成」という事態がある。たとえば大鹿のツノのようなもので、あの程度まで大きくなってしまえば、生存適合的だとは言えなくなる。これも形成ドライヴがかかったと言われるような事態であり、自己組織化の一例である。全体の体制は維持されており、局所だけが大幅に変化する。藪や山林を移動するさいには、このツノは妨害にもなる。にもかかわらず生きていくうえで、なにかの役に立っているに違いない。そこで奇妙な仮説が生み出されることになった。あれほどわずらわしいほどのツノを抱え込んでもなお生きているところをみると、生命力のあるオスであろうとメスから判断されて、生き残るというのである。この場合には、ハンディキャップを抱えても生き残ることを可能にする環境が、「自然」ということになる。 意識そのものも多くの場面でこうした変化に直面してきたと考えてよい。意識とは一つの働きであり、それが出現して以降、多くの機能性の変遷があったと考えることができる。鳥の羽は当初体温調整のために活用されていたが、どこかで強く羽ばたくと身体が浮くことに気付き、むしろその機能へと全面的に移行してきたと考えることができる。同じ器官が機能変化していくことは珍しいことではないのであろう。とすると意識も別様の機能で出現し、現在のように「認知」や「認識」で主として活用されるようになったというのが実情に近いのであろう。意識は当初、体温維持や活動の維持のような活動の恒常性を補助的にささえるために出現してきたと考えるのが第一のポイントである。冬山で遭難して、眠ってしまうとそのまま低体温で死亡してしまうことが多く、冬山では眠ってはいけないと言われる。眠らない限り、体温の低下に対しては、多くの対応策があり、意識とはそうした補助的な選択肢を広げておくための機能的な装置であったと思える。このことは感覚反応のさいに、注意の分散を行うための隙間を開くための装置だと考えることもできる。そしてその後意識が、反射反応に対してそれを遅らせる遅延装置へと変容してきている。どこかの機能が前景に出ると、それによって他の機能領域が相対的に縮小されて、意識のそのものの感触が変貌してしまうのである。その後意識には、物の制作をつうじて、尖った槍やまっすぐな棒、薄い切片のような現実には実現されていないが、制作行為の予期として働く、ある種の理念性の確保とそこに向けた行為の誘導という機能が付加される。このとき意識は、見かけ上人間の行為そのものを統合的に誘導する装置として、さらには現実の自然界にはない理念性という超越へと向かう機能が出現してくる。時期的には、ホモ・サピエンスが登場して後、約7万年後であり、その時期に石器、棒にある種の極限性が含まれるような制作物が出現してくる。その後5万年程度経過して、言語を獲得するが、言語の獲得による意識の変貌は大きすぎて、何が起きたのかを突き止めることは容易ではない。少なくとも記憶の機能は格段に向上し、コミュニケーションの細かさは別次元になってしまうが、それによってそれまで持ち合わせていた多くの心的な働きは後景化して別様に変容したのであろう。その後ユダヤ思想に見られるような経験の極限の一歩先を感触として掴む機能が付加される。いわゆる絶対超越に触れていくという感触である。ごく最近に起きた変化は、意識の自己言及性すなわち意識の意識である「自己意識」という機能性の獲得が生じ、意識じたいの強固なまとまりを獲得するようになる。 自己組織化の場合には、組織化の個々の局面に応じて、「自然」ということの内実が決まってくる。それは何が組織化されるかによって、それに相関する事態が変わってくることによっているのである。
2 プロセスとしての情報
情報は、インターネットの登場以来、まったく新たな局面に来た。言語の機能は、ソシュールによれば、伝達、喚起、表出、述定であり、自然言語以外の記号まで拡張した場合でも、これらの機能は維持されている。トイレに紳士像、婦人像の図柄があり、男女の区別を行っているが、これも使用者に場所を特定する伝達である。しかし情報ネットワークは、局面をまったく変えてしまった。情報は次の情報に接続できれば、ネットワークとして成立する。このネットワークの外が環境であるが、環境の変容は、現時点でもうまく見通せないものが多い。まず流れてくる情報は、ほとんど誰から流されたものか、不明なものが圧倒的に多い。発信者が不明なのである。それどころか発信者が一人なのか、そもそも発信者がいるのかどうかさえ危うい場面がある。実際に起きた事件であるが、コンピュータにあるウイルスを送っておくと、ウイルスに感染したパソコンは、定期的に「したらば」掲示板を読み取る。この掲示板に書き込まれたことを、このパソコンは発信してしまうのである。この掲示板に、大阪の小学校を爆破するという書き込みがあれば、それをみたパソコンが自動的に送信してしまう。発信元のコンピュータのアドレスは残っている。そのため威力業務妨害ということで、警察が動き、このアドレスの所有者を逮捕することになった。ところがこの所有者は、そうした事態についてはまったく身に覚えがない。明らかにインターネットの仕組みに精通していない警察の誤認逮捕である。しかもこのアドレスの所有者は、どこで誰からウイルスを受け取ったのかを特定することができない、ウエッブ上を流れていたウイルスをたまたま引き込んだのである。インフルエンザウイルスがそもそも誰からのウイルスなのかを特定できないのと同様に、もともとの保有者を特定できないのである。 こうしてみるとインターネットでは、「主体」の概念がおよそ別様になってしまう。情報は主体から発せられるものではなく、なんらかの偶然で発信されてしまう。そのため主体―情報―受け手という図式が多くの場合、成り立たなくなってしまう。情報の末端には、人間がいるということさえ成り立たなくなってしまうのである。 またインターネット上に公開された情報は、そもそも特定の人に向けられたものではない。任意の人に向けられた情報は、誰が受け取るかが分からない情報である。不特定の発信者から不特定の受信者へと向けて、情報は流れ、それを受け取った人は、また不特定の受信者へと向けて発信する。こうして情報の発信が断続的に継続すれば、固有の位相空間が形成される。それを情報空間と呼んでおきたい。これは言語的コミュニケーションとはまったく異質なネットワークの形成であり、新たなシステムの出現である。このあたりの仕組みは、オートポイエーシスが最も適合的であり、情報ネットワークは個体化して固有の位相領域となったのである。 インターネットは、パソコンの内部に入り込んでおり、秘匿すべき情報がなんらかの理由で流出したり、あるいは秘匿されているバリアー超えて情報を読み出そうとする。このなかには公文書と呼ばれるものも含まれるので、情報管理は圧倒的に難しくなる。情報にはある意味で秘匿領域がない。隠すことのできる部分があるから「内面」が生じる。ところが原則情報ネットワークには「内面」がないのである。というのも秘匿され現実に二度と呼び出せないものは、もはや情報ではなく、原則呼び出し可能なものでなければならない。コンピュータで一時保存してあり、機能的に秘匿されているものは、機能的にこじ開けることができる。これはコンピュータの記憶が、登録-呼び出しという機能で成立していることに関連している。そこには選択的に忘れるという仕組みも、忘れたものを再度想起することで情報が経験に組み込まれるという仕組みも存在しない。 また現実感の変容という問題がある。ヴァーチャルリアリティと呼ばれるもので、視覚映像で現実感が形成されてしまうと、たとえば御嶽山頂上付近で大爆発が起きたときに、ただちに逃げ出し、鼻と口を塞ぎ、イオウ酸性の大気物質を吸わないようにしなければならないようにしなければならないにもかかわらず、噴火の現場近くにいて、その噴火の映像を何枚も写し取った例がある。現実の噴火は、映像の噴火とはまったく別のものだが、まるで映像を見るように撮影し続けて、逃げ遅れた人たちがでた。御嶽山の頂上付近にいたのは、ほとんどがアウトドア派であり、登山をする人たちである。それでも映像は現実感を変容させてしまい、対応の選択を誤らせるということが起きる。 このことの延長上に、たとえば鳥取中部で横断層ずれの地震が起きると、翌日にはインドでも大地震が起きたというデマ情報が平気で流れる。情報は、それに反応し応答する人が出れば、いずれも情報である。まさにそれによって情報は成立しており、事実性や真偽は、そのあとの末端の問題に追いやられてしまう。こうした現実感のなかでは、極端な情報が氾濫する。つまり刺激的で、面白ければなんでも情報たりえ、莫大な量で飛び交う情報のなかでは、さらに刺激的なものを求めて情報のネットワークでの発信が続く。 さらに別様の経験の仕組みも広範に導入される。コンピュータソフトには、俳句を詠むソフトもあるらしい。必要なデータをあたえておくと、結果として、俳句らしきものがコンピュータから出てくる。それを人間は、面白いとか斬新だとか言ったりする。コンピュータはあたえられたデータに基づいて、語を組み合わせ、語の並びを提示しただけである。それがタマタマ人間にとって、面白かったのである。コンピュータは、倦むことなく語の組み合わせを作ることができ、どこかで偶然停止することはできる。異なった経験の仕組みから作り出されたものを、「俳句」として、あるいは「俳句の拡張」として受け取ることができ、そこから斬新な「経験」を学ぶこともできる。 ところが異なった経験の仕方で、なお結論が人間の経験を超えるものが、多くの領域で出現するようになった。たとえば将棋のソフトであり、人間のプロの高段者と将棋ソフトが対戦して、現時点では将棋ソフトの方が、勝率が高いのである。将棋のようなゲームでプロが成立するのは、必勝解がないこと、向上があること、あらたな選択(新手)が生まれること等の条件がある。ソフトはあたえられたデータから最善手を探し出す。これが人間の思い付く範囲を超えていることがしばしばあるようである。コンピュータにはおそらく定石や常識はない。いつも一から計算して、最善手を探し出すのである。そこである事件が起きた。あるプロの高段者の差す手が、確率的偶然を超えて、ある将棋ソフトの示す手と一致しているというのである。しかもこのプロは、終盤には頻繁に席を立ちトイレに行くというのである。そしてトイレでソフトを見ているのではないかという疑いが持ちあがり、ついに日本将棋連盟は調査を行い、このプロ棋士を一定期間出場停止の処分にしてしまった。情報であるから、ソフトを参考にしたと言っても、自分の考えた差し手をソフトでも確認したという程度から、ソフトで正解手を検索した等々まで、さまざまな度合いがあり、この度合いを判別して、どこまでが可能でどこから先が不正だという判断による線引きを行うことは容易ではない。ソフトは人間の思考回路とは異なるプロセスで最善手を探すのだから、それはそれで学ぶことが多いはずである。コンピュータは、データの組み合わせでその場の最善解探し出すことができる。それはおそらく勝負とか、勝ちとかということとはかかわりなく、人間にとっての勝ちになる手を見つけ出しているのである。勝つということが何であるかを知らず、勝ちになる手順を見つけていく。それはおそらくこれまでになかった思考回路である。 医療技術でもガンの治療法で、多くのデータを入力しておくと、難しい症例に対して、コンピュータが治療法を選び出し、提言するようである。難しい病気のために途方に暮れていた医師が、コンピュータの選択した治療法にしたがって治療を行ったところ、成功したという報告もある。つまり思考回路が人間とはまったく異なるために、その場その場で最も有効な選択肢さえ提示できるようである。人間は、素直にコンピュータから学べばよいのだが、一回限りの重要な対戦や勝負、一回限りの重要な手術では、およそそうした学習には限度があることも事実である。人間はコンピュータから学ぶ場数が足りていないことは事実であり、異質な経験をいまだ活用できていないというのが実情であろう。集合知というのがある。不特定多数が参加して、発信者は匿名であり、応答も匿名で行われる。そのため人気投票に類似して、多くの意見がだいたい妥当なところに落ち着くことがある。当初から集合の範囲は決まっていないので、意表を突くような意見が出た場合、あらたに集合そのものが変容してしまうことがある。極端な意見は打ち消し合って、集合の中央値とでも呼ぶべき値がまとまりをもつようになる。だから集合知は、参照すべき平均的見解を示唆してくれる。 情報ネットワークが世界レベルで広がると、情報の元で新たな現実性を形成する試みが行われる。情報のもとで新たな貨幣を定義することも可能になっている。それがビットコインである。これは原則的に一切の決済に活用でき、瞬時に決済が目に見えるので、世界中で汎用性がある。情報ネットワークは世界大に広がっているのだから、この通貨は、各国通貨の壁を楽々と乗り越えることができる。しかも通貨の発行中央銀行は存在しない。ビットコインは、それが通用する(流通可能である)ことによってだけで支えられた通貨である。経済的価値と交換可能性のあるものを「通貨」だと呼ぶのであれば、デパートの商品券も図書券も、ある種の「通貨」である。取得からタイムラグを経ても交換に活用できるものは、定義上通貨となる。これに対して、クレジットカードのように支払って後の一定期間が経てば、金利が発生するものが「金融」である。支払いまでの猶予期間を、費用換算できる仕組みが金融である。21世紀に典型的な事態だが、通貨の貯蓄が通貨の必要量(需要量)を超えると、マイナス金利となる。この傾向は、スイスやスエーデンのような金融の先進国で起き、現時点での波及効果はいまだ見通しがつかない。ビットコインも世界共通通貨がないことに抗するかたちで、世界レベルに広がった情報ネットワークを活用するなかでうまれた紛れもない「通貨」である。これによって国際決済に新たな現実性が出現したのである。こうした変化がどの程度新たな現実を作り続けるのかは、おそらく誰にとっても見通しがつかないのである。
参考文献
河本英夫『オートポイエーシス—第三世代システム』(青土社、1995/6) 河本英夫『精神医学』(青土社、1998/12、共著)河本英夫『感覚――世界の境界線』(白青社、1999・11、共編著)河本英夫『オートポイエーシス2001』(新曜社、2000/1)河本英夫『オートポイエーシスの拡張』(青土社、2000/3) 河本英夫『システムの思想』(東京書籍、2002/7、対談集)河本英夫『メタモルフォーゼ—オートポイエーシスの核心』(青土社、2002/9) 河本英夫『他者の現象学III』(北斗出版、2004/1、共編著)河本英夫『遍在の場・奈義の龍安寺・遍在する身体』(奈義町現代美術館、2005/3)河本英夫『システム現象学—オートポイエーシスの第四領域』(新曜社、2006/6)河本英夫『哲学、脳を揺さぶる—オートポイエーシスの練習問題』(日経BP社、2007/2)河本英夫『飽きる力』(NHK出版、2010/10)河本英夫『臨床するオートポイエーシス』(青土社、2010/10)河本英夫『損傷したシステムはいかに創発・再生するか』(新曜社、2014/3)河本英夫『<わたし>の哲学』(角川書店、2014/5)河本英夫「想像界とネット界」(西垣通編『ユーザーがつくる知のかたち』(角川学芸出版、2015年)125-160河本英夫「庄子的行為論与自造」(『哲学的時代課題』2000,12 中国語論文)243-252Hideo Kawamoto “The Mystery of Nagi’s Ryoanji : Arakawa and Gins and Autopoiesis,” In :Interfaces Universitē Paris 7 –Denis Diderot, 21/22, 2004, 5, 85-102.Hideo KAWAMOTO, Noue Formlierung der Autopoiese, In : Leben als Phaenomen, Koenigshausen & Neumann, 2006,5, 190-198.河本英夫「複雑系統与環境」(『第二届中日哲学論伝』中国語論文 2009,4)209‐212Hideo KAWAMOTO, *“Bildung der Sinne Von der Poiesis zur Autopoiesis,” in ; Y.Nitta/ T.Tani (Hg.) Aufname und Antwort, Koenighauzen & Neumann, 2011,S.159-171.Hideo Kawamoto, The conceptions of environment and ‘eco-philoophy’”, in :A. Sumi, N. Mimura and T.Masui, Climate Change and Global Sustainability ; A Holistic Approach. United Nations UP, 2011,pp.241-257.Hideo KAWAMOTO,* “L’AUTOPOIESE ET L’INDIVIDU EN TRAIN DE SE FAIRE”, Y. Brés, D. Merllié, REVUE PHILOSOPHIQUE, 2011,9, p. 347-363.Hideo Kawamoto, “Chaos, Aoutopoiesis and/or Leonardo da Vinci/Arakawa”, in: J.Keane & T. Glazebrock, Arakawa and Gins, a special issue of Inflexions, Inflexions Journal, No.6, 2013,2,103-111河本英夫『第三代系統論――自生系統論』(郭連友訳、中央編集出版社、北京、2016年11月)上智大学中世思想研究所『中世思想原典集成 11 イスラーム哲学』(平凡社、2000年)西垣通『ビッグデータと人工知能』(中公新書、2016)メイヤスー『有限性の後で』(千葉雅也、大橋完太郎、星野太訳、人文書院、2016)
(2016年12月)
2 世界という現実性
哲学は、何を語ろうとしているのか。哲学が開始され、アリストテレスが基本的なモデルを作り上げ、その後2500年も続いて、なお終わろうとしない。この学問はいったい何を目指し、何を行っているのか。しかも当面、哲学探究は終わる気配さえない。 哲学の主要な場面は、あくまでも人間が作り上げた「言語」である。そして経験が哲学の現場である。ところが哲学の言語には、通常の社会生活ではほとんど使用されないようなものが含まれている。しかも意味不明な活用法も繰り出される。そのため哲学は、何を言っているのか不明だと言う敬遠に近い感想をもたれる。敬遠されることはそれじたいは一般には問題ではない。むしろ問題なのは、哲学が前に進んでいるのかどうかが、どのようにしても回答が得られそうにない点にある。当初言語という特質から、哲学が何を行っているのか、一度整理してみることから開始したいと思う。 人間の言語以外に、現在では多くの材料が活用できるようになっている。また哲学が活用できる素材や題材も時代に応じてどんどん変わっていく。人間の言語の範囲で考えてきた伝統的な哲学が、いったい人間の経験のどの程度の範囲を覆うことができるのか。あるいは人間の経験の可能性をどの程度拡張してきたのか。哲学である限り、人間の経験の可能性を拡張し続け、人間の経験の弾力を高めていかなければならないはずである。その課題に資するためには、つねに試行錯誤が必要となる。この論考は、その試行錯誤の試みの一つである。 いくつかの理由から、この先の哲学というプログラムの大枠を形成しなければならない。それはある種資金の出し手の希望に応えるように作っておかなければならないのである。
1 哲学という試み
哲学の道具立て 言語学者のソシュールの説では、言葉は二つの要素からなる。海という語は、ウミという音と、この音ともに喚起されるイメージであり、多くの場合青々と広がった情景が浮かべられる。音のまとまりがシニフィアンと呼ばれ、喚起されるイメージがシニフィエと呼ばれる。日本語にすると「意味するもの」と「意味されるもの」という訳語があたえられ、そうした区分だと思われがちだが、そのような意味合いはまったくない。音とイメージという異なる質がつながってひとつになっているものが、語である。喚起されるイメージは、通常は視覚イメージであれ、聴覚イメージであれ、具体的なイメージである。 音のまとまりと喚起されるイメージの間には一対一対応はない。実際青々と広がったイメージを、日本語ではたまたまumiと呼んでいるが、他の言語ではまったく異なった音のまとまりが対応付けられている。こうした事態が「対応恣意性」と呼ばれるソシュール言語学の基本規則の一つである。歩行という語は、音のまとまりと動作イメージがつながっている。 こうした言語の規則性を前にしたとき、哲学が頻繁に活用する語には、奇妙な特徴があることがわかる。大別して、そこには二種類の奇妙な語群がある。 第一に、世界(宇宙ではない)、存在、物自体、神、無のように本性上、具体性をもたず、具体性を持ちようもない語群である。ほとんどが有限の事象ではないために、具体化すればごく一部を切り取っているか、なんらかの比喩に留まるような語である。こうした語はそれじたいは具体的なイメージとはならず、具体化したとしても、その具体化されたイメージと「そのもの」との関係をおさえることができない。こうした語のシニフィアンは確定できないが、世界各国の多くの言語には、こうした語が含まれてしまっているのである。こうした語は、ある意味で未規定的で、それじたいが何であるかを確定することができないような語である。これらには、特有な偶然性が内在しており、本来的で解消することのできない偶然性が含まれている。こうした偶然性を「無限性」に置き換えて議論する仕組みを考案してきた前史もある。そうした語をむしろ積極的に活用してきた哲学の前史がある。語の内実が決まらないのだから、どのような意味を盛り込もうとそれじたいは偽ではない。とするとこうした語群は、どのように有効に活用するかが決め手になっている。たとえば「存在」という語は、ヘーゲルの『論理学』では、「一切の内容を欠いた、ただ在る」という事態として配置されている。こうした配置には、「存在」という語そのものは、単独では意味を持ちようがなく、それじたいで見れば空虚になってしまうことが含まれている。だから存在の近傍には、「無」がある。無は、何物でもなく、何もないが、「在る」という語とは区別されていることによってかろうじて内容を備えている。そのため無は、在ることと同じであるが、区別されているという事態によって内容をもつ。そのため在ることと無は、同じ一つのことだがまさに区別されることによって反対のものである。これに対して、ハイデガーの「存在」は、万物の根源そのもののという伝統的意味合いが込められており、場合によっては「エネルギーの場」というような意味合いで活用される。一切の存在者にともなっているが、それじたいは姿を現すことはない。いずれの議論も「存在」という語が何を意味しているのかが確定できないことを、逆手に取っている。一方では、存在という語を可能な限り薄めて、実質的な内容を持たせない方向で、他方では意味内実の可能性をすべて含ませる方向で活用されている。いずれにしろこうした語が意味すると想定されるものは、確定されることはない。そのため語と、語の言い表していると思われているものとの関係は、言表に含まれる経験が、それをつうじてどの程度の展開可能性をもつのか、あるいはそれまで気づかれていなかった経験をどの程度さらに明るみに出すかだけが問われることになる。真偽で見れば、どのようにしても真偽を確定できないが、この確定できなさをさらに逆手に取る哲学が出現することを妨げるものはなにもない。だがおそらくそこには耐用年数というものがあり、使用耐用年数を過ぎたものは、当面「哲学用語」の埒外に置かれる。語は、ある意味で人間的な人工的造形物である。由来も分からず、その意味も確定できない。しかも語は、何かについての語でもある。語はつねに語以外のものにかかわり、語そのものを超えていく。ここに語の超越性が含まれている。語はつねにみずからを超える。語の自己超越性を、語とそれが表そうとするものとの関係に置き換えようとすると、ウイットゲンシュタインの言う「内的関係」以上の事態が出現してしまう。内的関係は、語とそれが結びついている事象との関係をどのように詰めても、それを詰めることができないことを意味する。「椅子」という語を四本足の物体と関係づける関係づけそのものの正当性も由来も決まらないことになる。それを超えて、世界や存在は経験の片隅には引っかかっているが、語が結びつこうとするものが決まらない。「・・・についての語」という語の超越性は、実は行き場がない。だがこの語の超越性が止むこともない。語は、つねに何かを指すが、何であるかが確定できない。第二に、心、魂、本能等々の語群である。これらの語群は、活動態を表そうとしている。活動態だから、人間の眼には見えない。不思議なことだが、活動はそれじたいでは見えず、活動の結果や活動にともなう物しか見ることしかできない。脳は見えるが、心は見えない。物体は見えるが、エネルギーは見えない。これが人間の眼の不思議なところである。これらの語群でも、シニフィエは決まらない。具体的なイメージがないからである。しかも調べることもできない。魂という語は、現在でも魂のシュートとか、魂の籠った低めギリギリのストレートとか、比喩として活用されており、何となくだが分かる。それぞれの事象で「魂」と感じられるものを「魂」の典型的な活動だとすることはできる。川辺で死んだワニが死後4日も経つのに、近くを通りかかった人に噛みついた事例をヘルダーが取り上げている。気持ちは分かるのだが、これでは死んだ後でもしばらくは身体に住み着き、身体を動かすもの程度の意味合いしか残らない。そのため魂の内実はどのようにしても確定できない。それどころか医学的に見れば、「魂」という実態(実体)は存在しない。「魂」は複合的な活動態だと考えておくのがよく、かつ合理的である。これらの語は、特殊な活用法を見出す方向で使用できる場合に、新たな比喩を創り出す方向で活用することができる。 意味内容が決まらない語については、それを活用するさい、文や文章で表すことになる。主語-述語形式で、書き表すのである。ところが活動態では、主語が決まらず、主語の内実が次々と変化していくこともある。たとえば渦巻を例にすれば、渦巻には特定の運動のモードがある。それを写真にとることもできれば、絵にかくこともできる。だがそれは活動の断面もしくは活動の結果であって、活動を行う当のものではない。活動態は、活動の産物を創り出すことはあっても、産物が活動の主体であることはない。こうした場合には、主語が決まらないのである。活動を、主語-述語形式に落とし込んだとき、活動そのものは主語ではありえない。むしろ活動から主語に相当するものが作り出される。こうした場面では、活動態を名詞(主語)で表現することが不適当なだけではなく、そもそも主語-述語関係が、活動態の表現として、事態を歪めてしまうことにもなる。主体が何かを行うのではなく、ほとんどの場合、主体こそ活動の結果であることになる。「述語的世界」と言いたくなる気持ちは、理解可能な範囲にある。だが活動態は、動詞で表現されるようなものではない。動詞は、基本的には主体が何かを行うような場面で作られている。「私は歩く」「私は考える」「私は散歩する」というように、主体の意図や意志にかかわる範囲で、動詞は作られている。その範囲内の動詞でまかなえる事象はごくわずかである。かりに動詞の一つとして産出という動詞を持ち出す場合でも、産出関係はどのように「産出的因果」に落とし込もうと、そこには本来的な偶然性が含まれてしまう。活動態は、主語に相当する実体を創り出すことを必要条件とはしていない。いまエネルギーの場から粒子が出現する場面を想定してみる。エネルギーの場の局所的な歪みが、運動の滞留を生み、そこから粒子が出現すると考えてみる。この場合、「エネルギーの場が粒子を産出した」、と考えることはできない。たとえ局所的な運動の滞留があったとしても、それが解消してしまうこともある。もちろん粒子になることもある。そうした事態を表すのが、「ゆらぎ」である。その意味でエネルギーの場は、粒子を生み出すような仕組みが備わっているのではなく、産出関係というより、場そのものの自己組織化の一断面だと考えたほうがよい。こうして本来的な偶然性を、むしろ積極的な創造性へと転化することができる。 活動態を捉えるさいには、原因-結果、根拠-帰結の関係は、カテゴリー・ミステイクであった。また産出関係は、一つの比喩としては有効だが、そのうちには何段階もの仕組みがある。つまり産出関係の詳細な内実が問われるのである。そして「ゆらぎ」のような不確定性や自己組織化のような創発的な事態を捉えるためには、主語-述語関係で組み立てられる文の構造を手掛かりにすることは、まったく適切ではない。哲学の主要な道具立てとなっている「言語」(普遍化されたものが「概念」)は、哲学の手掛かりとして有効に機能しないという面が多々ある。少なくとも、主体そのものの出現と形成、主体の行為としての動詞の自律性と自律性のモード等々の課題に光をあてながら、記述していくための仕組みを考案していくだけの構想が求められることになる。そのとき論理の内実に新たなカテゴリーを追加しながら進むよりない。 歴史的経緯で言えば、20世紀の「構造主義」は、論理のモードに新たな項目を追加した。それが言語学由来の関係のモードであり、基本的には隠喩・換喩である。ここには要素的言明の真理値を確定しながら、真の言明を積み上げて行く論理実証主義への異論と、要素間のネットワークを取り出すと言う経験科学の延長上の手法がある。真理要求と事柄の確定を同時に保証するのが、構造的なネットワークである。そのためこの場合、反省への信頼は、個々の事象をつねに超えでていく全体性と対になったものである。しかも哲学が鳥瞰的な視座の確保を行ない、経験科学が実証的な実績を積み上げて見せるという、哲学と経験科学の蜜月が容易に形成されたのである。事柄の関係としての隠喩と換喩の威力は、凄まじいのもがあった。レヴィ=ストロースは、フランス語の馬の命名で、馬と人間との集合関係が換喩的であれば、命名法は隠喩的になり、馬と人間との集合関係が隠喩的であれば、命名法は換喩的になるという命名のダイアグラムを導いている。たとえばシャハヴァンテという馬の名前であれば、人間の芸名の延長上に人間の名前と共通の集合に属している。このとき馬は人間から観望される存在である。人間と馬の生活圏は相互に独立になっており、生活圏が隠喩的であれば、命名は換喩の延長上に配置される。ここでは隠喩、換喩が集合の関係として拡大使用されている。複数の集合が、部分-全体関係に入らず、にもかかわらず密接な関連にある場合が隠喩であり、部分-全体関係で配置できるものが換喩である。馬の命名規則の一部がこうしたものである。このことの意義は、通常規則があると思われていないようなところに規則のネットワークを張り出して見せるという発見的な手続きである。またヤーコブソンは詩的言語の分析で、詩の言語は、語の選択の軸を、結合の軸へと投影したものだという。語の集合をとれば、換喩的である語相互を、隠喩的関係に投影し、変換するのである。換喩と隠喩には当初より、未決定性と偶然性が含まれており、構造的ネットワークの特質は、未定、未了、未完である。構造主義は、科学的探究という手続き的な単純さと、その内部に含まれた偶然性をむしろ構造そのものの出現と変容として扱うという果敢な企てをやったのである。だが構造的ネットワークはそれじたいでみずからを組織化することもなく、みずからを動態化することもない。そのためこのネットワークと並行して、構造改革やパラダイム転換を標榜する科学革命、あるいは構造の剰余が繰り返し主張されることになった。これらの構造の動態化は、構造的ネットワークと並行して主張され、相互に外在する。唯一それらをつなぎとめているのは、視座として確保されている主体としての「人間」である。 だが「人間」こそ、内実が決まらない典型的な語でもある。人間は、それじたい何になり続けているかが決まらないのである。生物学的には、人間の範囲は決まるのではないかと思われるかもしれない。つまり人間の集合は確定でき、馬や豚やクマやイノシシや鶏とははっきりと区別できる。この区別が行われる限り、人間の集合の範囲は決まるように見える。だがこれは外延の範囲を決めることにしかなっていない。それによっては、人間の内包(内容)は残念ながら確定できはしない。人間は、みずからの内包を更新し続ける存在だと考えた方が、人類史の実情に合っている。フーコは、『言葉と物』の後半で、古典期と現代の間にある大きな裂け目を経て以降、現代の知性の張り出す位相空間の結び目に「人間」というある種の「代表象」が生み出されたと考えた。その結果、知の枠取りが変容すれば、人間そのものが消滅するという予言めいた発言を末尾で行うこととなった。実際構造主義的な発想からすれば、そもそも人間とは、構造の作動の下で浮動する変項の一つでしかなかった。つまり「人間」とは、こうした構造のネットワークのもとで張り出される「浮動体」でしかない。そのことと、ともかくも毎日、食べ糞をして生きていく生存体としての人間とは、明らかに位相が異なる。それは人間像の乖離であって、リスクともチャンスとも言えるような新たな局面なのである。
超越論的経験論哲学の思い込みの一つが、拠点の確保であり、物事の始原、物事の究極への探求だと思われている。そしてそれは人間の基本的欲求でもあり、それじたいは解消されるような欲求ではない。さらに真への欲求も根強いものがあり、それは同時に「根拠」への問いとなって表れている。個々の経験にあらかじめ前提されている根拠を明るみに出し、それを一揃い整合的に整えることがカント哲学の課題であった。昨晩の晩御飯には、鰻と刺身を食べ、その前の晩御飯にはうどんを食べ、その前の晩御飯には牛ステーキを食べ、その前にはスパゲッティを食べたとする。個々の晩御飯をくっきりとあるいはうっすらと思い起こすことができる。そして前後関係で配置することができる。そのとき配置を可能にする共通の座標軸が前提されているはずである。それが「時間」であり、個々の晩御飯を前後関係で配置するさいの共通の前提である。そのとき3日前の牛ステーキをたまたま思い起こせないこともある。それはブランクとなって、配置のなかから具体的項目が空白となる。また思い起こせないだけではなく、人為的にそこを空白にすることもできる。それと同じように、共通の座標軸となっている時間そのものを取り除いて空白にすることはできるのか。これは実際にカントの行っている論証の一部である。そして時間そのものは取り除くことはできないのだから、それは経験に先立ち(先験的)かつ知性そのものにあらかじめ備わっている(アプリオリ)ことから、人間の経験には、個々の経験に先立つ広大な根拠の領域があることになる。 しかしこの場面で、鰻と刺身やうどんが前後関係で配置されるとういう配置の行為とともに、そこに共通の座標軸も同時に形成されていくと考えることもできる。事象の認識とともに同時に根拠となる共通の前提も形成されると考えていくことができるのである。根拠という前提があらかじめどこかに存在すると考える必要もない。そうだとすると経験は進行しながら、みずからの根拠も生み出し、その根拠をさらに更新しながら進んでいくこともできる。こうなると根拠という意味合いが変わってしまう。一切の手続き的プロセスとは独立に、どこかに拠点が存在するという思いを残すための場所が、もはや存在しないのである。それと同時に根拠(前提)への問いはそのまま残り、根拠への問いを内部に含んだまま、「拠点論」とは異なるかたちの議論が成立することになる。こうして経験とは切り離された叡智界を独立に設定しなくても、根拠への問いを経験の形成にとってより有効に活用することができる。この場合、根拠とは、「超越論的相対性」でしかない。それでも根拠への問いは内的に含まれている。それが超越論的経験論と経験科学との違いとなる。もっとも優秀な経験科学者は、おしなべて「根拠への問い」を併せもっている。根拠への問いは最終的に行く果てがない。それはヘーゲルの言うように「没落への道」なのである。だがヘーゲルの場合、没落への道は、最終的には知の総体性として、別様の救済を受けることになる。それによって知と相関する現実性の総体は、ヘーゲルの場合たとえ無限性をもとうとも見かけ上あらかじめ決まっているように見える。 こうした事態は別様なかたちで、フィヒテの当初の議論の立て方にもみられる。『全知識学の基礎』の原則論は、認識論と実践論の共通の前提を取り出す試みとして、構想されている。本人がそう述べてもいる。そして「自我」が設定される。この自我は、通常感じているような「私」というような経験的浮動体ではなく、「みずから自身をセットアップする働き」のことである。この働きは、自我を産出する。セットアップする働きも自我であり、セットアップされたものも自我である。ここではある種の循環が生じているが、もはや反省の循環ではない。むしろ産出という事態を、働きと事象に区分したうえで、それを一つの事柄にまとめ上げているのである。それが「事行」と呼ばれた。 普通に考えれば、セットアップする働きは、セットアップされた事象よりも広範な可動域を備えている。産出する働きとしての自我が、産出された事象としての自我と、同じ一つのものに成ることはあり得ないのである。ところがそれを認めると、出発点が確定できなくなる。かりに出発点がそれとして確定できなくても、それを「設定する」ことはできる。この設定が、「措定」とも「定立」とも訳されている。出発点は、一つの設定でよい。問題は、むしろこの設定から「どこまで進むことができるか」である。あるいはこうした設定をすることで、どこまで原理的な課題を取り出し、それに対して考察を加えることができるかである。どのような拠点を設定しようが、それ自体が問われるのではない。またそれは問いようがない。出発点の背後や外に、それを問うための助走路も余白もないはずだからである。そうだとするとそこからどの程度のことを明るみに出し、新たな現実が見えてくるかが、議論の成否を決める。この力点の移動によって「体系」(システム)の意義が異なってくる。見かけ上拠点哲学だと見えているものは、正当化の拠点を確保して、そこから正当性を維持しながら進んでいく議論である。しかし正当性の保証はなくても、前に進むことはでき、前に進むことによってだけで明らかにできることだけが、この哲学の成果となる。こんなふうに考えていくと、デカルトの「思う我」も、拠点としての重さを持たせる必要もない。思う我から、どれだけのことが明るみに出たのかだけが問われることになる。事実、そこから解析幾何学という巨大な成果が得られているのである。こうして本人がどのような思いを込め、どのような意図で開始された議論であっても、そこから進んでいく議論の内実の豊かさだけが、この議論を支えることになり、それが議論そのものの成果である。どのような根拠も、そこからの展開可能性によってだけ支えられていることになる。拠点ではなく、経験の進展とプロセスの豊かさだけが、実質性をもつのである。 根拠への問いは、たんに根拠そのものを暫定的なものにとどめるだけではない。前提を別様なものに置き換えたとき、いったい何が起きるのかを試行錯誤する回路が拓けている。幾何学の定義に、直線とは2点間を最短で結ぶものというのがある。点から線を考えていくときの基本なる定義である。しかし最短距離で結ぶ線は一つに決まるのだろうか。一つに決まる場合には、すでになだらかな「平面」が前提されているはずである。2点の記された面が、曲率をもった面であれば、2点を最短で結ぶものは、一つには決まらない。かりに球面をとり、両極に2点をとれば、2点間の最短距離は無数に引くことができる。こうして「最短」という事態に異なる可能性が開かれてくる。こうした議論は、実はカントに出てくる。 ライプニッツが、神による世界の創造を考察したとき、神が無駄なことをするとは考えられないので、世界を作るさいの建築コストは、最小だと述べている。建築コストが最小だとして、建築のプロセスは一通りに決まるのだろうか。世界を作るさいの最小作用には、力学が貫いていることは間違いがない。だがコストは、最初の開始と最終の産物との間の落差でしか決まらない。その間でどのようなプロセスが進行するかを決定しているものは、何もない。こうして前提を別様なものに変更し、世界の可能性を別様に開いていくことが、超越論的経験論の特質なのである。超越論的哲学は、経験論へと接続されるとき、もっとも豊かな姿となる。 おおまかな見通しとしてシェリング、ベルクソン、ドゥルーズ等々に引き継がれていくこの超越論的経験論は、今日の哲学の選択肢のなかでは、現象学と並んで、相当に有望なものの一つである。その内実としては、現時点でいくつかの特徴がある。以下箇条書き風に特徴を取り出してみる。(1)根拠への問いを、知の基礎づけではなく、知にとっての選択肢を増大させる方向で行う。根拠はつねに現実が別様でもありうる可能性の示唆のために用いられる。(2)そのため根拠は、どこまでも暫定的な設定(措定、定立、セットアップ)として解明され、そこで解明されることは超越論的な相対主義(フッサール)に留まる。(3)現実性の範囲は、あらかじめ決定されてはいない。むしろ現実性を拡張する方向で、さまざまな素材と経験科学的な知見は活用される。(4)経験の可能性の条件の解明ではなく、経験の拡張の可能性の条件が問われる。つまり経験そのものの可能性を増大させ、経験の弾力を高める方向で考察がなされる。ヘーゲルの場合、(3)を満たさず、超越論的目的論となる。目的が外に存在せず、目的が体系に内在する絶対的観念論である。つまり事象の範囲はあらかじめ決まっている。(5)事象は、つねに別様でありうる可能性の下で考察される。論理的懐疑ではなく、さらに経験を前に進めるような選択肢の提示が基本となる。経験科学、芸術家、身体技法等々の領域へとアイディアと霊感をあたえることができれば、おのずと現実性の範囲は変わる。ことに身体に働きかけることは、多くの場合何が起きてしまったのかがわからないために、そのぶんだけ有効である。(6)考察の仕組みのなかに、どこに選択肢があるのかの注意が必要とされる。たとえば通貨、国家、さらに言語のような対象に対して、それらの本来性は何なのかというように問うことになる。通貨には、法定通貨以外の多くの通貨が実際に活用されており、本来的通貨は決めようがない。また言語の範囲も決めることができない。インスタグラムで音楽を流しているだけでも言語的な機能を果たす。本来の国家が何であるかは決めようがない。サイバー国家がありうる局面には来ている。国家の定義は、主権があること、領土があること、国民がいることである。世界の各地でテロが起きるたびに犯行声明を出す「過激派国家」は、おそらくサイバーという位相領域に存在する。領土という発想が、物理的領土に限定されなくなったのである。(7)こうした場合、現実の作業は、何をモデルとして活用するかに大幅に依存している。シェリングの場合、不均衡動力学を活用し、ベルクソンの場合、「人間進化論」と呼ぶべきものを活用している。このモデルが容易には解決できない「課題」を含んでいる場合には、奥行きと深さのある哲学となる。ある意味では、こうした課題を見出すための発見的手続きが、このタイプの哲学の成否を決める。こうした課題に到達できなければ、「哲学」を自称した場合でも、文芸評論や文化評論に留まってしまう。 こうした項目のうち、(5)の経験科学、芸術家、身体技法と連動的な活動を続ける中で、さらに新たな項目が付け加わる可能性がある。すると超越論的経験論は、あらかじめ方法的な枠が決まっていて、それに応じていくつかの領域で応用研究が行われるようなものではないことがわかる。むしろ展開しながら、新たな課題を見出していく「プログラム」のようなものであり、経験の可能性が広がるに応じて一挙に劇的に転換する可能性さえ内在している。哲学は、根拠を確定したり、世界をまるごと抑え込むような見かけ上の特権性をもつ。そこにはさまざまな思いが見え隠れしてもいる。だが哲学がみずからで見出す課題とともに、そこで回復され増幅される経験の弾力に比べれば、どのような特権性もひと時の話題作りに留まるように見える。超越論的経験論とは、こうした特権性を告発し、それに対抗するのではなく、こうした特権性の傍らを騒ぐことなくおもむろに通り過ぎていくのである。
2 哲学はなお何をなしうるのか
ガブリエルの思い出マルクス・ガブリエルという才人がいる。ドイツ観念論を母体として広く分析哲学にまで及ぶ議論を展開している。この才人の特徴は、事柄以上に事態を過度に鮮明に描く能力を持ち合わせ、トリックすれすれの論証能力を使うことができること、この論証能力を活用して哲学は「前進」できるというおおらかな確信を持ち合わせていること、そしてどこまでも言語と解釈が哲学の主要な場であり、この場に限定して哲学はなお進歩できると確信していることである。ガブリエルの哲学史の素養は、十分に蓄積されたものである。だが哲学史の素養に溢れていることと、哲学として魅力あるかどうかは、まったくの別問題である。ガブリエルの『なぜ世界は存在しないのか』は、「新実在論」を標榜する著者の一般向けのサーヴィス精神にあふれた本である。この本を傍らに置きながら、現在哲学が何を課題としうるかを考察したいと思う。存在と呼ばれるもののなかにはどうみても疑わしいものはたくさんある。近世のイギリスで見られた魔女裁判のさいの「魔女」や、幼いころ村のはずれに住むと言い伝えられた「山姥」や、突如雨が降り気温が下がると「子供の臍を取りに来る鬼」という類の伝承のなかにある個物は、言い伝えのなかだけに存在する。そこで疑わしいもののなかから、哲学的な誤謬を取り出し、それを「偽」(間違い)だと明言することで、哲学は前進できるという思いがガブリエルにはある。その誤謬を断ち切ってしまえば、哲学は足元を掬われることなく、また壁にあたったまま停滞するような議論を中止させることができると考えているようである。その代表が「世界」であり、物事の一切の総体性を表す語である。この語を存在の一覧表から取り除くことで、多くの偽を取り除くことができるというのが、ガブリエルの主旨である。そしてそれ以外の存在は、可能な限り広く取るのである。 なぜ「世界」がターゲットになるのか。認識の仕組みのなかに出てくるある誤謬を取り除くためである。世界をカントの物自体に置き換えて考えてみる。人間の認識は、認識のなかで捉えられた表象であり、その場合にはある物についての表象とたんなる幻覚とが区別できなければならず、そのためにも表象はなにかについての表象でなければならない。この何かについてのという場合の「何か」が物自体に相当する。認識が知りうるのは、表象までであり、物自体は知りようがない。だがそれを無しで済ますわけにはいかない。要するに認識の背後世界のことであり、この背後世界はまさに認識からは届かないと設定されているのだから、認識にとっては一つの壁である。同じようにして認識からは届かないと仮構された「世界」も存在しない。これらは認識が、まさに認識であることによって仮構されたものであり、認識がみずからのうちに作り出した剰余であり、それは存在しないということになる。 ガブリエルが取り除こうとしているのは、認識が壁に当たることによって停滞するところのものであり、認識そのもののなかにあるある種の誤謬である。ドイツ哲学のなかでは、「限界概念」と呼ばれてきたものであり、限界概念は個々の事物や事実とは同じ扱いができない。 ガブリエルが断ち切っておきたいとおもっているものがもう一つある。それは一切の事実や事物をそこへと帰着する基盤を想定して、そこから一切の議論を組み立てようとするある種の「還元主義」であり、本のなかでは「構築主義」と呼ばれている。心は脳のさまざまな働きからすべて説明しうるというのは、手続き的なプログラムであり、それはそれで成立するのだが、それが最初から立場として設定され世界像となるような立論に反対しているのである。 こうしてガブリエルが排除したいと考えているのは、世界を像として捉える「世界像」としての世界観であり、科学的世界像も像である限り、間違っていることになる。そして芸術や宗教にも固有の経験があるのであり、その固有性をそれとして認めることで世界の多元性を認めようとする。このとき哲学は、余計なこだわりを持たず、余計な壁に直面せず、多様性をそれとして受け取るような豊かさを回復することである。ガブリエルの描いた世界は、つまるところそうした精神の豊かさを回復するためのいわゆる「人生哲学的解釈学」だと考えてよい。そしてそのことを立場として主張する限りは、おそらくほとんどの人には「常識」もしくは「異論の余地なし」だと思われる。 ところが他面では、意味として捉えられるものは、それはそれで存在し、対象領域をもつ。語りとして成立するものも、映像で描かれるものも、意味として捉えられたものはすべて存在することになる。この場面の議論では、性急な「存在」の拡張がなされている。言語的に語られ、対象領域として意味の場をもつものは、すべて存在するということになる。このことに関連して、領域の領域としての世界は、それを語るための領域が、世界の外には存在しない。つまり語りようがない。そうしてみるとこうした議論の延長でも、世界は「存在しない」ことになる。実際には、基礎づけ的正当化にさいして、「世界」をどのようにしても「基礎づけることができない」ことを基調としている。 これじたいは乱暴な議論だが、この乱暴さを上回るほどの議論のうまさと面白さをガブリエルの話は持ち合わせている。この場面では、ガブリエルはすでに才人というより反射神経抜群の哲学的タレントなのである。このタイプの哲学者は稀に存在し、日本では故大森荘蔵がそれに近い。大森荘蔵は、ときとして「哲学の仕事は、人々にぐっすりと安らかに眠ることの条件を作ってあげることだ」と言っていた。まさにこれが「人生哲学」の基本となる。ただしこうした議論にはいくつも論証の隙間があり、丁寧に詰めて見なければならない箇所は多い。ガブリエルは、一切の背後世界と科学的な還元主義的世界像(構築主義)を取り除き、直接的な事実や物があるという。認識とは表象することではなく、直接知ることである。そして事実や事象は、領域(意味の場)に現われ、しかも多くの領域(意味の場)に出現する、というものである。これがガブリエルの多元論の骨子である。伝統的には、直接認識は、直観に委ねられ、直観の働きだと考えられてきた。これを感覚的直観に拡大して多用したのが、現象学である。感覚的直観が、「知覚」だと呼ばれている。知覚は、物を直接知覚するのであって、物についての表象を形成したりはしない。知覚では、意識極と対象極に分かれ、こちらから向こうというつながりはあるが、どこまでが意識で、どこから先が物かという区分があらかじめ決まっているわけではない。あらかじめ確定された意識と物を志向性によってつないでいるわけではない。現われは体験的直接性であって、すでにして成立している世界のことであり、そこには体験的行為を行う身体や時間がおのずと含まれている。こうした現われの出現においてすでに含まれている身体や時間を、新田義弘は「現われの媒体」だと呼んだ。端的に言えば、フッサールの行った「現われ」という領域の設定が、途方もない深さをもっていたのである。 こうした現象学から見れば自明の事態を、認識論で語ろうとすると、意味から語り、意味の場を語り、意味の場の多元性を語るようなことになる。意味の場とは、現象学で言う「地平」のことであり、地平は知覚の継続のなかでそのつど変貌していく。これはすでに見飽きた「地平主義者」の言い分である。むしろ現われは、生存の重さと深さをかけておこなわれてしまっている体験的現実である。その現実の内実に迫るような探求をすっとばしてしまうと、どうしても「地平主義者」に行きついてしまう。新田義弘以降の日本の現象学第二世代には、こうした「地平主義者」がかなりいた。地平主義者には好都合なことだが、世界とは「地平の地平」のことであり、地平相互の移り行きや地平相互の比較が必要な時に、どこかで想定されているもののことである。人間の言葉にはうまい言葉がないので、とりあえずそれを「世界」と呼んではいけない理由はない。地平主義者は、たとえば統合失調症タイプの世界の不連続点にすでに過度の自明さをもって生きている人や、脳神経系の疾患を背負い固有の世界を生きてしまっている人たち、固着を体験の基本的なモードにしている人たちに対して、世界は多元的であるなどという言い分が、ことごとくすれ違ってしまうことに思い至ることがない。あるいは思い至ってもそれに対してどう対応するのか選択肢を設定することができない。世界は多元的であるという言い分がまったく通じない人たち、多元的であることにことごとくすれ違ってしまう人たちは、実はたくさんある。 ただし1箇所、ガブリエルの議論にも、こうした体験的現実に迫るような箇所がある。それは末尾に近い「感覚」を論じた部分である。ここでの議論は、意味や意味の場やそれらの多元性とはまったく異なったことが語られている。「感覚」は意味の母体ではあるが、それじたいはいまだ意味ではない。
わたしたちの感覚はけっして主観的なものではない、ということです。わたしたちの感覚は、わたしたちの皮膚のしたに、あるいは皮膚の表面に挿入された添加物ではありません。むしろ感覚とは客観的な構造であって、わたしたちのほうがそのなかに存在しているのです。(マルクス・ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』288頁)
主観と客観の区別をおこなっておくと、感覚は配置に困るようなものである。感覚は、主観から客観を感じ取るような働きではない。だからと言って、感覚は「客観的な構造」というわけにもいかないのである。眼を開ければ外界が見えている。眼という働きは、すでに視界一面に広がっている。眼球の構造は、身体の一部に属している。眼球という器機と眼の働きは区別して考えたほうが良い。そのとき感覚という働きこそ、はじめて「内外の区分」を行っているのであって、それはすでにして世界の現実と地続きなのである。感覚は、主観、客観の区分以前の働きであり、まさに感覚をつうじて現実のなかに区分が生まれてくる。感覚には、本来「内部も外部もない」。そしていまだ意味もない。感覚はそこから意味が出現してくるさいの母体であり、意味の場の形成に不可分に関与している。 ガブリエルの論証的な議論の多くは、カテゴリーの論理的誤謬を取り上げている。存在者の存在と「存在」そのものを同列に同じカテゴリーで扱うことはできない。脳神経系の事実をどのように積み上げても、現われや意味をそれで置き換えていくことはできない。それぞれは意味の領域を異にしており、あるカテゴリーを他のカテゴリーに置き換えたり、あるいは帰着還元できない。それはその通りである。そのとき同時にカテゴリー間の関係は、どのようなものかという問いは残されたままであり、その場面でそれぞれが固有の対象領域だとすると、そこに「多元論」が出現していた。奇妙なことにこの多元性を見極め、多元性のなかを自由に移動していく「人間」(主観性)だけは、多元的ではない。この「人間」がこっそりと前提されながら、なお多元性の間を自由に移動する主観として最大限の働きをしてもいる。この人間の行っていることこそ、意味や意味の場とは独立の「経験」なのである。この経験こそ、哲学の現場である。 あるいは多元論という事態には、多元性を見分けている人間という主体が多元性の外に暗に前提されている。多元性の主張は、まさにそのことによって多元的ではない。こうした議論そのものは、実はすでに手の込んだ冗談に近い。 こうしたガブリエルの議論に乗りかかりながら、こうした多元論の哲学が論じ残している当面の課題を設定していくつもりである。
哲学の当面の課題(1)存在には、さまざまなモードがある。存在という名詞の手前に、「存在する」という動詞的な働きがある。存在にさまざまなモードがあることはすぐにわかる。伝承や文書のなかで描かれた「悪魔」という存在は、眼前の物体の存在とは、存在のモードを異にしている。「存在する」という動詞には、働きとして多くのモードがあるはずなのだが、それを分析することは容易ではない。眼前一面の過飽和の水蒸気に満ちた道路がある。そのとき「ヤッホー」と叫んでみる。それによって一挙に靄が出現し、視界が不透明に白濁し、道路さえ見えなくなることがある。この靄の存在は、いったいどのような存在なのか。過飽和の水蒸気に満ちた大気は、流動し運動を続けているが、そこに別の働きが関与したとたんに、相転移が起きている。この相転移は、事象そのものの変化であって、突然現実性そのものが変化したのである。それは意味が変化し、それにともなって意味の場が変化し移行したようなものではない。存在するという動詞は、ひとつの変化であり、変化そのものを感じ取っているからこそ、靄のなかを進む歩行をしばらく中断したり、元来た道を逆走することもある。少なくても意味と意味の場が出現するのは、ほとんどの場合、変化の結果を認識したときである。変化の結果だけを認識している場面では、「存在する」という活動をそれとして捉えたことにはならない。 こんなふうに考えていくと、流動体の存在、物(剛体)の存在、有機体の存在、心の存在、物語のテーマキャラの存在、論理的カテゴリーの存在、理念の存在等々は、存在するという活動態のモードがそれぞれ異なっている。たとえば魂については、多くの人がそれとして論じ、対象領域を形成している。ところが医学的に見れば、魂は活動の複合体であり、それが語られるのはひとつの比喩としてだけである。中世の文献のなかでは、「魂」という語は意味を形成し、対象領域を形成している。ところが現代医学のなかでは、比喩としてだけ活用され、比喩的な意味ではあるが、医学という対象領域には「魂」は存在しない。意味の場が異なれば、魂は存在しなくなる。この場合には、意味の場そのものの相互の比較が必要になる。だが存在の数や原理の数を増やしてはならないというのは、ウオッカムの鉄則でもある。同じようにカントが『純粋理性批判』で取り上げているような、燃素(フロギストン)の話がある。これもひと時語りのなかで存在していた。燃焼時に物体から飛び出る何かである。燃焼とは物体から燃素が出ていくことだと考えられていた。そしてこれは多くの燃焼の現実に適合するのである。まだ化学元素の整っていない時期の話で、これはこれで成立している。後に燃素は存在せず、物体から出ていくのは、炭素や水素であり、そのさいに二酸化炭素や水蒸気のような化合物となる。酸素の化合と燃素の発出は表裏の関係だが、意味の場は異なっている。とするとこの場合には、たんなる多元論ではすまない。燃焼という意味の場そのものが変容し、存在すると思われていたものが、端的に消滅する。ガブリエルの「新実在論」は、むしろどこかかつてのパラダイム論に似てくる。 物(剛体)の存在は、ひとつの活動態がある場所を占めることである。ガラス窓では主要成分である珪素が600年程度の周期で運動しており、そのことによってガラスは維持されている。この維持の仕方が、ある場所を占めることにつながっている。ガラスは光を通すほどの隙間に満ちているが、水を通すことはない。この通過できなさが、ガラスという個物の位相領域を形成している。そのため物の存在は、ある場所を占め、かつその場所を他のものによって代替的に占有されないことである。これは物がそれとして在ることの仕組みにかかわっているのであって、意味と対象領域にかかわってはいない。有機体の場合には、占有する場所をみずから変える。植物は成長し身体を変えることで場所を変える。動物は移動することで占有する場所を変える。それをつうじて場所をみずからに固有のものに作り替えていく。それが「生態的地位」と呼ばれている。有機体は、場所をみずからに固有の位相空間に換えてしまう。それが有機体が、それとして「みずから生きている」という意味である。それでは心とはどのような存在の仕方をするのか。最も安直な答えは、心は活動の複合体であって、単独活動態ではないとすることである。そのため特定の存在の仕方をするわけではないことになる。心は一つの働きであり、働きは通常は持続的な活動態の場合には、場所を占める。あるいはみずから場所を指定する。ところが心のなかでも、「主観性」ともなれば、そもそも場所を特定しないことが特徴となる。デカルトの定式化と同じように、精神の本性は、「思うこと」であって、「位置を占めること」ではない。主観性は、どこにあるのかという問いが主観性そのものとすれ違うのである。こうした人間の主観性を暗に活用することで、実際のところ、対象世界の多元論が成り立っている。 こう考えていくと、一つの重要な帰結が生じる。活動態がそれとしてみずからを個体化するという場面が、「存在する」という動詞の必要条件であることだ。このことを軸として考えてみると、映画や文学作品のキャラは作品という場所に、それじたいでどこかを占有したとき、「存在する」ことになる。そうなると何かが存在するかどうかは、むしろ個体化という活動の副産物であることになる。有機体の場合には占有する場所をみずから変えていくことが個体化に含まれている。このとき存在とは、実は派生的な問題の一つである。問わなければならないのは、個体化そのものの仕組みだったのである。 シェリングが、初期の自然哲学で、絶対的産出と阻止から、物質を導き出していた時、物質の個体化と現実性の出現をともに合わせて処理できるような構想を立てていた。絶対的産出や阻止は、動力学の仕組みを使っており、時代の制約下でなされた構想である。だがたとえ仮構された仕組みがどのようなものであろうと、個体化と現実性の出現は、同じ事態の二つの側面であるというシェリングの構想は、おそらく決定的に重要なものである。 世界が存在するかどうか。それはエネルギーの場が存在するかどうかという問題に似ている。個体化以前の場面では、人間の能力では存在するかどうか答えようがないのである。
(2)物事も事象も生成する。意味も生成する。おそらく世界も生成する。生成するものはいまだ意味は決まらない。意味になるかどうかもわからない。そもそも生成は、認識の対象にはならない。また理解してそれとして捉えられるようなものではない。生成もプロセスも、そこになにかは感じ取られてはいるが、意味が分かるというようなものではない。認識は、すでに生成の終わった後の結果しかとらえることはできない。それが認識の宿命であり、認識とはそれが成立したとたんにすでに終わった場面から物事を捉えようとする営みである。認識そのものの出現では、日常的な言い方をすれば、何が起きているのかわからないという場面を通過するはずである。その場面が「経験」(途行き、行為)の本来の姿である。このとき何が起きているのかわからない途行きを進みながら、どこかの段階で経験の進行の予期が働き、中途の安定場所(経験の踊り場)で認識が形成される。これを認識の獲得だとして、途行としての経験を認識へと回収していく作業が、ヘーゲルの議論の要となる仕組みである。何かが経験に起きる。起きている事象をやがて出現する認識に包摂する。この包摂をつうじて、認識はより包括的で、高度なものになっていく。この場面で、認識を獲得したとき、認識そのものをひとたび括弧に入れ、次の途行への多くの選択肢を思い描きながら、さらに別様に継続可能なありかたを模索し、試行錯誤することもできる。認識に包摂することに代えて、認識の安定そのものも一つの副産物だとして括弧に入れ、その場面で再度途行の可能性を拡張していくこともできるはずである。これを「プロセス的還元」と呼んでおこうと思う。この試みに敢然と挑んだのが、シェリングの「思考以前のもの」にかかわる考察であり、思考から見れば、すでに忘れてしまっている経験の層を思い起こすようなものである。思いい起こすことのできない過去は、「先験的過去」と呼ばれ、想起するとは別の仕方で思い描くことができるとシェリングは確信している。それが「神話学」である。こうして経験を集約することに代えて、経験の多次元性を前面に出すことになる。ここから結果として、副産物としての多次元論が成立する。多次元論は、論証の最終目標ではなく、経験の途行の副産物でしかない。これがオートポイエーシスの世界である。こうした方針を採用する理由ははっきりしている。芸術家の創作の場面では、認識のなかに制作行為を包摂したのでは、すでに創作ではなく、評論家に転化してしまう。芸術的制作を、作られた作品の鑑賞に押しとどめてしまうことになる。これではほとんど経験が前に進むことはない。また障碍者の行為形成を行う治療では、認識で自分をわかっても治療が進むということにはならないのである。
(オートポイエーシス的世界観)
オートポイエーシスで副産物のように形成された多次元世界が、こうした図である。これは副産物であって、こうした図柄を見て認識の成果だと考えたのでは、ただちに筋違いとなる。こうした認識を括弧に入れ、行為(途行)へと戻っていくことが、「プロセス的還元」である。こうした図柄は、あくまでも世界観であって、世界の見方にすぎない。「世界観」こそ、初級者の誤謬である。ゲーテが言うように、分かるということは、まさにそれによって何も分からないのである。そこで「行為することが必要である。」認識の反省によって形成されたこうした多元論の図柄では、反省をつうじて反省そのものを括弧入れしていくことが必要となる。こんなふうに考えていくとこれは世界観レベルの哲学ではなく、むしろ「職人の哲学」である。多くを語らず、黙々とみずからの制作物に工夫を続けるものこそ、職人である。芸術家や優秀な科学者や稀な哲学者が、遂行しているものこそ「職人の哲学」である。生成の感じ取りに対しては、多くの場合身体行為とともにすでに対応してしまっている。変化率に対しては、ともかくも何かを行ってしまう。これが生きていることの本性である。ゲーテは、「眼は光によって光へと形成される」と述べていた。認識そのものの出現の場面は、いつもどこか神秘や奇跡に満ちている。出現の姿を、ゲーテは「色彩論」で論じようとした。光と影の条件を代えて、次々と色彩を出現させていた。色彩は意味ではない。見ることの出現の姿こそ、色彩である。だから空の青こそ、色彩の法則だと言い、空の青の背後に何も探してはならない、とゲーテはいう。とすると意味の形成以前の広大な体験世界があることになる。これをどのように扱うかは、現在でも確定できない。手法としては、体験的世界の解明の方法的な手続きである現象学を活用することになると思われるが、同じ手法を何度もただ適用するような現象学が求められているのではない。 意味の手前の世界には、さまざまな事象が含まれている。たとえば身体である。身体は、どのように語られようと、意味ではない。語りのなかで捉えられた身体は、「身体について語られた意味」である。どのように語られようが、それについて語られている身体そのものは、体験的な直接性である。つまり生身の身体であり、直接的事象である。認識された身体は、生身の身体とは別のものである。身体はみずから動き、身体はみずからを感じ取っている。しかも心のような反省的にみずからを捉える仕組みはない。だからと言って、身体はたんなる物体ではない。自己反省のような仕組みはないが、物や意味のように対象領域を形成するわけではない。身体は心のように自己制御できるものではないが、さりとて心から切り離して別物扱いできるわけではない。身体については、圧倒的に語るための言語が不足している。人間の言語は最初から対象についての名前と記述か、感情を整えるための音楽性を帯びた言語か、いずれかである。つまり人間の言語の成り立ちからして、対象記述か内観記述になってしまう。人間の言語は、最初から主観、客観に分離するように作られている。この言語を用いたのでは、身体についてはうまく語れないようになっている。この人間の言語のおかげで、残念ながら人間の能力は構造的に抑え込まれてしまっている。 この言語の現状に対して、メルロ=ポンティの取った戦略ははっきりしている。比喩で言い当てるというやり方である。よくもまあこんな表現を思いつくものだ、というほどうまい比喩を繰り出すのである。ひととき分かった気になることができるが、さりとて何が語られたことになるのかがわからない。言葉を置き換えようとすると、メルロ=ポンティの記述したこととは異なることになってしまう。メルロ=ポンティは綱渡りのような比喩で、身体を描こうとした。 身体を描くためには、言語の限界で言語を活用する能力が必要となる。つまり身体を論じる哲学者は、詩人でもなければならない。一人の人間の言語感覚から見て、メルロ=ポンティの夥しい量の比喩は、どこかから借りてきたものだという思いはすぐに浮かぶ。しかもすぐ近くに優れた言語能力を備えた詩人がいた。それがポール・ヴァレリーである。ヴァレリーからメルロ=ポンティは大量の比喩を借りている。メルロ=ポンティには晩年の『見えるものと見えないもの』という優れた著作がある。そこに「キアズマ」(交叉)という優れた論考がある。視覚と触覚のような異なる働きは、共通の第三者によって統合されるのではなく、どちらかがどちらかを制御するのでもなく、一貫してそれぞれは働き、かつ交叉しているという内容である。「キアズマ」という語も、ヴァレリーから借用したものである。その語を、ヴァレリー自身は「不倫」の心性を表すために使っている。 意味の手前にある事象の一つが「環境」であり、「環境世界」である。人間が生きているとは、環境内を生きることであり、環境は認識対象ではなく、人間の生を取り巻いている。視覚的な比喩で言えば、人間を取り囲むように広がる世界である。環境世界は圧倒的に多様であるが、この多様性は、対象として捉えられた意味と意味の場の多元性とは異なったものである。ここが多次元性が出現してくる場所である。人間は、ハエにはハエの固有世界があり、ダニにはダニの固有世界があるということを推し量ることはできる。だがそうした固有世界に、視点を移動させるようにしては、住まうことはできない。魚は4原色だから、人間の見えている海とは異なり、圧倒的に鮮やかな環境世界を生きているはずだが、人間が実行できるのは、それをシミュレーションすることだけである。つまり薄々分かってはいてもそれを実行することができない多くの多様世界を、人間は周囲に抱え込んでおり、それと共存していることになる。環境は、どのような意味でも対象に落とし込むことはできない。そのため意味ではない。その分だけは、環境への考察は、二重に視点を移動させるような工夫が必要とされる。当の個体からどのように環境が捉えられているかという当事者への視点移動と、当事者がすでに自明な形でそこで生きてしまっていて、当事者さえ認識の手前ですでに生きてしまっている環境への視点移動である。
(3)世界観を軸に哲学を展開していくと、決定的に欠落してしまうものがある。認識は、言語と視点移動によってだけなされるのではない。そこには身体とともに行われる多くの「手続き」がある。見方や観点で置き換えると、哲学的世界観や宇宙観、科学的世界観のような議論になりがちである。いずれもただの「観」である。観を競ったのでは、なにか現実性とすれ違い、まったく別のことを情報と言語と論理だけで論じていることになる。 ガブリエルは、メイヤスーの主張を「偶然は必然である」と要約し、みずからの主張は、「必然は偶然である」と要約している。概念の比較だけであれば、必然が成立するためにはそれに対置される偶然をみずからに不可欠なものとしなければならず、まさに必然は偶然に対置されることではじめて成立することになる。ここが最初の概念操作である。メイヤスーの主張は、どのような現実であろうと、つねに別様になる可能性がある、というものである。現実は、それとして別様になる可能性を内在させているのだから、つねに偶然性を本来的なものとして孕んでいる。これが偶然は必然的であるという意味である。これに対して、ガブリエルは物事を必然だと記述できるためには、必然性(最低限の条件は無矛盾)を証明するための証明の枠がなければならない。ところが必然的な言明の証明を同じ言明の集合から行うことができない。そうすると必然性の証明は、それとして閉じることができない。必然性そのものは、偶然性に開かれてしまう、ということになる。これが「必然は偶然である」ことの意味である。どのように強力な概念的規定(英語では概念的決定としか訳せない)であっても、それじたいは偶然性に開かれていることになる。そしてガブリエルは、自分の主張はメイヤスーよりも、より強力な立場だというのである。 こうした議論に直面したときには、そこからどのような持続的な課題が取り出せるのかを考えてみることが肝要である。メイヤスーの場合、数学的な無限性において、つねに新たな現実性の局面が出現するかもしれないことを立論の基調にしている。「無限性」そのものを人間は捉えることはできない。だから無限性という言葉は、ひとつの大雑把な要約にすぎない。構想を課題へと転換していくために、この場面で「手続き的な経験」が必要とされる。それがだせなければ、ただ言ってみただけである。 ひとつだけ取り上げてみる。人間は一応3次元物体である。いま腸の襞を被覆法で一つ一つ覆ってみる。四角か円の面を使って、繰り返し襞を覆い、面の量を確認していく。面だから2次元である。このとき四角や円で覆うことのできない剰余の部分が大量に残る。この剰余の部分を足し合わせててみたとき、無限に発散したとする。すると2次元の延長で2次元に回収できない領域が生まれる。これは2次元の延長上にはないが、しかしいまだ3次元ではない。とすると2次元と3次元の間には、現状ではいまだ人間が確定することのできない小数点以下の次元があることになる。たとえば2,67 次元や2,83次元が存在することになる。 次元と次元の間には、際限のない隔たりがあり、その隙間で何が起きているのかはわからない。またそれぞれの固有の次元をどのようにして確定できるのかもわからない。無限を問題にすれば、こうした持続的で展開可能な課題が出現してくる。これはメイヤスーにとっては、有利な事例である。こうしたことが手続き的経験である。 自然現象から取り出してみる。お椀をかぶせたような半円球の真上から、水滴を連続して流してみる。水は半円球に当たって右か左かに分かれるとする。確率的には、右半分、左半分に分かれて落ちるように設定しておく。落ちてくる水は、左右均等に分かれてもおかしくないが、実際には一方へ9割、他方へ1割のような落ち方をする。最初の水滴が右に落ちるか左に落ちるかは、確率的な偶然である。つまりそこには「揺らぎ」が含まれる。この揺らぎはメイヤスーの言う「偶然」の物理的な事例である。そしてひとたび右左のどちらかに落ちれば、水滴に落ち方にはっきりとした傾向が出てくる。水滴の落下に「履歴」が関与するのである。この事例の場合には、自然界には論理的な意味での絶対的必然も絶対的偶然も存在せず、そのため必然や偶然という概念を振り回すことが、事態を混乱させていることになる。起きていることは、現実の手続き的な進行であり、そこで起きることの仕組みである。 ガブリエルの行っていることは、正当化(基礎づけ)の手続きが、完備しないということに集約される。78+65=143は正しい計算である。だがなぜ正しいのか。1+1=2という基本的な計算の仕組み(加法の定義)を入れておけば、この定義のもとで導くことができる。だがなぜ1+1は2なのか。それ以外でも良い。1+1=3として定義すれば、その定義の延長上でそこから導かれる解は決まる。1+1=2の正当性は、演算の枠内では決まらない。これが必然は偶然だということの手続き的な意味である。だが1+1=3だとすることの意味は、1+1=2を対照とし、そこからしか決めようがない。1+1=2はたんなる定義の一つではなく、加法という手続きの意味を担うためのモデルケースなのである。そして加法という手続きが、どのような操作なのかが決まらないという事態を示したのが、クリプキである。答えは正解であっても、そこでなにが起きているのかは決まらない。内在的な未決定さが残ることを、クリプキの議論は示唆している。実際に人間でも同じ答えを出していても、同じオペレーションを行っているかどうかは不明であり、コンピュータの計算では、同じ回答であっても異なるオペレーションを行っていることは明らかである。クリプキの議論は、必然性のなかに偶然が含まれることを示していることになる。クリプキの議論によれば、たとえ解が正解(必然的)であっても、そこには偶然が含まれる。この議論の立て方は、ガブリエルが持ち出すような必然的正当性の証明が完結しないという場面ではない。正当であることをあっさり認めても、なおそこに内在的な偶然が含まれるという事態である。これはガブリエルが持ち出している事例以上に、ガブリエルにとって有利な事例である。正当化論証が完備したものにならないという話題は、ミュンヒハウゼンのトリレンマとともに、ゲーデルの「不完全性定理」ですでにさんざん議論されてきた。だが正当化論証とは、本来異なるところに問題があったのである。これらの事例は、反省的な多元性に代えて、むしろ多次元性を示している。 数学や物理学は、哲学に似て、根本のところを探し出すような作業である。最も基本的なところで世界の成り立ちを支える原理を取り出す手続き的な作業である。それを科学的な世界観と言ったのでは、たんなる評論家の言い分になってしまう。そして素直に認めた方がよいと思うことだが、優秀な数学者や物理学者は、哲学者以上に哲学的である。哲学者だけが哲学をやっているわけではない。ガブリエルには、どこかで哲学者だけが哲学を行っているという暗黙の思いが前提されている。そこから「自然主義」や「科学主義」への無理解による余分だと思えるほどの批判が繰り出される。 科学は、世界観ではなく、どのように成果をだしても、世界観を目指してはいない。測定器具を作成し、測定のための理論を作り、そのうえで仮説を立てて事実を確定していく。すべて手続き的な行為である。それまで見えなかった現実を見えるようにし、ときとして新たな現実を創り出しても行く。科学を世界観として捉えたのでは、こうした手続き的行為は語られることもなく、傍らを通り過ぎられてしまう。
(4)哲学の進歩(前進)はどのようなものか。これは奇妙な問いなのだが、哲学は多くの場合命題を扱い、命題形式で叙述する。命題は真偽が決まる。そして日常言語の大半は言明であり、真とも偽とも言えない。「私は、明日の試合には勝ちます」という言明は、決意や覚悟の表明ではあっても、命題ではない。たとえ明日の試合に負けても、誰も嘘を言ったとは言わず、残念だったねとねぎらうことになる。偽の命題を排除し、偽を訂正して、真の命題だけを集約すると、哲学は前進することになる。本当にそうなのか。 たとえばデカルト的世界観では、世界は二つの原理(思うことと延長すること)で設定されている。ここで言いがかりに近い議論を向けてみる。なぜ原理は二つだけで、二つだけにとどまるのか。これが世界観レベルの言いがかりであることははっきりしている。哲学的にはおかしくても、そこから派生的に巨大な変化をもたらしてしまうことはいくらでもある。延長は、条件を変えて圧縮すれば、点になる。点から成る世界は、幾何学の世界である。そこからデカルトは、独力で「解析幾何学」を作り上げている。たとえ世界観レベルで奇妙な世界を描いたとしても、そこから持続的で発展的な展開が生じれば、それは大きな前進をもたらしていることになる。デカルトの「機械論」はさらに圧倒的な派生効果をもっていた。インドにも中国にもこうした機械論は存在しなかった。ところが機械論は瞬く間に世界を制覇したのである。デカルトは、死体解剖から人体を細かくとらえることの限界を知り、たとえば心臓の仕組みを知ろうとすれば、井戸のポンプを調べた方がよいとやり方を変えている。それによって心臓の解剖に代えて、ポンプを見ることで、仕組みや働きを「拡大鏡」にかけるように捉えていくのである。これが機械論の骨子である。現実性のなかに視覚的な比喩の自在さをもたらしたものが「機械論」である。光が当たって反射していくさいの規則は、テニスボールの跳ね返りから定式化している。機械論は世界観ではなく、一つの手続き的な経験だったのである。 この時期、哲学はいまだ職業的な専業としては成立していない。哲学とはある意味「何でも屋」であった。スピノザはレンズ磨きをやり、ライプニッツはハノヴァーの行政官だった。カントの頃から哲学が専門職業化して、それ以降哲学という特殊領域が形成されるようになった。哲学はこれ以降、もっぱら「概念」(言語のなかでも普遍性をもつもの)を扱うようになっている。カントは大学の教員として、立派な職業的哲学者であった。要するに哲学で食べていけるようになったのである。これは普通のことではない。哲学が職業的な専門性として成立することが、哲学にとって良いことなのかそうでないのかは、よく分からない。また善悪を決めるようなことでもない。 哲学はいつも時代の子であり、多くの隣接領域のなかでしか、前に進むことはできない。哲学は隣接領域に巨大な変化をもたらすこともあれば、芸術家に霊感をあたえることもある。逆に、隣接領域から多くのアイディアをもらうこともある。レヴィ=ストロースは、多くの神話を収集し、そこに含まれる規則性を明るみにだしてくれた。そこには当然のことながら規則には収まらない事例も多くある。絵画の制作や身体表現(舞踏)の制作の現場に立ち会うことは、機会さえ求めればいくらでも可能である。制作のプロセスそのものを作品とするような作品もある。はっきりと分かることがある。哲学は哲学だけに留まることはできず、哲学に留まってはならないのである。哲学は経験の弾力を回復し、経験の弾力を高める営みである。この経験の弾力を高める試みが、反省の実行と反省の限界の認識からだけもたらされるとは、とても思えない。ガブリエルの才気は、素直に認めてもよい。だがそれ以外にも、哲学は多くの課題領域に開かれている。際限のない課題に開かれてしまう局面に立ち会うこと、それこそ哲学が終わることのできない理由である。
参考文献
河本英夫『オートポイエーシス—第三世代システム』(青土社、1995年)河本英夫『メタモルフォーゼ――オートポイエーシスの核心』(青土社、2002年)河本英夫『システム現象学』(新曜社、2006年)河本英夫『経験をリセットする』(青土社、2017年)河本英夫『哲学の練習問題』(講談社学術文庫、2018年)河本英夫「方法としてのオートポイエーシス」(村上勝三編『越境する哲学』春風社、2015年)73‐93.河本英夫「ゲーテ自然学とオートポイエーシス」(『モルフォロギア』第38号、2016、11)24-36.河本英夫「自然という現実性」(『国際哲学研究紀要』別冊Vol.9、2017)27-52.ガブリエル『神話 狂気 口共笑』(大河内泰樹、斎藤幸平監訳、堀之内出版、2015年)ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』(清水一浩訳、講談社、2018年)クリプキ『ウイットゲンシュタインのパラドックス』(黒崎宏訳、産業図書、1983年)メイヤスー『有限性の後で』(千葉雅也、大橋完太郎、星野太訳、人文書院、2016)ヤニッヒ『制作行為と認識の限界』(河本英夫、直江清隆訳、国文社、2004年)
3 情報という現実性
情報は単独のシステムではない。それはエネルギーやエントロピーが単独のシステムではないことと同様であり、さまざまな活動態の「断面」に留まる。エネルギーは測るための枠を必要とする。この枠のなかの開始点と末端で成立しているとされるのが、「エネルギー保存則」である。またエントロピーはあらかじめ系が設定されていなければならない。大域的な開放系では、エントロピーを語りようがない。エントロピーは、その系のなかで「極大」となって終わる。一切の運動を欠いた平衡状態となるのである。通信技術から見たとき、エントロピーと情報は、類似したかたちで定式化できる。内在的な不均質性の度合いが問われるのだから、同じ定式化を活用しても問題はない。だがエントロピーはある系のなかで極大で終わるのに対して、情報は無限に拡散するように見える。ここに情報の特質がある。また情報は、何かについいての情報でもあり、別のものにかかわるある種の「志向性」をもつ。その意味では、意識や言語に近い性格をもち、世界大の現実へとかかわっていく志向的な可能性をもつ。その点では言語や記号と同様に、ただ平行して作動する多くのシステムの一つなのではない。底引き網のように、網はそれとして稼働するが、網目に引っかかるものは何でも絡めとっていく。この絡めとる網目の大きさを自在に調整できる点が、情報と自然言語の違いである。 網のように世界の現実と絡み合っていく点が、情報の志向性であり、一般的には「何かについての情報」という側面である。他方情報は、自動的に作動する。情報は次の情報に接続されるものは、どのようなものであれ、次の情報を生み出す。精確に言えば、次の情報が生み出され、既存の情報と接続するものは、情報ネットワークのなかに組み込まれ、それとして「情報」となる。ベイトソンの言う「差異を創り出す差異」こそが、情報であることになる。この段階では、「情報ナルシス」という特質が現れてくる。情報はただ別の情報と接続することで、それとして成立する。こうして情報以外の現実性につながる回路と、情報相互がつながる回路での分岐は極端に進む。それが情報システムである。情報は、ネットワークとして、それじたいの内部に訂正可能性をもたない。何かが出現し、それに接続可能なものであれば情報として活用される。そして接続可能性が見込めないものはいずれ消えていくだけであり、いわばゴミになるだけである。それじたいに一切の選択性をもたないものは、定義上「ゴミ」である。 言語・記号一般と同様に、情報も現実とは一対一対応はしない。一つの現実を別様に表記することは表現の可能性を高める。だが誰にも理解できない表現になれば、情報ネットワークに留まることはできない。しかし特定の人間もしくは受け取り手にだけ通じるように改変することはできる。これが「暗号」である。軍事や政治的な陰謀で繰り返し活用されてきたが、文学的な作品ではっきりしたかたちで登場したのは、ポーの「黄金虫」である。ここではアルファベットの統計的な出現頻度に合わせて数字を置き換えていくもので、トリックとしては初級のものである。またごく普通の日常言語的表現に、こっそりと二重の意味を込めるように裏の意味を込めることもできる。これも古くから繰り返し用いられているもので、通常の日常表現に同時に、こっそりと裏のメッセージを込めるやり方である。そうした裏のメッセージが込められていることに敏感に反応してしまうものがいる。ナッシュ均衡を定式化したジョン・ナッシュは、普通の新聞の文章に特殊なメッセージが込められていると読み続けており、自分だけに宛てられた秘密の指令だと読みとっていた。ナッシュの伝記的な作品である『ビューティフル・マインド』では、いくつかの単語は文法的な配列とは異なる輝きを示してつながってしまっている。 他方、情報はネットワークとして疑似自律的に作動し、そこで固有の現実性を創り出していく。一般的には芸術的な創作ですでに実行されているものである。このとき情報と情報制御機構を活用して、現実そのものの内実と範囲を変えていくことができる。事実、「仮想現実」や「拡張現実」において、現実性の幅が決まらなくなっている。そのとき同時に経験のモードも変わっていくはずだが、経験そのものを有効に拡張できるものや、現実性をより豊かにしていくものの内実を決めることが極めて難しくなっている。精確に言えば、経験を有効に拡張できず、世界の側の選択肢を広げることもない莫大な情報が飛び交うようになっている。つまりガセネタやゴミ情報の氾濫である。こうした場面で、何が哲学的な課題となりうるのかという問いが生じる。そしてそれを明示することは簡単ではない。課題を明確にできないのであれば、すでに哲学は困惑と当惑のなかに巻き込まれている。哲学の課題の一つが、筋違いの議論を別様に転倒し、課題の方向性を設定し続けることである。また新たな現実の形成へと向けて、どのような選択肢があるのかを構想することである。つまり状況を前にして、前進可能な問いに転換していくこと、さらにはどのような展開見込みがあるかを構想として提示していくことである。 さしあたり情報ネットワークのなかで、個々人の欲望がどのようになっていくのだろうか。欲望の変質と行く先についての検討を加えておきたい。欲望にかかわる限り、精神分析学的な議論との重なりが大きくなる。統合失調症や躁鬱のような脳神経系の変質を含む病態は、とりあえず除外される。また精神分析は、言語的な語りを治療法の軸としており、身体の振る舞いや運動を活用することはほぼない。つまり精神分析こそ、情報ネットワークに適合的な枠組みをあたえてくれるのである。欲望は、現実性の拡張に応じて、大幅に姿を変える。つまり変貌していく欲望の在り方に焦点があたるように議論を組み立てなければならない。そのためには構造的な図式に変えて、変貌し続けるシステムに置き換えていかなければならない。さらに情報ネットワークの加速度的変化のなかで、人々の行動はどのように変化していくのかについて考察を加えておきたい。総体として、こうした課題設定は、社会精神病理学の装いをもつと思われる。 また情報は単独のシステムではないが、そのことの内実を詰めてみる。自動運転ロボットは、センサーとロボットを別建てでプログラム設定しなければならない。この二つのプログラムは、それぞれがAIのなかでより詳細になっていくに違いない。センサーのプログラムは固有に進化し、モーターのプログラムはそれとして進化していく。それぞれの進化速度は大幅に異なり、進化の幅もそれぞれで異なる。そのときプログラム間の連動をどのようにしてリセットし続けるのかが問われてくる。問われるべき局面がもう一段階上がってくる。そのさいの理論的見通しについて考察しておきたい。
1 情報ネットワークの欲望
情報ネットワークのなかでの個々人の欲望の変化について考察しておいた方が良いと思われる。だがこれを論じるためのぴったりの構想が見当たらないのが実情である。というのも情報は、そもそも感情の制御に適合的に作られたものではない。だが二次的に感情の変化をもたらしてもいる。そこで便宜上ラカンの精神分析を拡張して活用することにする。構造主義者であるラカンの最も一般化された構造的な仕組みは以下のようなものである。
これだけの基本要素を設定しておけば、心的活動のどこに無理が来て、どこに歪みが生じるかを論じることができる。欲望する主体には、それじたいの作動の理由も到達点もない。欲望は、ただ作動する。この特質は、たとえば空腹には理由がなく、また満たされてもいずれ空腹はやってくる。始まりの理由も、終わりの理由もない。活動態を捉えるさいに、アリストテレスは、活動の行きつく果て、すなわち目的を捉えなければならないと考えていた。だが欲望や本能的な欲求には行く着く果てはない。それは生きていることそのものに行く着く果てがないことによる。死は生きていることの向かう果てではない。ヨーロッパ思想のなかにいくつか大きな誤解があるが、「生は死に向かう」というのもその一つである。植物が途中で枯れてしまうことは良くある。しかし植物は枯れることに向かっているわけではない。また自己組織化を基本とする世界では、何かが出現することにも理由はない。事象は事象だから出現するのであって、そこには理由は不要である。そうした理由もなく行く果てもない活動態が、欲望である。ラカンは性的欲求を軸に欲望を考えていたと思われるが、本能的な欲求である食欲、排泄欲、睡眠欲にも基本的に違いはない。しかも付帯的な欲求が次々と分岐していくことは可能であり、情報ネットワークではそうした欲求の変質はいくらでも起きる。また欲望の作動のモードも変質していく可能性がある。ここでは構造主義的な発想に変えて、システム的構想に転換することが求められている。 情報ネットワークが拡大し続けることで目に付く形で違いがでるのは、大文字の他者である。大文字の他者は、基本的には自然言語と文化的な記号の複合体である。ラカンの設定としては、自然言語とその派生態からなる単独のネットワークだと考えてよい。そして言語の特質から見て、これは音声言語のネットワークであり、身体的振る舞いをともなうネットワークである。そのため大文字の他者には、裏側で身体的な振る舞いが張り付いている。ラカンの後期の分類で、象徴界(言語的意味世界)、想像界(イメージ的世界)に並ぶ現実界(身体を含む非言語的世界)は、大文字の他者の裏側にある。この言語的ネットワークでは、欲望や欲求は、こうした言語が語られる環境のもとで形成され、制御される。ここには人間固有の生育的な能力形成が想定されている。ここは人間学的な発想で考えておいたほうが良い。このとき欲望は言語を全面的に自分の制御下に置くことはできない。逆に言語は、欲望を自分のなかに取り込むことはできない。だが両者は密接に連動する。欲望と言語的ネットワークは、密接だが相互に外的である。そうした関係が「外密」である。システム的には「カップリング」と呼ぶべき関係である。そして両者の境界に「無意識」が出現する。この無意識は、言語からはどのようにしても到達することはできず、また言語の合理的な制御にも落ちない。だが言語からは明確に規定できない関係で密接につながっている。欲望する主体から見れば、言語は放棄する可能性がないように、みずからに降りかかってくる。そしてそれがどのように経験に組み込まれたのかも知りようがない。幼少期の言語習得期では、言語はなぜそうしたものなのかもわからず、また選択的に拒否することもできない。つまりおのずと降りかかってしまっているものが言語であり、経験と言語との関係そのものは、経験からも言語からも明らかにならない。未決定な関係のまま密接性が維持されているのが、欲望と言語的ネットワークの関係である。 そこにさらに情報ネットワークという巨大な仕組みが入り、多くの場合文字情報と映像表現を中心とする表現手段をつうじて、際限なく平行する多平行ネットワークに変質していく。こうした言語的ネットワークの情報化にともなう欲望そのものの内実と作動のモードの変化が問われる。 この変化にはいくつものモードがある。情報ネットワークの作動に対応して、欲望そのものの作動モードが変質する場合がその一つであり、たとえば次になにかがもたらされるという「情報の飢」に恒常的にさらされることで、経験は別の作動のモードへと巻き込まれてしまう。そこでは言語と経験のかかわりの変容が起き、経験のモードそのものが変容する。目覚めれば、SNSに接続し、なにかが伝えられていないかを確認する。こうして経験の基本的なモードに変化が及ぶ。経験はいつも待ち受けモードとなる。その延長上に、情報反応性の反射反応が広範な広がりを見せる。まず相手の話を聞く力がなくなる。話をじっと聞き、言葉や言葉の意味ではなく、言葉をつうじて相手の経験を取るような聞き方ができなくなる。自分の経験を動かすようにして相手の経験と連動させるのではなく、経験の手前で、情報という断片化された言葉に反射反応する。そしてただちに「騒ぎ」を起こすのである。おそらくこの延長上では、一般的に言う「理解」さえできなくなる。こうした在り方を情報ヒステリーと呼んでおきたい。この場合、経験に奥行きも懐の深さもできず、言葉に反応し、すでに持ち合わせた自分の枠のなかに配置することを理解に置き換えていく。欠落しているのは、「じっと聞く」「経験に落ちるように聞く」「自分の経験のなにを作動させるかを感じ取るように聞く」というさまざまな聞く経験のモードである。それを欠落させるために、多くのことがわからなくなる。情報を受けて、言葉を振り回すことだけはできる。相手の言葉を聞き、反応しているようだが、いつも反射反応なので、経験そのものが微妙になることも、こなれていくこともない。そしてしばしば周囲からはまったく理解できないような挙動が出現する。ときどき電車の中でも見かけるような光景がある。電車通路のなかで、スマホからワイヤーで何か音楽を聴いているような女性がいる。30歳前後の眼鏡をかけ髪をポニーテイルのように結わえた小柄のかわいい女性である。電車が駅に近づき、つまずくように停車したとき、この女性の後ろにいた中年男が電車のなかでゆられて、この女性の背中に少し触れた。この中年男は、右手で吊革をもち、左手でカバンを抱えている。この女性は突然振り向き、「テメエー、ナニスンダヨー、ケイサツニツキダスゾ、オリロ」と叫び始めた。周囲にいた人の半分は、何が起きたのかという怪訝な面持ちであり、もう半分は「またキレタ」といううんざりした顔である。この女性は居場所がなくなってその駅で下車してしまった。スマホで音楽を聴いているのだから、その状態で発声すれば度起こした大音声となる。しかも電車の中で自分だけで「閉鎖系」を作っており、そこが侵害されたと感じれば、度を越した反応が出る。明らかにヒステリー性の反応である。スマホがらみの情報には、情報一般にふさわしい公共性がない。情報と言いながら特殊な閉鎖性を作る。そこに予想外の介入があれば、ほとんど理由も結末も理解を絶した振る舞いが出現する。いわば「キレル」という事態が頻繁にこともなげに出現する。情報は一般に量的に増大すれば、増大局面に反比例するように、視野も経験も狭くなる。言葉に対して、敏感感応する場面は、基本的に病理的には「神経症」である。神経症全般は、『精神医学診断表』からは項目としては姿を消し、「人格障害」のひと項目に配置されている。いわゆる社会的な不適合の集合体である。神経症の構造的な特徴は、(1)言語行動や行動一般にことごとく裏面で「自己正当化」が伴っていることであり、(2)言葉の範囲と現実性の範囲がほぼ重なっていることである。自己正当化の構造的な支えができている場面まで進んだものが、神経症性妄想、すなわちパラノイアである。一般に神経症は、フロイト、ラカンとも特定の言葉の抑圧から生じると考えている。現代の神経症の特質は、特定の言葉を抑圧している自分自身への自己正当化に力点が移動している。この自己正当化をつうじて、「演技性人格障害」や「自己愛性人格障害」へとこともなげにつながっていく。神経症は、病理的に見れば、統合失調症にもうつ病にも背景的な一部として出現する広範な病理である。それは作為的な自己維持にかかわる無理のことであり、それが行為の無理となって出現する病理である。情報の受け取りは、あらかじめ予期の範囲が極端に限定されている。情報は次の情報の待ち受けの予期しかもてなくなる。そこには他者も環境も自然もすべては作動する情報の外に自動的に区分される。予期があらかじめ限定されていれば、経験の幅も弾力もほとんどが失われてしまう。 情報ヒステリーは、恒常的に特定の枠で情報を待ち受けていることがベースにある。たとえば送られてくるメッセージとともに、あらかじめ待ち受けの枠が用意されており、それが作動すれば自動的、機械的に反応するのである。あらかじめ絞り込まれた予期の枠に対応するような情報が流されるようになり、その情報に反応するのだから、情報量は増えても経験はどんどんと狭くなっていく。この事態は広範に見られるもので、SNSでは多くの場合、情報量の増大が、経験の狭まりをもたらす。待ち受けの枠には、自己主張の枠と、自分が自分自身で禁じている項目とがある。特定の自己主張の枠に引っかかれば反応する場合が、反復性の反射反応であり、いつも同じパターンで、いつも同じような反応を繰り返す。「また同じことを言っている」という反復の基本形が出現する。ここに情動の固着が入る。反射反応だからそのつど当人はすっきりはしているのだろうが、周囲からすれば、なんでわざわざというようなことを繰り返す。これは本人の自動的な情動の繰り返しであるから、言ってみれば、情報・情動ナルシズムである。これが出たときには、その人物は物事をもはや精確に捉えることはできないと考えてよい。ここでは精確に言葉を捉えることが問題なのではなく、経験は特定の感情を繰り返すことに向いてしまっており、ときとしてこの感情に合うように言葉を作り替える。ただ同じ感情を繰り返したいだけなので、すでに経験は終わっているが、SNSに垂れ流せば少数の共感者はいつもいるので、安心を得るためにはSNSに垂れ流すのが手っ取り早い。情報ネットワークには、固着の集合的なささえが恒常的に用意されている。他方、自分自身で禁じている項目にひっかかれば、反射性の「大演説」となる。大演説の垂れ流し場所が、SNSである。この大演説は、誇大妄想性のものにはならない。誇大妄想は、フロイトの言う「投射」を介することがほとんどである。フロイトは「シュレーバー症例」の分析末尾で、投射を定式化している。骨子となるのは、(1)自分の感情を別様なものへと作り替え、自分の感情に自分で気づかないようになること、(2)作り替えた感情が、内発性のものではなく、自分の外からもたらされたものというように外に由来を転化するのである。たとえばある男が、ある女性に好意や思い入れ抱いていたとする。ところがその女性が自分に思いを抱いているので、自分はそれに応じているだけだと、感情の質もしくはモードを入れ替える。感情の由来は、自分自身ではなく、外からもたらされたものに作り替えられる。そしてその女性が行う振る舞いや身振りや言動のなかに、自分に寄せられる思いの証拠を、感覚知覚をつうじて際限なく確認するのである。自分自身の感情の制御に代えて、その女性への「観察」で置き換える。感情の制御は容易ではないが、観察によって際限なくその女性を捉え続けることは、認識の本性にかない、際限なくリビドーの備給を続けることができる。そのため感情を観察という認知へと振り向けること、さらにそれによって仮構された自分の感情を繰り返し確認するのである。フロイトであれば、「被愛妄想」と呼ぶべきものである。これだけのエネルギーが備給されていれば、行動は誇大であり、発話は妄想性を帯びる。 そして情報化社会では、このタイプの誇大妄想は背景に退き、反復性の固着行動となると予想される。誇大妄想の場合、たとえば本当にあの女性は私への思いを抱いているのだろうかという疑念はつねに何度も付き纏い、それを何度も否定していく。この否定に妄想の強靭さが作られていく。そうした鍛え上げられた妄想に代えて、何度も同じことを繰り返す情報ナルシスが前景にでる。その一部が、ストーカーとなる。 感情の発露は、なんらかの行動を帯びる。その行動に、不釣り合いなほどの大袈裟な振る舞いが出現する。ある美大系大学の公開講座で、受講生の女性が、不当な内容の講義を受けたということで大学当局を訴え、それを聞き入れない大学当局を民事で訴えた。見せかけは、「訴訟狂」である。「訴訟狂」と「演説狂」は、典型的な妄想の表現モードである。この公開講座の外部講師には、刺激的な作品を作り続けているアーティストが並んでいる。いわゆる「取り扱い要注意」というアーティストである。こうした講師の講義を聞き「急性ストレス性障害」になるほどの衝撃を受けたとの訴えがなされた。当然のことながら、大学は個々の講師に要望をいちいち出すことはしない。そうなると何が訴えの内実なのかを掴むことは難しい。押し問答の末に、大学当局と公開講座の運営係が自分の要求を聞き入れないので、民事訴訟に及んだというのが、事件のあらましである。一般的に考えれば、聞きたくもない講義を聞かされたのであれば、それ以上聞く必要もなく、その場合には大学当局の事務局に掛け合って、受講料を払い戻すように交渉することができる。公開講座で募集に応じて参加したのであるから、それを取りやめるのである。次に自分の希望する講師陣を挙げて、次の機会にはそうした講師を呼ぶように努力してほしいと要望を出すこともできる。自分の意向に合わない講師の授業が行われたことに不満をもつことは不自然ではないが、それが公開講座を運営する大学のミスだということにはならず、また事態の改善を求めることは不自然ではないが、民事での筋違いの訴えに直接つながるものでもない。本人の主張と法的な社会的制度への訴えの間には、どうにも無理が生じている。そしてそれは多くの場合、自分自身の選択肢を減少させていることから生じている。いわば欲求は発現の回路を極端に狭めている。そして妄想の初期症状の一つである「訴訟狂」のかたちを取る。自分自身の選択肢を減らすことによって出現する不釣り合いな挙動は、感情のもう一つのモードを表している。それが情報・情動[0、1]モードである。情動は本来度合いをもつ。強い情動、ほどほどの情動、弱い情動のように、度合いがある。それは一般に強度性と呼ばれるものである。ここから多くの選択肢が出現する。ところが情報に浸透された情動は、[0,1]という両極化の作動モードを帯びる。情報のなかに含まれる[good, but]という価値感情によって、度合いの判別が効かなくなり、[0,1]のいずれかに両極化していく。場面ごとの選択肢を自分で消していくのである。これを場面ごとに積み上げていけば、言説レベルでは両極化した言説が出現し、その果てで、唐突な「訴訟狂」が出現する。ここには個人的な事情もからんでいる。この女性受講生には、ヌード芸術は崇高なものであるべきだという思いがある。美大生に対して、かつてヌードモデルとして自分の身をさらし、報酬の支払いを受けてきた自分自身の前史への自負もある。その思いは一般的な個人の思いとして尊重されるべきである。だが他者に強制するようなものではなく、また他者にそれに合わせるように思いこむべきものでもない。この女性に見られる「自己愛性の傾向」は、他者への余分な思い込みとなり、過度な筋違いとなって出現する。一般的に見れば、「固有なものは、どのようなものであれ、固有性として尊重されるべきである」。これは「弱者は、弱者として尊重されるべきである」と置き換えても良い。私は個人的には、可能な限りそうであってほしいと思う。しかしそれは個々人の固有の関係性のなかでしか維持されないだろうという思いもある。一般的な社会原則として述べることも、他者に半強制的にそれに同意するよう求めることも、困難である。個々人のネットワークのなかで、徐々に形成されるべき社会的配慮ではあるが、社会的規則として設定されることはない。これが社会的存在のバランスというかたちでしか成立しない事象の固有性である。個々人の個体性にかかわる事象は、おおむねこうしたものである。自己愛性の傾向は、このバランスを崩すことでしか維持できない。 欲望と情報ネットワークとの関係で、情報は、文字情報と映像情報をつうじて膨大な量のものが流されるが、こうした情報が自然言語の発話と異なるのは、情報には語られざる内容がほとんど含まれないことである。自然言語の発話では、まさに語らないことによって意味を帯び、語らないことによって意味の膨らみと奥行きが形成される。その領域が膨大にあるからこそ「言葉」であり、「語り」なのである。常日頃SNSで経験を動かしているものは、逆に多くのことがわからなくなる。 そして情報ネットワークの作動の速度が速いために、情報の授受に対しては、敏感感応が起きる。この速度への対応不全が、情報ヒステリーである。この速度への対応に反復的に応じようとするのが、情報・情動ナルシスである。そのとき経験に奇妙な特質が生じ、そのモードが情報・情動[0,1]である。一般的に考えれば、欲望と言語の間には、緩やかでしかも密接な関係しかない。これが「外密」であった。だが主として、情報の速度を基調とする情報側の変化によって、欲望は出現の仕方を否応なく変えざるをえない。この変化は、いずれは欲望そのものの変化をさらに生み出し続けていくに違いない。 副次的に、感覚神経不全でしかないものが、情報ネットワークで別様に拡張され、別様な効果を生み出すこともいくらでも起きることである。こんな事件があった。ある学生にとって同じ風景が一日に何度も浮かんでしまう。意識の制御とは無関係に、非志向的に浮かんでしまうのである。非志向的な想起というPTSDに広く見られる神経機能不全である。一日に何度も同じ風景が浮かんでしまう。そこでその学生は、像として浮かんでくる同じ人物に向けて、メールを発信し続けたのである。内容は、「あなたはどのような死に方をしたいですか。それを私に伝えなさい。そうすれば私がそれを実行してあげます。」この文面をマシンに残しておき、同じ想起像が浮かぶたびに、同じ文面をリピートで想起像に浮かぶ人物に送り続けたのである。一日に20回を超える頻度である。起きていることは、単純な想起障害である。この事態がSNSにつながってしまった。こうしてこの文面を送り続けられた人の居住する東北地方の県警からパトカーがやってきて、この学生は都内で逮捕され、移送された。21日間の留置場での取り調べの後、近くの市の精神病院に移された。ここで管轄が警察から保健所に代っている。この学生は警察の留置場に置かれ、最後の段階では地検になんどか連れていかれて、立件が難しいと判断されている。精神病院に移されて以降、ひと月ほど経ったところで、私はその病院まで面会に行った。大学関係者の誰かが面会に行かなければ、病院を退院した学業への復帰について、詳細に検討することはできない。精神病院の回廊を進む途上で、散歩していた本人にばったりと出会った。本人の目つきに不自然さはあるが、挙動にはおかしなところはない。ただ社会復帰までには少し時間はかかると感じられた。おそらく服用している治療薬の影響もある。本人に、調子はどうかと私は尋ねてみた。本人は「病院のご飯より、留置場のご飯の方が美味しかった」とだけ無造作に答えた。
ラカンの図式的な構想のなかで、際立っているのが、対象aである。対象aは、心が不安定となり、不安な状態になれば、経験のどこかに出現して、経験に支えをあたえようとするようなある種の安定化のための変数である。通常は消えていて、現前化することはないが不安定状態のなかで出現する。いま眼前に鏡を置き、自分の像を映してみる。映っている像のなかで、自分の姿を消してみる。眼だけが残る。さらに眼の形も消してみる。そうすると鏡のなかからこちらを見ている「まなざし」だけが残る。外から自分自身を見ていて、なにかのきっかけで出現する「まなざし」のことを対象aだと考えておいてよい。ある意味で自分自身の経験の分身であり、経験に外からまとまりをあたえる以上、経験にとっては超越論的な原理である。そうした原理が経験のなかから立ち上がってくれば、反省的な自我に類比した超越論的原理となる。ところが対象aは外からやってくるのだから、外から介在するかたちで経験はまとまりを再度獲得することになる。そして対象aは、多くの場合それじたいでみればほとんどとるに足りないほどのものなのである。たとえば耳のピアスであり、髪を束ねるカチューシャであったりする。意識の焦点化をともなうなんらかの具体的なイメージであれば、対象aになることができる。多くの日本人にとっては、ほとんどかかわりのない原理なのかもしれない。自分の経験のまとまりを支えるような外的イメージをもつ必要はないことが多いのである。なぜラカンは対象aを強調していたのか。それは構想のなかにこっそりと部分-全体関係(換喩的関係)が組み込まれ、全体をまとめ上げるような原理を想定しているからである。システム的に考えれば、システムは作動し続けることによってそれ自体がそのつどまとまりを形成する。そこにはあらかじめ全体を取りまとめるような原理は不要であるだけではない。むしろそんなものはない方がシステム的な動きはスムースになる。システムは緊急時になんらかの支えを必要とする。そう考えるのが構造主義的な発想である。そんなものはなくても、システムは作動をつうじて自己治癒する。ラカンの場合不安定さが嵩じたときに出現するものとして、対象aを設定している。そしてこれが古典的な自己治癒モデルであり、支えを回復するというモデルなのである。全般的に考えると対象aは、自分自身の「原風景」のようなものに近く、いつでも思い起こそうとすれば思い起こせるものである。想起しようとすればいつでも想起できるものに近い。これは経験全般にとって重要な意味をもっているのだろうか。昨日の晩御飯の風景を想起してみる。ある断片的な場面が思い浮かぶ。しかしその5分前の風景もあったはずであり、5分後の風景もあったはずである。イメージ記憶は、いつも特定の場面の切り取りから成立している。この切り取りの理由はよくわからない。固有の意味が含まれているとも思えない。ただそうした個々の場面をともなうイメージがあることは間違いない。そして情報ネットワークのなかでは、記憶に残るような断片の表現が優先されていく。それをうまく設定することは、作品を何度も経験したいというリピートの欲求につながっていく。その場合、対象aは、作品作りのテクニカルに活用すべき変数の一つになるのである。それは記憶にかかわっている。あるいは個人史にかかわっていると言ってもよい。そしてそのなかに経験全体にとっての彩をあたえるようなイメージ像はあるに違いない。だがそれがどのように経験の安定化や経験の自在な作動に関与しているのかはよくわからない。私にも思い起こそうとすれば思い出せるイメージ像がある。保育園の砂場でくたくたになるほど遊んだ夕暮れに、西日を受けてまぶしそうに遠くを見ている自分自身のイメージ像である。それが何を意味し、何を支えているのかと問うてもほとんど不明である。一時的に意識の全域をまとめるほどの効果があるとも思えず、また非志向的に浮かんでくるほどのものではない。ラカン自身は、対象aの内容を、乳房、糞、声、まなざしだとしている。対象aはどこかで意識の深層に触れるものでなければならない。そして文化的な要素のなかで、意識の状態をリセットして、状態を変えていくものだと拡張解釈すると、対象aの機能性がにわかに広がってくる。通常はごく常識的な普通の人であるのに、なにかのきっかけで「まるで人が変わったように特殊な状態になってしまう」ことにかかわる要素がある。この場合、対象aはもはや防衛的なものではなく、むしろ当人をトランス状態に移行させてしまうようなものである。宗教的なものであれ、芸術的なものであれ、この場合の対象aは感覚的確信に満ち、平均以上に能力をさらに発動させるように働く。情報ネットワークが、そうした要素の起動にかかわることはあるに違いない。そしてそれは犯罪にもかかわるような場面まで敷衍することができそうである。かつての「少年A」は、「バモイドオキシ」という自分のための神をもち、「アングリ」という自分自身のためだけの儀式をもっていた。少年Aの中学生時代である。それらをとおして犯罪を実行し続ける自分自身を安定化させていたのである。そして犯罪を続けているときも、社会に対して、サカキバラセイト(榊原聖人)を名乗り、発信を続けた。この局面では犯罪性向はよくわからないが、特殊なトランス状態が起きている。対象aの範囲を防衛的働きの範囲を超えて拡張していくことは可能である。その場合には、言語そのものの在り方も言語の意味も変えてしまう。あるいは言語の裏側を支えている身体行為を全面的に別様に組織化することもある。つまり対象aは自分自身を組み換えるほどの威力をもつ範囲まで入れることはできる。シュレーバー症例のなかでシュープに至る局面で、シュレーバー自身のイメージの確信は、「女になって犯されたら、素晴らしいことだろう」というのがある。大学の演習の時間に、この話をしながら感想を聞いてみたら、男子学生で夢のなかでそうした情景は何度も出てきたというものや、いつもそうした思いをもっているという男子学生が数名いた。あるいは「言葉で食事について語ることと、言葉を食べることは等しい」というような事象的なイメージが語られることもある。この場合には、口腔の作動で、空気の調整(語ること)と咀嚼の強さ(噛むこと)が、同じ活動態の別の局面での現われとなる。対象aを拡張していくと、統合失調症の範囲まで経験を広げることができる。統合失調症は、言語的な秩序の解体などではない。それは末端の結果だけを見ているのである。むしろあるイメージをきっかけとして、ラカンの図式そのものを組み換えるような活動を行うことがある。統合失調症の圧倒的な多様さは、構造的な図式そのものの解体を意味している。言語の解体は、すでに言語的構造の特徴ではなく、別様のシステムが作動し始めたことの副次的な結果である。それは言葉が出現する場所で働いているシステムであり、そのシステムに自分の経験を連動させようとすれば、たとえ精神科医であっても特殊な訓練が必要となる。
ラカンの図式で、左下に配置された「自己」は社会的な自分の像である。社会のなかで、自分自身だと他者に振り向けられた像をもたないのであれば、社会存在としてやっていくことはできない。これは他人向けに作られた自分自身の像である。そして情報ネットワークのなかで、この「自己」の像が、一通りで決まらず、偽装や仮装に満ちたものとなり、ときとして分裂したまま使い分けるというような事態も起こりうる。ユーチューブの画像には、時として、アニメ風のパーソナリティが配置されることがある。「三千院心」「カッパえんちょうー」「みいたん」「AKARI」等々は、原稿を読み映像身体の定型の振る舞いはあるが、印象画像に近い。それでも公的に作り出された「自己」である。情報内容、雰囲気、論調に応じてキャラが出るように設定されている。情報ネットワークのなかでは、代理自己や匿名自己、偽装自己は、ごく普通のものとなる。SNSのなかでは偽装された自己と現実の自己との乖離は、ごく日常的なものとなる。 東京新聞の女性記者Mは、官房長官への筋違いの大演説質問で有名で、本人の固有名でハラスメントの名称が作られるほどだった。SNSでは、ターゲットとなるものがあれば、ただちに仁義なき戦いが起きる。仁義なき戦いの大半は、便乗組である。そのとき女子中学生の発起人名で、M記者支援署名のSNSでの呼びかけがなされ、膨大な数の支援署名が集まった。ところが女子中学生が発起人とされたこの呼びかけを行ったのは、実際には50代のただのおばさんだったことが判明し、呼びかけアカウントはただちに削除された。こうした騒ぎを繰り返しながら作動を続けるのが、情報ネットワークの特質である。韓国ネタを発信し続けた「三千院心」と「カッパえんちょうー」は、ユーチューブ当局に送られた集団的なクレームに晒されて、コンテンツが削除されたり、発信活動が停止されるという事態が起きた。「カッパえんちょうー」については、本人名の偽造コンテンツが何種類か配信され、チャンネル乗っ取り騒動まで起きた。ネットワーク用の「自己」の仮構はいくらでも可能であり、生身の自己の悲惨さに対応して、ネットワーク用の自己は「過激な姿」をとる。犯罪になるほどの過激な言論をネットワーク内で行うものを捕まえて見れば、無職で一般社会では誰からも見向きもされないような人物だったりする。SNSの自己と一般社会の自己が乖離したままになることは普通のことである。社会的存在としての自己は、社会内に実現される自己像のことではもはやなく、代償自己、偽装自己、演出自己等々の機能性に粉飾されたものになっている。 こんなふうに考えていくと、ラカンの図式も総体としてほとんど変質してしまうことがわかる。欲望する主体のなかの食欲、性欲、睡眠欲、排出欲のような基本的な欲求だけではなく、小さいがいくらでも肥大化できる欲望が次々と生み出され、現実を覆ってしまうのである。たとえそれらが付帯的な見せかけをもとうとも、本人の行動を強く促すのであれば、無視できないほどの要因となる。また大文字の他者は、任意に作動を続ける枝葉のようなもので、どの程度の広がりが進行しているのかをおそらく誰も見分けることができない。ミニネットワークは際限なく作り出され、同じ日本語を使っているのだからメッセージは通じるはずだという期待も、気づいたときにはスルーされてしまうほどの分岐が進行する。これらのネットワークに応じて、欲望の形態も変化していく。 こうした場面で、対象aも、経験が不安定になったときの防衛的な役割を果たすだけに留めることは、むしろ不自然である。内実として、対象aは一つに留まる必要もない。むしろ経験をさらに弾力をもたせ、より有効に作動させるためにどのようなイメージをもちうるかという課題に対応するように再設定したほうが良い。経験の安定化ではなく、むしろさらに新たな創造性と生産性に向けてどのようなイメージが有効かという問いのもとに設定できるような経験の範囲に、対象aを置いたほうが良いのである。こうなれば、大文字の他者(言語・記号)も、対象aも、自己もことごとく変貌したものになると予想される。 手続き的経験と理解 現代の情報化による変化のなかに含まれるいくつかの精神病理的変容にかかわる共通の事柄がある。SNSは、基本的に理解可能性だけに向けられたメッセージからなる。数学講座や初級力学講座のようなものは、適合性が低い。ここに知識のわかりやすさや伝達しやすさの問題ではなく、知のなかに含まれるモードがかかわってくる。数学、物理、論理、システム、経済、法等々は、手続き的な知識である。精確に言えば、手続き的経験である。この手続き的経験で獲得されるのは、技能である。これはたんなる理解されて記憶されるような知識ではない。最も極端で単純な事例で言えば、自転車に乗ることは技能の修得であって、知識の理解ではない。自転車の乗り方は「分かってはいるが、乗ることができない」という事態は、知能の在り方を取り違えた筋違いのかかわりなのである。記号論理学を学び損ねた学生がときとして質問にやってきて、回答の仕方を覚えるのですかという。これこそまさに筋違いの経験である。経済や法の知識も、現実に自分自身の行為に対しての選択肢と指針を提供するものであって、言葉として「需給バランス」や「サプライチェーン」という言葉を理解することではない。少なくとも、こうした語に対しては仕組みのなかにどこに変数や選択肢があるのかを探るような理解の仕方をしなければ、ただの言葉を覚えることに留まってしまう。とするとSNSの言説では、経験の動かし方が身につかず、言葉の理解しかもたらされない知識が飛び交うことになる。見かけ上の情報量は多いのに、経験がとても狭い者たちが大量に出現する可能性がある。多くの情報を振り回しながら、経験はほとんど動いておらず、結局のところ「ほとんど何もわからない」者たちが生まれていく。それがSNS時代の情報である。 教育現場では「アイクティヴ・ラーニング」がしばしば語られる。教員の側からの知識の伝授だけではなく、学生の参加を促すことが必要だという趣旨のことが説明として付け加えられることが多い。しかしこれでは授業形態のモードを示しているに過ぎない。必要なことは、授業をつうじて「手続き的経験」を修得することであって、これは知識を理解することではない。手続き的経験の必要条件は、「分かること」だけではなく、「できること」であり、経験を行為として実行する能力である。異なる選択肢の可能性を感じ取り、別様にも進んでみることができるという経験の習得と、立場や観点から意味を理解するということはまったく別のことである。 手続き的経験は、経験を一つの行為として実行する。それに対して、理解は提供された知識を配置し、場所をあたえることである。そして経験にそれの位置価をあたえることである。その場合、経験のなかに配置された知識は、すでに消費ネタになっている。手続き的経験は、別様に進んでみることの素材として、知識を受け取り、それを別様に進むことの手掛かりとして活用するような経験の仕方である。情報化社会では、間違いなく、手続き的経験が減少し、消費ネタ理解が増えていく。 語句敏感感応性 そのさい経験は新たな選択肢へと向かって展開していくのではなく、言語的な理解によって次の発信をどうするのかに力点が移ってしまう。経験はきわめて小さな幅のなかをさらに小さな起伏を求めて作動するようになる。ここに「情報の飢え」が生じる。 ここには大小の病的な言動が出現する。語に反応する「語句敏感感応性」や、語への固着をともなう「語句原理主義」と呼ぶべき事態である。言葉は事実や現実をなんらかのかたちで表現するものである。語句をそのままとることはなく、語句とともに発せられた現実の輪郭を感じ取っていくことが、一般的な語句の経験である。ところが語句そのものに経験が収斂し、語句が何か特定の事柄を含んでいるかのような経験の硬直が起きるのである。このときどこに選択肢があるのかという経験の流動性が消えてしまう。それを欠けば経験の基本性格が失われてしまうのだが、本人はそのことを感じ取っている様子はなく、また欠落していることに思い至ることもない。「語句敏感感応性」は、奇妙な緊張を抱えていて、自分自身の言動の訂正可能性をほとんどすり減らしてしまう。語句に関連づけられる意味や出来事であれば何でも持ち出すことができるために、情報的支離滅裂が常態化する。論理性も事柄の関連性もほとんどないまま、語句がかりに連想的につながるものであれば、あらゆることが持ち出される。そのあげく誰から見ても信じられないほどの言説が飛び交う。多くの情報を持ち合わせているように見えながら、学習の能力も減退してしまう。多くの経験が持ち込まれているように見えながら、学習そのものが減退するために、かかわらないほうが良い、言いたいだけ言わせて放置したほうが良いと感じられる広範な発信とそれに対応する人々が出現する。信じられないことだが、誰にとってもこうした人物は複数周囲にいる。恒常的に嘘を平気で言うが、「サイコパス」に見られるようなその場しのぎのでたらめではない。むしろ本人はどこか一生懸命なのである。真偽や事実/非事実、あるいは論理的に整合であるかどうかが一切問われることもなく、また本人はそれを吟味することもできず、ともかくも相手が反応してくれるまで、何でも持ち出し続けるのである。反応欲求とでも呼ぶべき奇妙な振る舞いにまとわれている。そうして多くの人は、こうした人物には積極的無視によってしか対応できないことにやがて気づくことになる。それらの発言は反応することを求めている言説と発信なのだから、反応しないことが最善なのである。サイコパス サイコパス(精神病質)は、いまだ精神医学的な規定も明確になっていない病態である。犯罪者のなかにも一定頻度で含まれているが、犯罪者であるからサイコパスであるわけではない。逆にサイコパスだから犯罪者というわけでもない。だがいくつかの理由からサイコパスは、なんのためらいもなく、またいささか唐突に、犯罪に踏み込んでしまう。また人格障害(社会的適応障害)ではあるが、明確に責任能力はある。犯罪そのもののもみ消しも画策する程度には、犯罪もしくは犯罪状態への対応能力はある。 ロバート・D・ヘアは、心理家として刑務所で面談を行ううちに、奇妙な犯罪者の一群がいることに気づくようになった。そして統計的に多くの精神疾患の症例を集めて、そこからいくつかの特徴的な指標を取り出したのである。それによってサイコパスの輪郭は、かなり明らかになった。ところがヘアの資料は、すでに犯罪者と認定されているものから多くのデータを収集しており、サイコパスのなかでも特異な一群の症例を扱っている印象を受ける。この病態は、多くの症例から詳細な分析を行わねばならない。というのもサイコパスは犯罪にかわかる頻度が高く、かつ周囲の人が犯罪に巻き込まれる頻度も高い以上、できる限り多くの人に理解可能なレベルまで病態に届かせなければならないからである。たとえばヘアの記述に以下のようなものがある。
レイ(仮称)は、私ばかりか誰をも欺く信じられない才能をもっていた。おしゃべりがうまく、嘘もかんたんにつき、それがあまりに流暢だったり素直だったりするので、ときにはもっとも経験豊かで猜疑心の強い刑務所職員でさえいっとき警戒を解いてしまうほどだった。私が会ったときには、前科がいっぱいあり(あとでわかったことだが、その後も前科がふえつづけた)、成人してからの人生の半分以上を刑務所で過ごし、しかもその犯罪の多くは凶暴なものだった。それでも彼は、更生する用意があることを私や私などより経験豊かな人たちに納得させ、打ち込めるものを見つけたので犯罪に対する興味が完全に薄れたと信じこませた。レイは果てしなく、のらくらと、あらゆることについて嘘をついた。嘘と矛盾する点をファイルに見つけてそれを指摘しても、彼は少しも悪びれなかった。あっさりと話題を変え、まったくちがう方向に話をもっていった。
こういう風に描かれると、ただのおしゃべりで嘘つきで、ペテン師のように読めてしまう。そして誰しも身近にもそうした人がいる、と思い起こされる。ただしそのとき思い起こされているのは、ほとんどサイコパスではない。サイコパスの難しさは、一つ一つの特徴を取り出すとその程度の人間なら身の回りにもいると思い当たることである。そしてそれによって理解しやすい人間類型へと接続して、誰しもわかった気になれるのである。そして特徴として取り出されるものを列挙すると、「口達者で皮相的」「自己中心的で傲慢」「共感能力の欠如」「ずるくごまかしがうまい」「浅い感情」「衝動的」「行動のコンロールが苦手」「責任感の欠如」「反社会的行動」というような項目が並ぶ。しかしこれらは問題成人ではあるが、一定頻度で出現するような問題成人であるようにも見える。先のヘアの引用文章で、こうしたレイのような人物も、自分の言葉を最初から疑っているような人を相手なら、もはや欺くような話はしなくなるであろう、と推測できる。むしろ警戒するはずである。またその程度の能力は備えている。いつも同じようなパターンで話すような「妄想様」人間ではない。にもかかわらず自分の話術のなかに簡単に相手を巻き込めるという自信と自負は、人並み外れたものがある。多くの場合、この自信と自負は隠されているが、最終的に本人を支えているのは、現実社会のなかで配置できないままになっている本人自身の由来の不明な「プライド」である。実際にサイコパスに会って話してみればわかるが、強い自己愛性人格障害とそれが満たされない現実の社会への不満が含まれており、それは自分自身の仮構へとつねにつながっていく。おそらくサイコパスにとって、SNSはまたとない住処なのである。 売名欲求 大文字の他者は自然言語を基本とするが、発話は特定の人物による特定の人物からの発話であり、声や身振りをともなっている。そして特定の情景や特定の音声言語に反応し、この反応した経験を押しとどめ安定化する仕組みの一つが、主体が自分自身で及ぼしている「抑圧」である。できるだけ反応しないように押しとどめている状態を、「落ち着いた意識」だと自己認識している場合が多い。 ところが情報ネットワークに流れる夥しいコンテンツは、多くの場合、受信者の集合は特定されず、無作為に放り出されていく。また発信する側も、時としては匿名であり、場合によっては偽名である。精確には誰が発信したのかもわからない。誰が発したのかもわからず、受け取り側も不特定多数で宙空吊りになったコンテンツが流れるのである。 発信する側は、こうした状況下で発信したコンテンツに反応してもらいたい欲求がある。おそらく自分が発信しているにもかかわらず誰も応答しないのであれば、肩透かしであろうし、ひとときの寂しさもあるだろう。とすれば虚偽であろうが、事実と異なることであろうが、誰かに反応してもらいたいという強い欲求が働く。それは身体的な反応を呼び起こすほどの効果をもった発信となる可能性が著しく高くなる。つまりビンボールまがいの効果をもつ発信を行うのである。反応してもらいたい欲求は、伝統的に語られる「承認欲求」とは別のものである。ある情報に反応があることは、次の情報の作動に加担できることであって、別段承認しているのではない。Goodという応信は、次にも引き継ぐことができるということであって、内容の良さのことではない。言説は、事実や正当性を競うのではなく、次の反応を期待して、反応があることを目指してなされることになる。このとき発信者には、内容とは別の「自分を知ってもらいたい」「自分の声を聴いてもらいたい」という思いが込められることになる。仮想名(無記名)の発信と不定集団の受信ネットでは、ともかくも発信する側は「知ってもらいたい」という欲求が前景化する。伝統的な承認欲求に促されてはいるようにみえるが、実際に起きることはいわゆる「売名行為」である。「売名行為」では、発信する思いと発信された内容に大きな乖離が含まれ、発信する思いは理解可能だが、発信された内容はそれにまったく対応しないというような事態が起きる。「私の思いを知ってほしい」という願いは理解できても、その内容はバカバカしいほど希薄なことが多い。デッドボールまがいの発信が行われれば、ただちに騒ぎとなり、両軍の全選手が飛び出してきて、乱闘となる。場合によっては、観客席のフアン同士も乱闘を始めることがある。そして場数を踏めば、これもただの「見せ物」であることはただちにわかる。一般的に言えば、プロレスのようなショーの一部である。ショーであれば、その場が過ぎれば、ひと時の騒動で終わりである。ただし野球の場合、この騒動の起因となった選手や行為は処分対象となる。それは審判団が行う業務である。だがSNSには、こうした審判はいない。 なにか事件が起きれば、ただちにそれに便乗したい欲求が恒常化する。一般には「炎上」と呼ばれる事態である。炎上があれば、通常の火災であれば、放火犯がいる。この放火犯が特定できないのが、SNSである。炎上の便乗は、実際の火事現場でもしばしば起きる。炎上の仕組みは、局所的に急速に広まるインフルエンザに似ている。誰が最初にインフルエンザを持ち込んだのかが特定できない。そうすると感染が収まるのを待つしかない、というような事態にもなる。インフルエンザの場合には、周囲は予防接種をして広がりを防ぐ。ところが「炎上」はまさに炎上機会を待ち望む欲求に、好機をあたえるだけになる。現実と情報 自動車同士の狭い道路での接触事故を想定する。二人の当事者がいる。事故であれば、警察を呼び、契約している保険会社に連絡を入れ、人の身体に損害がない限り、民事に留まる。この場合には警察は不介入である。保険会社が双方の間に立ち、責任割合を決めて、支払いの仕組みを確定してそれで終わりである。このとき事故の当事者が、警察や保険会社に連絡を入れると同時に、SNSに相手を批判する投稿を行ったとする。この投稿は、現実の問題解決にはまったく不要で、かつときとして余分な騒動を創り出し、問題を別の方向へと変質させる場合がある。言語表現は、あらかじめ反応することが見込まれる範囲に集中する傾向が生まれ、この傾向は言語表現に対して、「敏感感応性」という特質を広範囲に生み出してしまう。これは作為的に作り出された「反射反応」のことである。ひとたび閾値を更新した反応性は、次々と敏感感応域へと進んでいく。周囲からは何故反応しているのかがわからないようなことが起きる。あるいはなにか度を越していると感じられる反応が起きる。過度の反応に対して、さらに敏感に反応するネットワークが出来上がっている。「敏感感応性」は、ネットワークのなかで増幅される方向で半ば自動的に進行する。欲望は、言語表現と通信の仕方に多くのチャンネルをもつようになる。見も知らない二人が、挨拶を交わすように二人だけのコミュニケーションを形成することもあれば、誰も見向きもしないような発信を延々と繰り返すことも起きる。誰も受け取らない発信は、大演説となり、ただ流されているだけになる。また特定の人物に向けての訴えとなり、それが執拗に繰り返される。演説狂と訴訟狂は、「妄想病態」の頻繁に見られる外形的特徴である。これがSNSに流れ出すようになり、妄想性病態は、ごく月並みなありふれた光景となる。実質的に演説狂は、消滅する。つまり発信の平均水準が、すでに演説性を帯びてしまっている。だが訴訟狂は、特定の誰かを訴えるのだから、繰り返し炎上のネタとなる。訴訟狂の欲望は過度に満たされ、訴訟の味を覚えたものは、繰り返し同じタイプの訴訟を実行するようになる。演技性人格障害と自己愛性人格障害 情報ネットワークは、それに反応してくれる人の連鎖で成立する。すると偽装してでも、反応のありそうな発信を行ってしまうという欲求に巻き込まれてしまう。事実や内容を超えて、反応を求める方向に向かうので、そこに不可避的に「演技性」が絡まってしまう。「演技性人格障害」は、恒常的に平準化されたものとなる。演技性人格障害の最初の項目が、「注目されていなければ、面白くない」という内容であり、このとき自分と情報ネットワークというごく単純な社会関係だけになってしまっていることがわかる。ここでは裏側で、実生活上の選択肢の不足が起きている。朝起きて散歩すれば、散歩の途次、近所の人たちとの挨拶から始まる。コンビニの店員との軽い挨拶をし、お昼前にはスーパーに買い物に行く。そこでも軽い立ち話をする。こうした日常の社会像と、演技性に装われたネット上の社会像は、確実に乖離していく。日々の日常で正規の職も決まらず、鬱積にまとわれた社会像の青年が、ネット上の像として、まっとうな演説を行ったり、特定の人物を繰り返し攻撃したりする。自己という社会像には、ネット回路に応じて確実に乖離が含まれるようになる。その場面で出てくるのが、「自己愛性人格障害」である。内容は、自分は社会にとって貴重な人材であり、重要な人たちとかかわるべきであり、本来そうした人たちと交わるべき人間だと確信しているように、自分自身への過大評価と、多くの場合普段は覆い隠されているプライドからなっている。そしてそれを満たそうとすれば、確実に本人にとっての本人自身の余分な作為が生じる。大文字の他者が分岐し、小さなネットワークが形成されることに応じて、自己の像は内在的な解離性を帯びる。こうしていくつかの典型的な特徴が浮かび上がる。(1)情報ネットワークは、小さなネットワークであり、外交機密も特許情報も社内機密も顧客情報も基本的には、ネットワークのなかには出現してこない。情報ネットワークは、あらゆることに開かれているように見えながら、ごく狭い現実しか扱うことができない。しかもほとんど重要性のない情報である。そのためSNSの経験は、気づいたときには視野が狭まり、ガセネタを知識だと勘違いする強い傾向が生まれる。時として政治家のメッセージがツイッターに流れることがある。どういう反応が起きるのかを観測気球のように探っていくメッセージがほとんどで、公式発言ではない。(2)情報ネットワークへの関与の比率があがるにつれて、行為の選択肢が減少していく。「わかること」と「できること」の乖離が生まれ、この領域では行為の選択肢を増やす方向での試行錯誤の訓練を積む機会を、おのずと放棄していることになる。評論家のようなことを述べる人たちは増えるが、その裏側で、新たな経験の回路に踏み出す機会はおのずと失しなわれてしまう。そして個々の表現は、立場や観点から繰り出される「政治性」を帯びる。言葉に反応して、ただちに「差別用語」だと認定して騒ぐようなことはごく普通に起きる。たとえば「ハゲ」という言葉は、お笑い系の芸人が売りネタとして使ったり、それなりの風貌をそなえたジャーナリストがトレードマークとしてつかったりする。他方元国会議員が、自分の運転手に「このハゲ」と呼んだりする。言葉は、使われる状況や環境を離れては意味がない。それにもかかわらず言葉を単独で取り出し、その語の社会的価値を勝手に自分で決めてしまうのである。そこに軽度のイデオロギーが出現し、社会病理が発生する。言葉の単離は、情報ネットワークの特徴の一つでもあり、それを差別用語だと認定することが社会的主張だと思い込んでいる人たちが出現する。そこで起きることは、錯誤と固着の繰り返しだけなのだが、本人にとってはそれが一つの充実となる。 (3)欲望は、食欲、性欲、睡眠欲、排出欲のような基本的な欲求以上に、本来であれば測定誤差のような欲求がそれじたい肥大して、大きな比率を占める。しかも行為の選択は限定されているので、欲求と行為の間には筋違いのつながりが次々と創り出される。これらの欲求のなかには、自己承認欲求、他者攻撃欲求、被害者意識欲求等々の欲求が含まれ、自動的に肥大する。これが固着という現象になる。同じ欲求を繰り返してしまうことは「反復脅迫」に見えるが、起きていることは、同じ欲求への固着である。朝起きてただちにスマホを覗き、時間が空けばスマホを覗き、いわば慣性の法則にしたがうような惰性的行為が生まれる。これは情報刺激への飢えを生み出し、飢えが次の飢えにつながるような仕組みとなっている。「情報待ち受け欲求」という新たな欲求が出現する。持続的に仕事をし、自分を追い込みながら仕事をするという経験の仕組みにとって、情報待ち受け欲求は、実際には相当に大きな妨害になっている。おそらくまとまったかたちで本を読む者たちが激減する。 (4)社会のなかでどういう自己像をもつかは、社会生活を行う上では欠くことのできない生活の知恵に属する。ただし情報ネットワーク上の自己像と現実社会のなかの自己像は、極端にずれたものとなる。ここには演技性人格障害と自己愛性人格障害の広範な裾野が準備されている。こうしてラカンの図式に変容をかけて以下のような図式となる。
2 作動する情報と身体のなかの情報
情報は間違いなく、単独のシステムではない。CPで数学的な演算を実行させるとき、オペレーションを続けて、演算の結果を短時間で容易に算定する。このとき演算だけが作動するのではなく、オペレーションそのものを作動させているいくつものプログラムがある。多くはPCに内蔵されたプログラムである。自動的にオペレーションが続いているように見えながら、そのオペレーションの作動をもたらすプログラムは自動的に動いている。これはごく一般的な作動プログラムであり、「作動の順番」、「条件的分岐」、「繰り返し」を含んでいる。情報には、情報を成立させるプログラムや情報と連動するプログラムがつねにある。 またCPのオペレーションの結果は同じであっても、どのようなプログラムが動いているのかを判定することはできない。同じ結果を出すCPが同じプログラムを実行していることにはならない。つまりオペレーションの結果とプログラムの間には乖離があり、どのようにして同じ結果が出たのかもわからない。オペレーションの作動の結果は、同じプログラムが作動したことの証拠にも論拠にもならない。 かつてクリプキが『ウイットゲンシュタインのパラドックス』で議論した、「自分一人で規則に従うことはできるか」という問いの立て方は、実は「自分だけの規則」は果たして可能かという問題ではなかった。自分だけの規則を「規則」と呼んでよいかどうかという問題でもない。クリプキは、とても重要な問題に気づいていながら、問題の核心を取り違えていた。この問題の要点は、たとえ正しい回答を出している場合であっても、どのような規則に従って正しい回答を出したのかが決まらない、という点にあった。2000年前後で日本で盛んに議論していたことが、AIによって別様に拡大されたかたちでさらに明確になった。58+67という演算を行って正しい解答を出しても、どのような規則によってその解答に到達したのかが決まらない。AIがまったく異なる規則で同じ解答を出すことは、ほぼ自明なことである。情報では、視覚情報、身体情報、言語・記号情報を区別しておいたほうが良い。同じ情報でも異なる性質をもつからである。情報ネットワークで問題になるのは、言語・記号情報である。これはネット型になる場合には、情報量、情報速度、情報価値が主要な変数となる。情報量と情報速度は、5G、6G、7Gと順次格段に進行するが、それじたいはしばらくすれば生活上での慣れが来てしまう技術である。生活上でただちに慣れが来るものは、たとえ短期的に目覚ましい革新に見えても、それじたいは大きな変化ではない。ネット型の情報でより大きな影響を持つのが、ネットワークの規模であり、プラットホームを誰が握るかを競う競争である。これは情報社会学の問題であり、情報経済の問題である。中国のファーウェイが5Gで最大規模のプラットホームを形成した場合でも、ただちに5,5G、6Gが形成され、新たな世代企画で5Gからは翻訳できず、5Gには翻訳できるフォーマットを作ることは難しいことではない。そのため最大規模のプラットホームをどこが握るかは、しばらくは決着が付きそうにない。ネット型経済価値の代表が暗号通貨であるが、暗号通貨を使って多くの店舗で活用できても、その範囲では汎用性の高い「商品券」に留まってしまう。ガス、水道料金のような公共料金の支払いに使えたり、納税に使うことができなければ、社会的な公共性を獲得するところまでには進むことができない。また通貨に留まっている限り、金融商品にはならない。各種債権は金融商品であるが、債権を暗号通貨で発行したり、暗号通貨そのものが債券であったりすることはない。同じ「情報」という名称でも、異なることが言われている。色についてみると、裸眼で色相互の違いから約35000程度の色合いの区別はできる。これは人間の眼の識別による。AIセンサーでは、さらに細かく区別できる。とするとその区別に相当する自然言語は存在しないだけではなく、記号を活用したとしてもその区別に対応させることはできない。センサーは映像のまま分析を行い続けることができるが、その分析は、言語情報に落ちてくることはない。人間の眼でも同じことが起きているので、この視覚像と言語的表記の関係のギャップに奇妙なところはないのかもしれない。だが問題はその先である。たとえば医療現場で撮られたCTスキャン像の比較から、センサーは独自の読み取りを行うことがある。センサーの眼は、人間の裸眼以上に優れているのだから、センサーの分析は人間とは異なるものとなり、人間とは異なる判断を下すこともできるようになる。それを人間は一つの「有効な示唆」として受け取り活用することができる。さらにその先で、センサーの判断から人間はどのような学び方ができるのかが問われる。センサーはおそらく有益な示唆の一つを提供してくれるに違いない。しかしそのことがセンサーにしかできないのであれば、人間の経験はつねにセンサーを重要な示唆を提供しつづけてくれるもの以上にはならない可能性が出てくる。一般に、PCデータ処理が有効であるのは、通常の人間の経験の範囲内で、それまで人間の判断ではうまく処理できなかった領域へとAIが踏み込んでくれる場合である。作者レンブラントという名前が着いている絵に、どこかレンブラント本人以外の人が書いたものなのかという問いに対して、レンブラントの絵の特徴を読み込ませて、そこから外れるものを指摘させることはできる。著者名というのは、代表名であって、近現代的な「作者」とは異なることは良く知られている。そこでAIに判定させて、一つの絵のなかのどの部分は別の人が描いたのかを判定させるのである。こうした事態は人間の予期の範囲内にあり、およそ想定でき、AIの指摘する判定も理解可能なものである。ダ・ヴィンチは天才的な画家だが、絵にはあまり関心がなかったと見えて、本人が描いた作品は、はっきりとわかるもので11点しかない。それ以外に、部分的にいくつかダ・ヴィンチが手伝ったと感じられる作品もよく知られていて、それは人間の眼でもはっきりとわかる。そうした理解可能性の範囲にあるものをAIで改めて分析させて、AIの判定だとして提示することはできる。第一級の国際雑誌『ネイチャー』に投稿された論文で、社会の複雑性と宗教的信仰の推移をいくつもの指標から分析したものがある。社会的複雑性の指標を、人口、領土、行政府のレベル等でおさえ、宗教的信仰については、儀式の頻度やモード、超自然的信仰の有無などの指標を盛り込んで、データベースを設定して解析をかけてみる。一般的には宗教的信仰が獲得されて後、高度な共同体が作られ、それによって社会的な複雑さが形成されてくると思われていたテーマ領域である。実際にAIに分析をやらせると、社会の複雑さの増大が、宗教的信仰の獲得に先行していたという事実認定をAIが行った。従来の人間的解釈が、AIによって覆されたと話題になったことがある。しかし同じデータベースを使って、指標を少し変えるとまた別の結論が出た。AIをつうじた議論で盛り上がりが起きることは、それじたいは望ましいことだが、こうした議論の範囲では、すべて理解可能な範囲にある。タイプの異なる論じ手が増えているが、それでもすべて理解可能なのである。この段階では、知識や見方の数は増えているが、人間の経験が広がったわけではない。理解の彼方 センサーの行った分析から、人間はどのようにしたら経験を広げていくことができるのだろうか。ごく単純に言えば、先ほどのCTスキャン像の見方やそれの分析について、人間は何を手にすることができるのだろうか。おそらく視覚像とそれの分析、またそれらとは直接は接点のない人間の言語への変換の問題であり、プログラム間の変換の可能性をめぐる問題が生じると予想される。これは人間の眼そのものの限界に対応している。AIセンサーは、自分のプログラムを詳細にする方向でさらにプログラムそのものを分節させ、判断を求められればデータに合わせた判断を行う。だが人間にはそこで何が起きているのかが分からない領域がある。自然言語の特質は、自分でもやってみることができるということを、基点としており、それが学習の基本でもある。人間の経験にとって実行可能性のないものから、学ぶことはできない。AIがたとえ素晴らしい提言を行ったとしても、人間の実行可能性を超えたものは、受け入れるか拒否するかのいずれかになる。これが人間の能力からみた「臨界点」である。CTスキャンの像から、AIの出すデータを受け取り、「およそこんなことを示しているだろう」という理解可能性が及ぶ範囲がある。そこを超えてしまうと「何が言われているかがわからない」という理解を超えた範囲に到達し、そこからやがてそれを受容するか、拒否するかのいずれかしかない状態へと進んでいく。これが臨界点である。対応に[0,1]が出現してしまえば、そこでの人間の能力の形成はもはや期待することはできない。また理解を超えた領域でのAIの判断が、正しいのか間違っているのかがわからないのである。情報は技術的には[0,1]の組み合わせで作られているが、経験はそうした仕組みにはならない。ここでは情報と経験の乖離は、構造的な必然性がある。身体情報 身体と視覚センサーとの落差は、さらに大きい。というのも身体に本来的な触覚性の情報は、視覚情報とはまったく別のモードで作動するからである。触覚情報は、たとえば机の上のざらつきや起伏を感じ取り、区分する場面では、およそ4000種程度の区別ができる。認知的に判別できる度合いは、かなり細かい。視覚的に色の違いは、35000種程度可能だと言われている。色の違いの認定に比べれば、オーダーが一桁劣るが、それでも相当に細かな認知ができる。この色の識別の場合でも、光の量や対象の周辺の明るさによって、大幅に変化する。感覚は、感知可能なものと感知可能でないものを区分する働きである。これが感覚のコード形成である。そしてコードの枠内で、さまざまな細分化が起きる。ここがプログラム的認知である。音の場合には、50ヘルツ程度の低周波は、音として聞こえないが、振動として皮膚で受け取っている。高周波の場合にも音としては聞こえないが、脳神経系が関与し受け取っている広大な領域があり、ことに20キロヘルツあたりに、脳にとってとても快感をもたらす波長域があることが知られている。一般には、コードは安定しており、コードの内部で認知が差異化をつうじて詳細になる。故美空ひばりが、「か」の音に対して二重の振動数で発声していたことが、今日ではわかっており、それが美空ひばり特有の情感を作り出していたことも知られている。ところで机の上をゆっくりとなぜる場合と、一定の速度をもってなぜる場合では、判別される机の起伏やざらつきは、まったく異なってしまう。そのことは身体運動の維持に必要な限りでの認知しか行わず、身体行為にとって「余分な」情報は、おのずと「無視」されることによる。早足で歩きながら、足の裏でこまごまと地面を認知していたのでは、とても歩行はできない。歩行の維持にとって不要な認知的情報は、おのずと無視される。感知可能性を決めているコードが変化して、情報とならなかったのではなく、むしろ情報を「潜在化させてしまう」ような「無視」が働いていると考えたほうが良い。無視とはつねに創造的無視である。触覚は、視覚とは異なる仕組みで働いている。これが身体運動と認知が連動する仕組みであり、視覚的認知情報と身体動作は、情報による指示でつながっているわけではない。そのため逆に単独で取り出された情報は、奇妙な仕方で運動とつながっていく。情報は、無視とは別の仕方で出現する構造的な不自然さを備えている。哲学の困惑 このことは伝統的な認識論に、重大な異論を申し立てることになる。実はアリストテレスからカントまで、基本線では「視覚」をベースにして哲学の構想が組み立てられている。心穏やかにして身体や感情を動かさず、世界を精確に捉えるという認識の仕方は、アリストテレスではテオリア(観照)と呼ばれる。個物を作り上げる質料-形相の二つの要素で、質料を客観から受け取り、形相を主観性に備わったカテゴリーに置き換えて、両者が対象として構成されるという仕組みに転換すると、カントの認識論となる。このとき認識は、物から触発を受けて質料を受け取り、主観性という加工の仕組みを用いて、表象を形成する。認識は表象にまでは及ぶが、物自体に到達することはない。素材となる質料を受け取り、それを認識が加工するという仕組みは、視覚がこうした認識のべースとなっていること意味する。他の感覚であれば、基本的に直接接触であるため、物とぶつかり、物の舌触りがあり、物に由来する感触があり、物からの振動がある。物に触れ、それを感じながら、自分の手を感じるという仕組みになる。これが身体をベースにした認識の基本である。このとき物に触れて「感じる」という働きと、触れている自分自身の手を「感じる」という二つの働きは、まったく異なっていることがわかる。一方は対象認識であり、他方は身体内感である。ここでは視覚をベースにしたこととはまったく別のことが起きている。哲学が「行為」をうまく語ることができない理由がここにある。視覚と身体行為とは、繰り返し連動そのものを形成し続けなければならない領域である。そして多くの場合、行為の遂行にとって無駄な認知を回避しながら認知と行為の連動は形成される。この場合には、認識から行為が誘導されるだけではない。現在のセンサーは、視覚情報をデータ化するのだから、身体運動への適合の場面では、いずれ従来型のモデルとは異なる課題が生じる。たとえばアメリカのイチゴ農家では、イチゴ取入れの大型機械が活躍している。センサーがイチゴを見つけ、見つけたイチゴに触手を伸ばして熟れ具合を認定して、その触手がイチゴを摘み取り、大型機械の後ろに備えた籠に入れていく。この場合には、センサーで読み取る能力は幾分かずつ細かくなるが、モーターの動きはまったく同じパターンである。センサーから受け取ったデータを忠実に実行していくだけである。自動運転制御装置も、事情は同じである。自動運転機器の最大のものは、航空機である。離陸と着陸以外は、航空機は自動で運行している。船舶も似たようなものである。公海上を運行する船舶は、他船舶とすれ違う場面以外には、設定された航路を自動的に進むだけである。この自動制御の場面は、一般のオートイマトンの制御と同じで、リスク変数が一定値を超えなければ、同じ作動を繰り返してよいというプログラムで成立している。リスク変数の数もごくわずかで良く、別の飛行機の移動を近距離で感知したとか、海のなかに巨大な生き物の往来を感知した場合には、警報音が鳴り、そのとき場合によっては自動運行を手動に切り替えて、操縦士が運航を担う程度でよい。センサーは新たなデータや判断を獲得していくが、それによってモーターの作動の仕方がさらに詳細になるわけではない。ところが陸を走る車では、制御変数の種類と数は、比較にならないほど膨大である。閑散とした田舎道を走っている間はまだよい。都市部に入れば、対向車、信号、横断歩道をする人と動物、予想しにくい自転車の往来、高層ビルから発せられる微弱な電磁気、時として生じる落雷による電波障害と短期停電等々では、制御しなければならない多くの要因がからんでくる。衛星からの位置情報は、いつでも攪乱させることができ、また意図的に誤情報を流すこともできる。ロシアとウクライナのクリミアをめぐる戦争のときには、ロシアによるセンサー攪乱によって、ウクライナのミサイルや地上兵器は、徹底的に無力化されてもいる。そのつどリスク変数が閾値を超えて警報音を発するのであれば、場合によっては自分で運転したほうがましだということにもなる。それでも学習能力のあるAIであれば、こうした変数に対応するための技能を順次身について行くだろう。実際スエーデンで行われているように、無人街路清掃車は、歩行者のほとんどいない時間帯に、信号だけは守りながら、単純労働を繰り返している。しかしこれは電線を使って走る電気電車の運転手を無人にすることの延長上にあるだけである。この範囲内でも相当に難しい問題は実際に起きている。たとえば対向車線のある交叉点で、自動運転自動が右折するためには、対向車線を反対向きに走ってくる車をセンサーで敏感に察知し、右折可能かどうかを判定しなければならない。相手の車の速度と速度の変化率、交差点までの距離(時間)の縮小の度合いを読み、右折可能かどうかを瞬時に判定しなければならない。当然のことながら横断歩道をわたる人間は、同時に捉えていなければならない。センサーの処理しなければならないデータは多様で膨大である。高度なセンサーの開発と学習機能の高度化には、まだまだ隙間が多すぎる。京セラの開発した高度センサー「ライダー」は、赤外線反射とレーダーを組み合わせ、障害物を認識する仕組みだが、相手の動きを読むプログラムがどこまで形成されるのかは不明である。情報の時間 移動しながら眼前の物体を捉える場合、人間の認知では、自分自身と物体の間の衝突までの時間を知覚している。物が飛んでくるときに接近の度合いは、衝突までの残り時間で知覚され、たとえば走り幅跳びの踏切板のように身体をそこに合わせる場合にも、残り時間が知覚されている。ところが人工的センサーは、地図上の位置情報と位置の変化だけで物の接近や移動を捉える仕組みを採用せざるをえない。というのもセンサーにとって、時間はあらかじめ外側に設定された座標軸だからである。物体の接近と衝突までの時間は、空間的な距離の縮小で二次的に割り出されるだけになる。ある意味でセンサーは一度も主体的であったことがない。主体性はつねに2次的に割り当てられた駆動体である。センサーには、基本的に時間経験がない。このことは制御変数の一つが最初から欠落していることを意味する。センサーとモーターのカップリング 制御情報変数の獲得だけではすまない場面が、次の段階である。動く車の運転の細かさに対応するための運動制御の技能の獲得が必要となる。道路脇を歩く歩行者が反対方向から来る自転車を避けるために、道路の中央にいくぶんか出かかったとき、それを察知してそのつど停車したのでは、車の運行とは言わない。センサーによる感知に対して、運動体はつねに複数個の対応可能性をもつ。AIではセンサーによる識別の技能向上と、モーターでの対応可能性は、一対一にはならない。センサーとモーターは異なるプログラムとして設定されると思われる。そうなるとプログラム間の連動である「カップリング」の仕組みをどのように設計していくのかが、重要となる。そしてそこには一対一の対応関係がなくても、作動を維持できる仕組みが必要となる。この問題は複雑で根が深い。人間の発達過程で考えてみる。人間の場合、歩行が実行できるようになるのは1歳前後である。その手前では、移動能力がないまま認知能力は形成されていく。言語音を聞き取ることができるようになるのは、かなり早く、生後4が月程度から聞くことはできるようになると言われている。視知覚で人物を見分ける能力も形成されている。センサー側の能力の形成は、運動能力とは独立に形成されて行く。歩行できるようになるとセンサーと歩行能力の連動を形成しなければならない。このときセンサー側の能力も、運動能力に合わせて再度形成される。物の運動を知覚するさいには、運動獲得以前には、ある物が別の物の陰に隠れたり、ある物が別の物を隠したりする「遮蔽」の知覚から行われている。ところが運動能力が獲得されると、物の運動は、ある位置から別の位置への移動で知覚されるようになる。物の運動は、空間的な位置座標で行われるようになる。空間や位置移動の獲得は、みずから運動することができることに遅れてくる。すると物の運動の知覚でさえ、センサーのプログラムを作り替えて、センサーとモーターの連動を形成しなければならない。この事例だと、モーターの能力形成に応じて、センサーのプログラムさえ組み換えていることになる。人間の能力形成でみれば、運動能力の向上に応じて、認知能力は改変され新しく組織化される。そのとき運動の制御に活用されている情報が、生態的環境情報である。運動の速度調整や運動方向の調整に活用されているのが、オプティカルフローである。これは運動しながら認知されている情報であって、静止したセンサーが捉えた情報を元に運動が促されるのではない。オプティカルフローは、たとえば長い廊下を歩きながら、壁の通り過ぎていく度合いや変化の度合いのことである。変化についての情報は、AIだと微小時間記憶をもとに組み立てられるのだと思われるが、変化率にはおそらく当分対応できそうにない。運動するものにとって、運動の調整要因となるのが環境情報であって、環境情報から動きが作られるのではない。このあたりがAIと作りがまったく異なる点である。環境情報から動きが作られるように誤解が生じたのは、最晩年のギブソンが、「アフォーダンス」という誤った命名をしたからである。この誤解は、ギブソンのそれ以前の業績や成果を台無しにするようなものでもあった。情報から行為が促されるのではなく、行為のさなかで行為選択と行為制御のために活用されるのが、情報である。そしてAIではこうした情報の処理は、これからの課題であるように思える。モーターは、身体とはまったく別の作りをしている。実際にはモーターは駆動体であって、それによって動かされる身体は、たんなるボディである。ところが人間の身体は、触覚性の認知を備えた自分自身で動くものであり、たんなる被駆動体ではない。水の中で水泳の動きをするとき、水から押される感触をうまく活用するのでなければ、泳ぐことさえできない。こうしたことをセンサーで捉えることは容易ではない。身体の表面にセンサーを付けることとは異なることであり、身体の動きのさなかで生じる感触こそ、感じ取られるべきものである。こうしてみるとAIによって形成される自動運転自動車には、多くの変数が欠落していることがわかる。AIプログラムは、ある手続きに進むさいに、複数個の可能な手続きがあり、その手続きの選択が、その次の手続きの選択に影響をあたえ、この繰り返しのなかで有効な選択とそうではない選択が決まってくる仕組みが含まれているはずである。この手続きの進行の有効/無効の区分が、AIの行う「判断」と呼ばれる。オートマトンに複数個の分岐が入れば、それぞれの分岐で前に自動的に進むことのできる回路を探り当てているはずである。そのときセンサーの有効性を決めるさいには、データの細かさ、データの整理の速さだけが問題になるのではなく、モーターのプログラムをどの程度改善するのかを指標する「カップリング回路」と、その指標が必要になる。センサーのデータだけ細かくなって、モーターのプログラムが改善されなければ、実質的な駆動体としては粗暴な運転しかできないことになる。そしてこれは気の遠くなるような作業であると現時点では予想される。誰もいない直線の夜道を延々と走る場合には、国際線の飛行機や大型船舶と同じ扱いでよい。だが自動運転自動車では、事情が異なる。 カップリングの典型事例で考えてみる。典型例として、ゲノムとタンパク質の連動がある。この場合には情報上の指令は、ゲノムからだけなされる。だがゲノムの作動のためには、RNAや多くのタンパク質の支えが必要である。ゲノムは、必要なタンパク質を作りだすが、そのさいには2,3割のまがい物のタンパク質が作り出され、それらはたんぱく質の活動ネットワークに組み込まれることはなく、再度分解されて次のタンパク質合成の材料として活用される。つまりこの程度のミスは、生物学的な試行錯誤のなかに含まれる。その場合には、既存のタンパク質とは異なっていても、それでも有効に機能する末端のタンパク質が含まれていてもおかしくない。 ところがAIは、こうした場面での試行錯誤を減らす仕組みが組み込まれていない限り、学習能力だと呼ばれないことになる。自動運転車の場合、試行錯誤とは事故が起きてもおかしくない状態のことである。AIは事故を起こしながら学ぶことはできない。しかしその試行錯誤の幅が一定程度含まれ続けることがなければ、学習の幅は維持されようがない。ゲームのプログラムの自己形成とは異なり、プログラムの試行錯誤には損傷が含まれる。ここがAIの一つのジレンマである。事故の可能性を減らせば、学習の幅が狭くなりモーターの改善の可能性は狭まる。他方モーターの改善の可能性を広く設定すれば、事故のリスクは高くなる。これはAIのカップリングのさいの「試行錯誤のジレンマ」とでも呼ぶべき事柄である。AIの場合、情報処理だけであればどんどんと高度になる。だが運動制御は、それはそれで固有にプログラム化される。そのときセンサー側のデータ処理速度とモーター側の処理速度は、簡単には対応しない。人間の身体では、広範にデータを捨てる仕組みが備わっている。いわば「無視」と呼ばれるものである。無視があるので、プログラムのリセットが効く。AIによる自動運転自動車は、正直に言えば、学習の仕方が狭すぎるのである。おそらくAIは、多くの変数を欠落させた状態で、2次的に有効に機能する状態を見出していくに違いない。まぎれもなくそれは新たな学習の仕方だが、人間がそこから何かを学ぶには、あまりにも乖離が大きすぎる。特定の能力を過度に利用することは、他の能力の発現を抑制する。この宿命を最初から背負っているのが、AIである。
参考文献
大海悠太他「身体知研究会」『人工知能研究』(2019年9月)629-634 ギブソン『生態学的視覚論』(古崎敬他訳、サイエンス社、1985年) クリプキ『ヴィットゲンシュタインのパラドックス』(黒崎宏訳、産業図書、1983年) 佐々木正人・三嶋博之(編訳)『アフォーダンスの構想』(東大出版会、2001年)佐々木正人・三嶋博之(編訳)『生態心理学の構想』(東大出版会、2005年)シャノン『通信の数学的理論』(植松友彦訳、ちくま学芸文庫、2009年) 高岡詠子『チューリングの計算理論入門』(講談社、2014年) 西垣通『AI原論』(講談社、2018年) フロイト『フロイト全集 11巻、「症例シュレーバー」その他』(新宮一成他訳、岩波書店、2009年)ヘア『診断名サイコパス』(小林宏明訳、ハヤカワ文庫、2000年)松尾豊『人工知能は人間を超えるか』(角川書店、2015年) メルロ=ポンティ『見えるものと見えざるもの』(伊藤康夫他訳、法政大学出版、2014年) ラカン『エクリ』(宮本忠雄他訳、弘文堂、1981年) ロンバート『ギブソンの生態学的心理学』(古崎敬他訳、勁草書房、2000年
哲学の困惑 ――科学哲学的試論
2019年12月20日 発行
著者 河本英夫 (私家版)
印刷・製本 文京堂